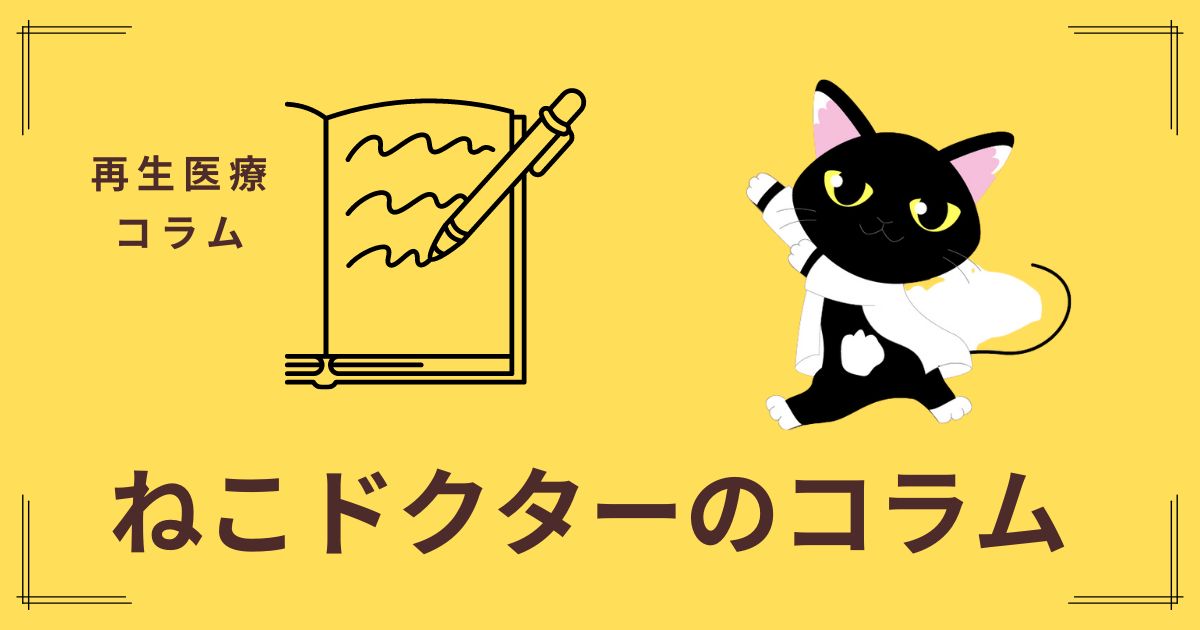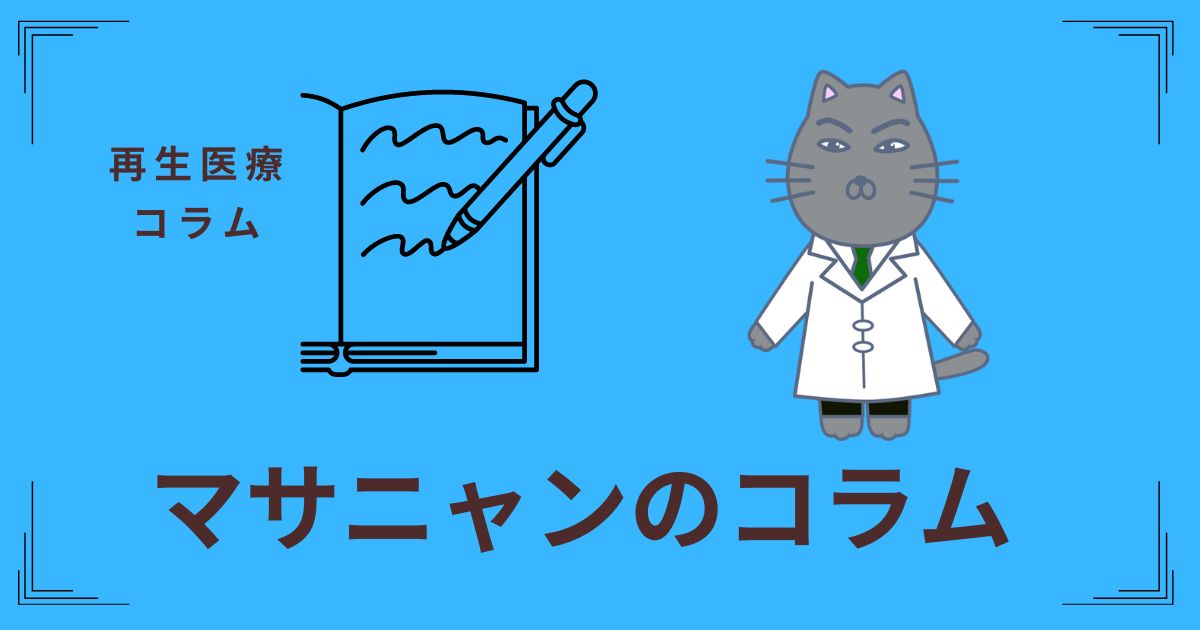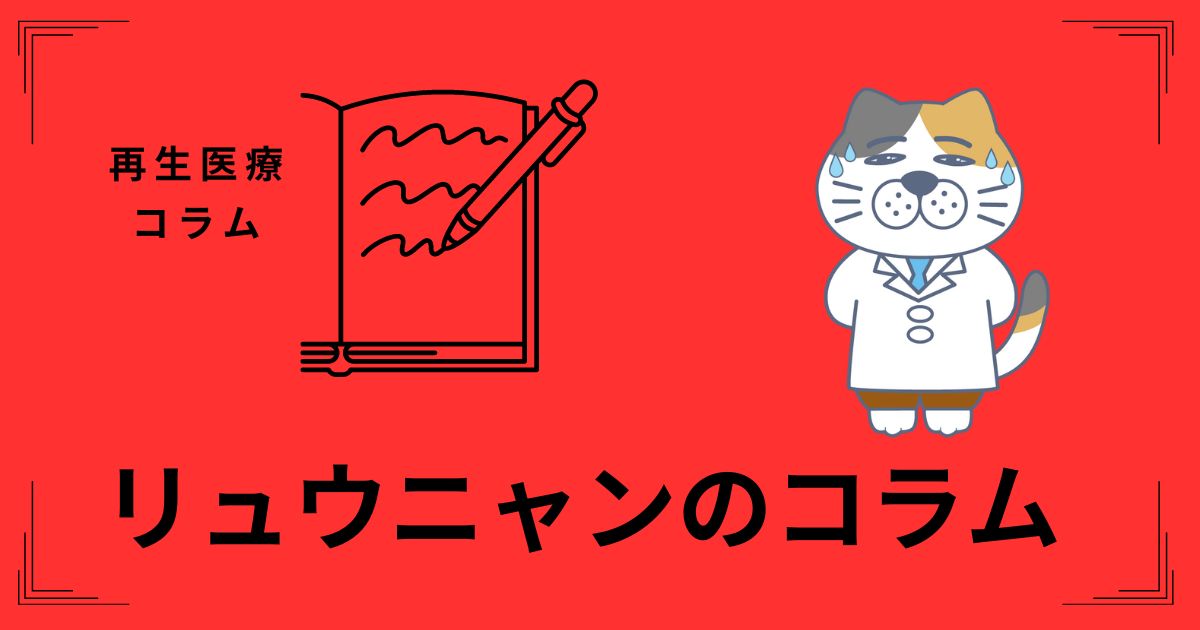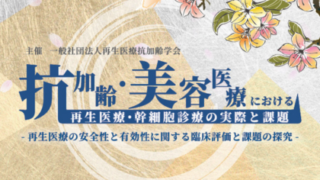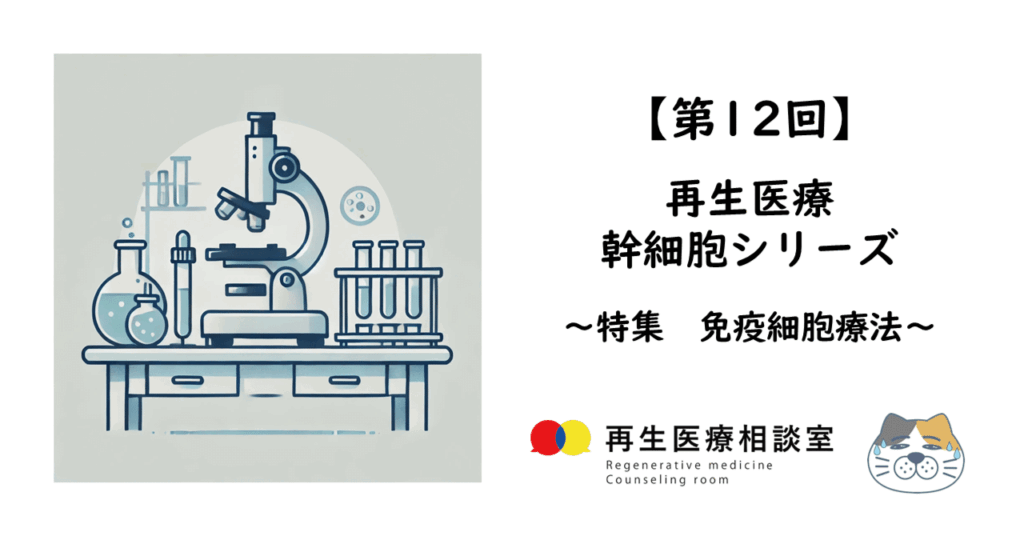
こんにちは、リュウニャンです!
前回は造血幹細胞(HSC)とそれから分化する免疫細胞についてお話ししました。免疫細胞は感染症やがんと日々戦ってくれている、私たちの身体の“守り手”でした。
今回はその続きとして、日本の自由診療でも注目されている「免疫細胞療法」について特集の形で解説していきたいと思います。自分の免疫の力を使った最先端の治療法とはどんなものなのか、ぜひ最後まで読んでみてください。
人間の免疫システムの全体像
まずは免疫システム全体のしくみをざっくり見てみましょう。
私たちの体内には、病原体(細菌やウイルスなど)や体内で生じた異常な細胞(がん細胞など)から身を守るための防御ネットワークが備わっています。これが「免疫」の仕組みです。
免疫の担当部隊は主に白血球と呼ばれる細胞たちで、血液やリンパ液の中をパトロールしながら異物を発見すると攻撃します。
免疫は私たちが生きていく上で欠かせない防衛システムであり、日々無数に発生している細胞のミスや侵入者から身体を守ってくれているのです。例えば健康な人でも1日に約5,000個ものがん細胞が生まれますが、免疫細胞がそれらを見つけて排除しているおかげで体は健康を保てています。
こう聞くと、免疫ってとてもありがたい存在ですよね。
免疫の種類
私たちの免疫システムは大きく分けて「自然免疫」と「獲得免疫」(適応免疫とも言います)の2種類があります。
自然免疫は生まれつき備わっている即応型の防御システムで、異物(抗原)に出会うとすぐに反応して排除に当たります。反応は迅速ですが手当たり次第に似たパターンの異物を攻撃するため、細かい対象の違いにはあまり対応できません。また過去に出会った異物の記憶を残さないので、同じ病原体が再び侵入してきても初回と同様に一から防御を始めます。
これに対し獲得免疫は、人生の中で病原体に感染したりワクチンを打ったりすることで後天的に身につく免疫です。最初に異物と遭遇した際には対応に時間がかかりますが、一度戦った相手の情報を免疫細胞が「記憶」するため、二度目からは格段に速く強力に対処できるようになります。この記憶能力こそが獲得免疫の大きな特徴で、後ほど説明するワクチンもこの仕組みを利用したものなのです。
免疫を担う主な細胞たち
次に、免疫システムで活躍する主な細胞を紹介しましょう。
免疫の主役は白血球ですが、その中にもさまざまな種類があり役割分担しています。代表的なものを挙げると以下のようになります。
好中球
白血球の一種で、血液中で最多の割合を占める食細胞です。好中球もマクロファージと同様に病原体を貪食・殺菌して排除しますが、特に細菌や真菌(カビ)に対する防御の最前線で活躍し、感染初期に大量動員されます。化膿した傷口に白い膿が見られるとき、その主成分は感染と戦って死んだ好中球です。
マクロファージ
主に自然免疫を担う大型の免疫細胞で、その名の通り外敵を「貪食」=文字どおり食べて処理する能力に優れています。体内に病原体などの異物が侵入すると、マクロファージは素早くその部位に集まり、異物を次々と包み込んで消化・分解し、除去します。例えば皮膚に細菌が入った場合、周囲のマクロファージが細菌を捕食し、酵素で分解処理することで感染の拡大を防ぎます。この過程でマクロファージはサイトカインという情報伝達物質も放出し、血管を拡張させて免疫細胞を集めたり、発熱などの炎症反応を引き起こしたりして免疫防御を助けます。
また、マクロファージは単なる「掃除屋」ではなく、捕食した病原体の断片(抗原)を自らの表面に提示し、T細胞にその情報を伝える役割も担っています。こうしてマクロファージは適応免疫(獲得免疫)への架け橋ともなり、異物排除において多面的に活躍します。
さらに体内では、マクロファージが古くなった細胞や壊れた組織片を処理することで組織の恒常性維持にも寄与しています。
樹状細胞
少し聞き慣れないかもしれませんが、免疫の世界では“司令塔”と呼ばれる重要な細胞です。樹状細胞は体内をパトロールして異物(病原体やがん細胞の目印)を発見すると、それを体内に取り込みます。貪食した病原体の詳細な情報(抗原の断片)を小さな「枝」のような突起に掲げながらリンパ節に移動し、T細胞やB細胞にその情報を素早く提示します。この情報提供によりT細胞が活性化し、適応免疫応答が開始されます。樹状細胞はまさに自然免疫と適応免疫の橋渡し役であり、ワクチンが効果を発揮するのも樹状細胞による抗原提示が適切に行われるおかげです。
リンパ球
獲得免疫をになう中心的な細胞で、細胞受容体によって特定の抗原を認識し、さらにT細胞とB細胞に分かれます。
T細胞には大きく分けて2種類が存在し、それぞれ役割が異なります。
ヘルパーT細胞は他の免疫細胞を助ける司令塔のような存在で、マクロファージの貪食・殺菌を補助したり、B細胞の抗体産生を促進したりします。
一方、キラーT細胞はウイルスに感染した細胞やがん細胞上の特定の抗原を認識し、その細胞を直接攻撃・破壊します。例えばキラーT細胞はパーフォリンやグランザイムといったタンパク質を標的細胞に放出し、細胞を内部から死滅させることでウイルス感染細胞などを排除します。
このようにT細胞は特異的な抗原認識にもとづいて標的を選び、強力な免疫応答を引き起こします(さらに、一部のT細胞は制御性T細胞へ分化し、免疫反応が行き過ぎないようブレーキをかける役割も担っています)。
B細胞の最大の役割は抗体(免疫グロブリン)の産生です。活性化したB細胞は形質細胞(プラズマ細胞)へ分化し、大量の抗体を分泌します。抗体は血液や粘膜中に放出され、病原体(抗原)に結合してその働きを妨げたり、無力化(中和)したりします。例えばインフルエンザウイルスに対する抗体はウイルス表面に結合して感染力を抑えるほか、病原体をマクロファージなどが処理しやすいよう目印(オプソニン化)となります。また、一度出会った抗原に対してはメモリーB細胞が体内に残り、次に同じ病原体が侵入した際には迅速かつ大量の抗体産生を行うため、より効果的な免疫応答(免疫記憶)が成立します。
ナチュラルキラー(NK)細胞
文字通り“生まれながらの殺し屋”という名の細胞で、リンパ球の一種ですが獲得免疫ではなく自然免疫に属し、生まれつき備わった「型にはまらない」方法で異常細胞を排除します。NK細胞は常時全身をパトロールし、ウイルスに感染した細胞や腫瘍細胞(がん細胞)を他の免疫細胞の協力なしに直接攻撃して処理します。NK細胞はT細胞のように特定の抗原の認識や免疫記憶をもつことはできませんが、標的細胞に異常のサインがあると、それを感知してただちに殺傷活性を発揮します。その攻撃手段はT細胞と似ており、パーフォリンという分子で標的細胞に穴を開け、グランザイムで細胞内の自己崩壊(アポトーシス)経路を誘導するものです。そのためNK細胞は、ウイルス感染初期や腫瘍細胞の発生に対する一次防衛として重要な役割を果たし、適応免疫が働くまでの間に増殖する異常細胞を食い止めています。
以上が主な免疫細胞たちです(他にも好酸球・好塩基球や、感染部位での肥満細胞、補体といった要素も免疫に関与しています)。
自然免疫の部隊には主に好中球・マクロファージ・NK細胞などが含まれ、獲得免疫の部隊にはT細胞・B細胞(リンパ球)が含まれます。
それぞれ役割は違いますが、最終的な目的は「自己(自分の体)を守り、非自己(外敵や異常細胞)を排除すること」です。
免疫機能と疾患の関係
免疫不全
免疫機能が低下した状態では、健康な人なら問題にならないような病原体によって感染症が発症しやすくなります。このように宿主の免疫防御能の低下によって起こる感染症を「日和見感染症」と呼びます。免疫不全を招く原因には、例えば後天性免疫不全症候群(HIV感染症によるエイズ)、抗がん剤治療やステロイドなど免疫抑制剤の使用、白血病などの血液疾患、先天的な免疫不全症(原発性免疫不全症候群)など様々なものがあります。
免疫過剰
免疫系は本来、ウイルスや細菌など外敵から体を守る防御システムですが、ときに過剰に反応しすぎることでかえって自分の細胞や組織を傷つけ、さまざまな疾患の原因になります。無害なものに対して過敏に反応してしまう花粉症やアレルギー疾患や、自分自身の細胞を敵とみなして攻撃してしまうリウマチのような自己免疫疾患がその代表です。
ワクチンの仕組み
ワクチンはまさに免疫の「獲得免疫」の力を利用した医療です。
例えばインフルエンザワクチンでは、不活化したインフルエンザウイルスの一部(抗原)を前もって体に入れます。すると「初めて異物が来たぞ」と免疫系が反応し、獲得免疫がゆっくり立ち上がって抗体産生や記憶細胞の準備を始めます。
この一次免疫応答では多少時間がかかりますが、接種後に体内にはインフルエンザに対するメモリーT細胞・B細胞が残ります。いざ本物のインフルエンザウイルスが侵入したときには、二次免疫応答ですぐさま記憶細胞が活性化して大量の抗体を産生し、ウイルス増殖を食い止めてくれるのです。これにより発病や重症化を防ぐのがワクチンの目的です。おかげで天然痘やポリオのように、人類が根絶に成功した感染症もあるほどです。免疫の記憶能力は、私たちが病気に打ち勝つ上で非常に心強い味方なのです。
免疫細胞療法の全体像
ではいよいよ本題の免疫細胞療法について見ていきましょう。
免疫細胞療法とは、その名の通り「免疫細胞」を使った治療法です。具体的には患者さん自身の免疫細胞をいったん体の外に取り出し、人工的に元気をパワーアップさせてから再び体内に戻すというアプローチをとります。患者さん自身の細胞を使うので拒絶反応が少なく副作用が比較的軽いとされています。一方で、免疫細胞を体外で扱うため高度な設備や技術が必要で、コストもかかる治療法です。
現在、この免疫細胞療法は日本では公的医療保険がきく標準治療としては位置付けられていません。大学病院などで臨床研究が行われたり、一部は「先進医療」という形で提供される例もありますが、多くは保険適用外の自由診療として民間のクリニック等で提供されています。日本では2014年に「再生医療等安全性確保法」という法律が施行され、免疫細胞療法を含む細胞を用いた治療を提供する場合はあらかじめ計画を提出して厚生労働省の認可を受けることが義務付けられています。提供施設は第三者委員会による審査を受け、安全管理措置を講じた上で治療を実施することになっています。こうした制度により、患者さんが安心して免疫細胞療法を受けられる環境を整備しようという取り組みが進められているのです。
NK細胞療法とは
NK細胞療法は、患者さん自身のNK細胞を利用する治療です。
NK細胞は先述のように、生まれつき備わった“がん細胞やウイルス感染細胞を見つけ次第倒す”リンパ球でした。しかし進行したがんでは、NK細胞が十分に働かずにがん細胞の増殖を許してしまうことがあります。そこでNK細胞療法では、患者さんの血液中からNK細胞を含むリンパ球を採取し、体外の培養室でNK細胞を増殖・活性化させて体内に点滴で戻します。培養の際にはNK細胞を元気に増やすためサイトカイン(免疫活性物質)を添加し、数日~2週間ほどかけてNK細胞の数を何百倍にも増やします。こうしてパワーアップしたNK細胞を体内に送り込み、がん細胞の攻撃に当たらせるわけです。
NK細胞療法のメリットは、自分自身の細胞ゆえに副作用が少ない点と、幅広い種類のがんで理論上適用しうる点です。実際、現在クリニックなどで提供されているNK細胞療法は肺がん・胃がん・乳がんから血液のがんまで、がん種を問わず利用されているケースが多いようです。副作用としては点滴時の発熱や寒気、倦怠感などが報告されていますが、重篤なものは少なく比較的安全と考えられています。これは元々体内にいたNK細胞を戻すだけなのでアレルギー反応などが起きにくいためです。
一方、NK細胞療法には課題や限界も指摘されています。
まず、NK細胞は万能ではなく、がん細胞全てを認識できるわけではないという点です。一般にNK細胞が標的として検知できるがん細胞は全体の約60%程度とされ、残りの40%は見逃してしまう可能性があります。つまりNK細胞療法で攻撃しきれないがん細胞が残存しうるのです。このためNK細胞療法は単独よりも抗がん剤や他の治療と組み合わせて補助的に使う方が望ましいと考えられています。実際に臨床でも、標準治療と並行してNK細胞療法を行うケースが多いようです。
もう一つの課題はエビデンス(有効性の科学的根拠)の不足です。NK細胞療法は多くのクリニックで実施されているものの、現時点で大規模な統計データが十分ではありません。ただ、最近では国内外で臨床研究が進み、肺がんに対する免疫細胞療法のランダム化比較試験で生存期間延長の効果が示されたとの報告も出ています。今後さらなる研究に期待したいところです。
樹状細胞療法とは
樹状細胞療法では、患者さん自身の樹状細胞を利用します。
樹状細胞は免疫の“司令塔”でしたが、実はこの細胞を使った治療は「がんワクチン療法」とも呼ばれます。なぜワクチンなのかというと、樹状細胞はT細胞やB細球にがんの目印(抗原)を提示して攻撃命令を出す役割でした。そこで患者さんの体内のがん細胞の情報を樹状細胞に教え込んでから体に戻し、免疫にがん攻撃を仕掛けさせる――まさに体内でがんに対する免疫応答を誘導する「ワクチン」のように機能するわけです。
具体的な手順としては、まず患者さんの血液から単球という細胞を採取し、サイトカインなどを用いて培養し樹状細胞へと分化させます。
次に、その培養した樹状細胞にがんの抗原情報を与えてあげます。抗原情報の与え方はいくつかあり、患者さんのがん組織由来のタンパク質断片(ペプチド)を加える方法や、人工合成したがんペプチドを投与する方法、あるいは患者さん自身のがん細胞を破砕して抽出液を樹状細胞に取り込ませる方法などがあります。
その後、抗原を身につけた樹状細胞を体内に戻すと、樹状細胞はリンパ節で待機してT細胞などにがんの目印を提示し、免疫全体に号令をかけます。命令を受け取ったキラーT細胞など攻撃部隊は、がん細胞だけを選んで攻撃し始めます。
樹状細胞療法の特長は、ピンポイントでがんを狙い撃てる可能性がある点です。攻撃の主役は患者さん自身のキラーT細胞ですが、的確にがんの目印を共有してから攻撃するため、副作用を抑えて効果的にがんを攻撃できると考えられています。これまでの研究でも樹状細胞ワクチン療法は副作用が少なく安全に施行できることが報告されています。
さらに樹状細胞療法は患者さんそれぞれのがんに合わせてカスタマイズできる点も利点です。患者さんの持つがんの遺伝子や抗原を調べ、その人に適したペプチドを選んで樹状細胞にロードすることで、より効果が出やすいオーダーメイド治療が期待できます。
一方、樹状細胞療法にも克服すべき課題があります。
まず、やはりエビデンスの蓄積不足です。NK細胞療法以上に実施施設が限られていることもあり、大規模試験のデータはまだ少ないのが現状です。米国では前立腺がんに対する樹状細胞ワクチン療法(シプロセルT、商品名プロベンジ)が2010年にFDA承認されており、世界初のがんワクチンとして話題になりました。
もう一つの課題は効果の個人差です。樹状細胞ワクチンは患者さん自身の免疫力に大きく依存するため、もともと免疫が非常に低下した状態では効果が出にくいと考えられます。また、がん細胞側も狡猾で、免疫から隠れる仕組み(抗原を出さなくなる、免疫抑制物質を出す等)を持つ場合にはワクチンが効きづらくなります。
免疫細胞療法の課題
繰り返しになりますが、最大の課題はやはり科学的エビデンスの不足です。というのも、一部には劇的に効いた患者さんもいれば全く効果が見られなかった患者さんもおり、ばらつきが大きかったため評価が難しかったのです。加えて、多くの免疫細胞療法は製薬会社の新薬のような大規模臨床試験(ランダム化比較試験)を経て承認されたものではなく、症例報告や小規模試験レベルのデータしかないものも少なくありません。この点は医療関係者の中でも指摘されており、懐疑的な見方につながっています。
実際、一部の悪徳商法的クリニックが科学的根拠のない免疫療法を高額で提供して問題になった歴史もあり、日本では免疫療法全体の信用が落ちてしまった背景もありました。患者さんが安心して治療を受けられるよう、今後は信頼性の高いデータを蓄積していくことが重要です。幸い近年は大学病院との共同研究や学会でのデータ発表も増えてきており、有効性を示す論文も少しずつ報告されています。
次に費用の問題です。免疫細胞療法は保険適用外の自由診療であるため、全額自己負担となります。細胞培養には専用のクリーンルームや培地、技術料などコストがかかるため、治療費は高額になりがちです。実際に多くのクリニックで数十万円~数百万円単位の費用が必要とされ、CAR-T細胞療法は保険適用下でも1回3,000万円以上するケースもあります。また高額な治療費を払っても効果が確実ではないとなれば、精神的な負担も大きいでしょう。
さらに治療内容や質の施設間ばらつきも課題です。自由診療の免疫細胞療法は各施設ごとに独自のプロトコルで行われており、採取する細胞の種類、培養期間や活性化方法、投与する細胞数や回数などが統一されていません。極端に言えばクリニックAの「NK細胞療法」とクリニックBの「NK細胞療法」は中身が違う可能性もあるのです。患者さんにとってはどこで受けても同じ効果が得られるとは限らないという不安材料になりますし、データを集約して評価することも難しくなります。
また一部には不適切な衛生管理で細胞培養を行い、患者さんに感染症リスクを及ぼすようなケースも報告されています。実際、2024年には東京都内のクリニックでNK細胞療法を受けたがん患者さん2名が培養過程で細菌汚染された細胞を投与され重篤な感染症を起こした事例があり、厚生労働省が緊急命令で当該施設に提供停止を命じています。こうした事態は患者さんの安全を損なうだけでなく、免疫細胞療法全体の信用にも関わる重大な問題です。
今後の展望
まず研究動向としては、国内外で数多くの臨床試験や基礎研究が進められています。大学や研究機関と民間クリニックが協力してデータを集めたり、新しい手法の開発も活発です。例えばNK細胞をより長く体内で生存させる方法や、がんに集まりやすくする工夫、他人のNK細胞を使った“オフ・ザ・シェルフ”製剤の研究などが行われています。特に他人由来のNK細胞やiPS細胞から作った汎用NK細胞製剤は、一度に大量生産して保存もできるため低コスト化につながると期待されています。樹状細胞療法についても、より強力にT細胞を活性化できるよう樹状細胞自体を遺伝子改変する研究や、新しいがん抗原を見つけてワクチンに応用する研究など、日々進歩が報告されています。
また併用療法や個別化医療とのシナジーも期待されています。併用療法とは、免疫細胞療法を他の治療と組み合わせて相乗効果を狙うアプローチです。例えばNK細胞療法+抗がん剤、樹状細胞ワクチン+免疫チェックポイント阻害薬、といった組み合わせが研究されており、臨床試験でも少しずつデータが出始めています。個別化医療の面では、患者さんごとに免疫状態や腫瘍の特徴を解析し、その人に最も適した免疫細胞療法を選択する試みが始まっています。
最後に、安全性の更なる向上も重要な課題です。先ほど触れたような培養時の感染リスクを減らすため、培養工程の自動化や無菌管理技術の進歩も進んでいます。また、治療する医師の側にも正しい知識と技術が求められます。免疫細胞療法は再生医療等のカテゴリーに入り、提供する医療機関は法律に従った体制整備が義務付けられています。正しく安全に提供される治療であれば、免疫細胞療法は患者さんの希望になり得るでしょう。
まとめ
免疫細胞療法は私たち自身の「体内の守り手」である免疫を活用する新しい医療の形です。自然治癒力を引き出すアプローチとも言え、夢のある分野です。現時点では課題も多く、誰もが受けられる標準治療とは言えません。しかし世界的に研究が加速しており、少しずつ光が見えてきています。「自分の細胞で自分の病気を治す」というコンセプトは再生医療の大きな柱でもありますから、将来さらに洗練された形で私たちの医療選択肢に加わってくることでしょう。
今回は免疫細胞療法について詳しく解説しました。最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは、また次回お会いしましょう!