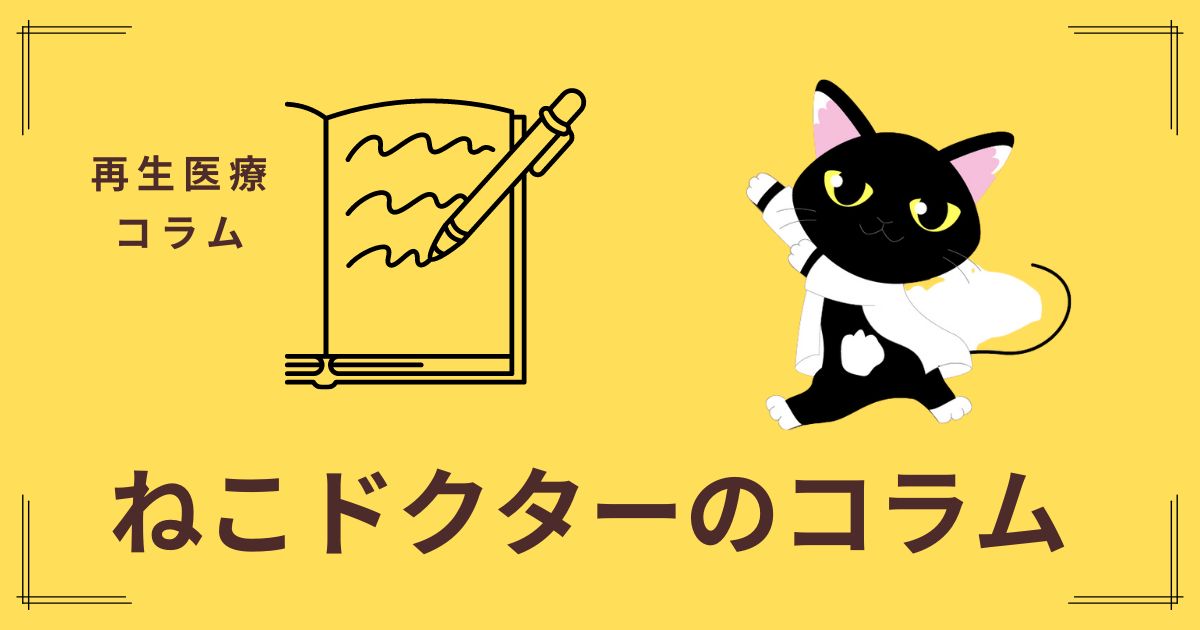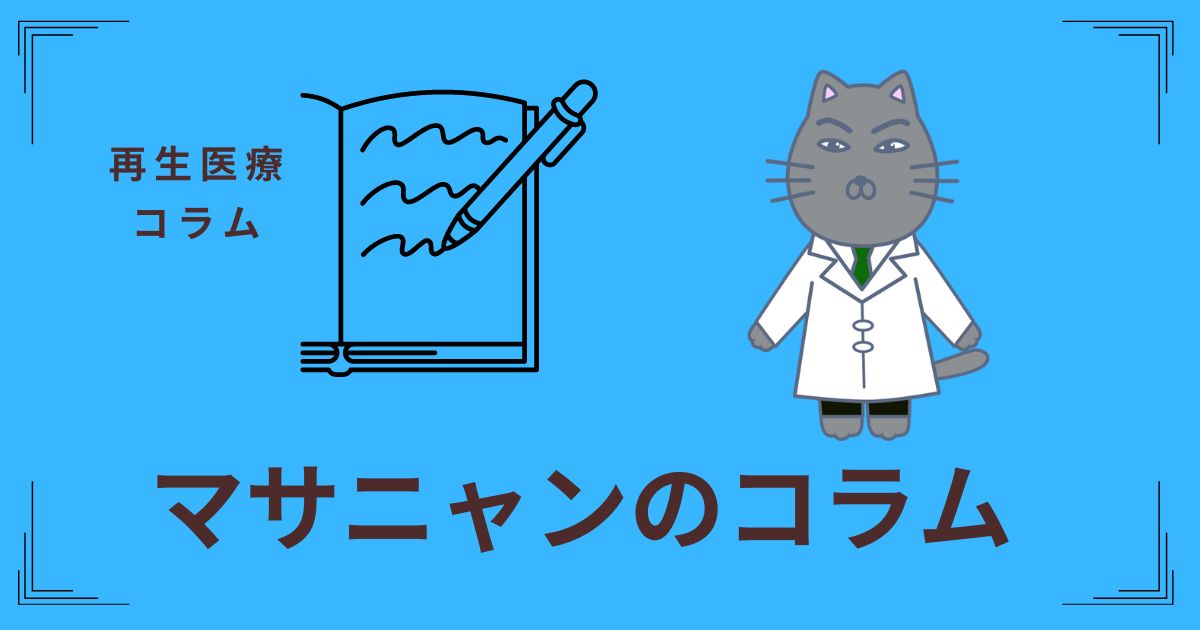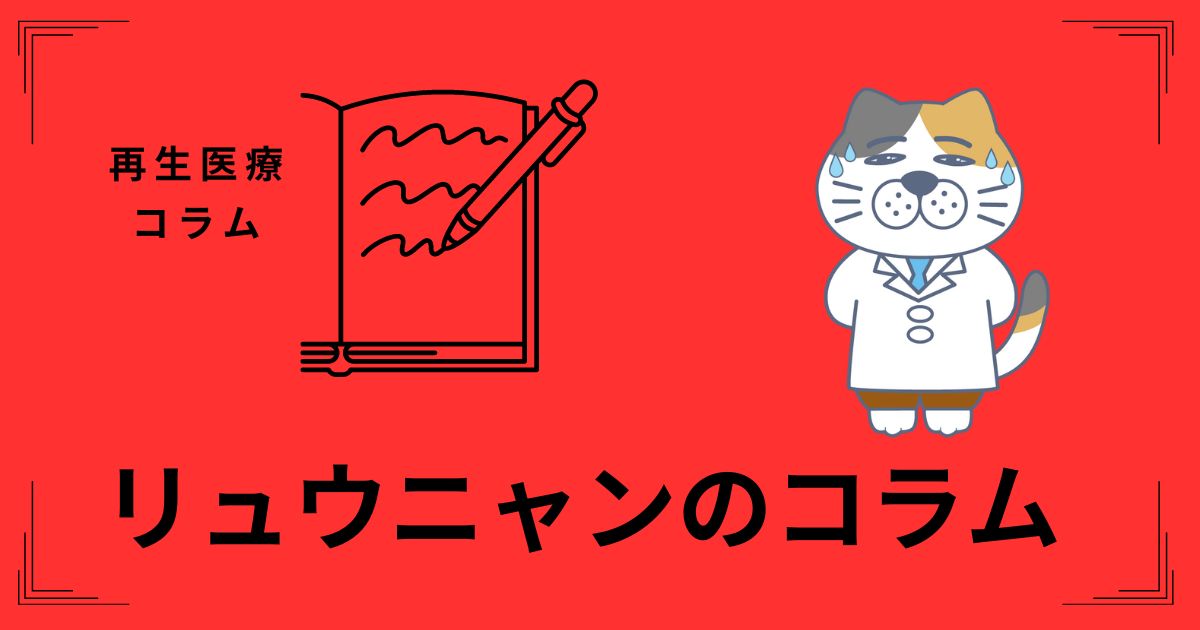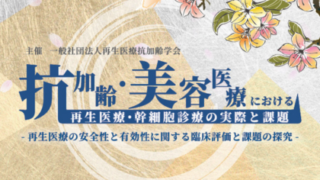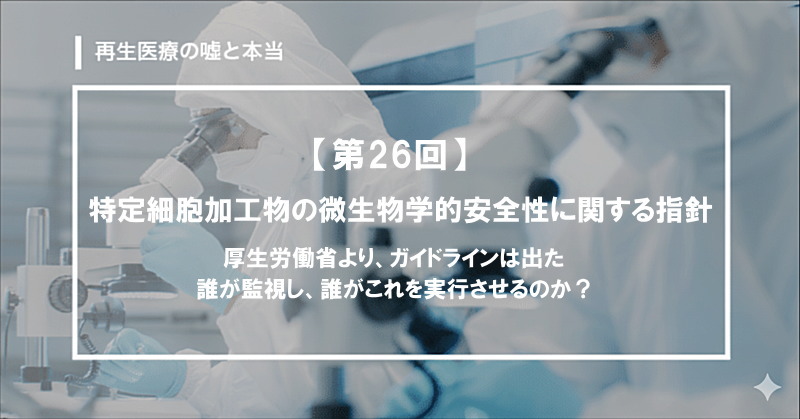
特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針
令和7年10月6日に「特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針」は、再生医療法の運用10年を経て初めての包括的な改訂案として厚生労働省の課長通知として公表されたが、その内容について…
厚労省通知を本当に意味のあるものにするために率直に言います。
今回の厚労省の課長通知は、現場を知らないアカデミアや研究者の視点で作られた無駄で悪手の規定が目立ちます。
実際に細胞を扱う現場の実情を理解せず、過度な菌検査や非現実的な手順が盛り込まれています。(その他、色々ありますが)
私たちの声が無視された背景
実を言うと、私はこの通知が出る前から厚労省に働きかけ、現場を知らないアカデミックな視点だけでなく、実務者の声を反映するように求めてきました。しかし、残念ながらその声は無視され(いつも)、アカデミアの視点だけで作られた形になってしまったわけです。
今後どう改善していくか
このままでは形骸化は避けられません。
だからこそ、この1年で厚労省の姿勢を変え、現場の声を反映させていくことが重要です。
アカデミアの視点だけでなく、現場で働くプロフェッショナルの意見を取り入れ、本当に意味のあるルールにブラッシュアップしていくことが求められています。
相談室としての視点:規制がなければ意味がない
厚生労働省が課長通知として示した「特定細胞加工物の微生物学的安全性指針」は、実際に法改正や実効化までにまだ約1年ほどかかると見られています。
▼ 私たち相談室の立場から見れば、現場の声はこうです。
| -「ガイドラインは出た、でも誰が監視し、誰がこれを実行させるのか?」- |
法律にならなければ、結局は「やったふり」が横行し、本当の安全性向上にはつながりません。{規制と監督の枠組みがなければ、いくら立派な指針も“絵に描いた餅”}になってしまうのです。
「書いて終わり」では意味がない
現場を知らないと、こうした指針が出れば「すぐに現場が変わる」と思いがちですが、実態はそう簡単ではありません。
法制化までには1年、2年とかかるでしょう。その間、「これを書いたからOK」という計画書が乱立し、審査側も形だけで終わる。誰が実際にこれを監督し、運用するのかが不透明なのです。
ただ批判するだけじゃなくて、この通知をより実用的なものに変えていくために関わっていきたいと思ってます。
1年後に形骸化したルールになるんじゃなくて、ちゃんと現場の実情を反映した安全基準に仕上げるために、今こそ声を上げていくタイミングだと・・いつも感じています。
次回は「特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針」この内容について簡単に説明したいと思います。