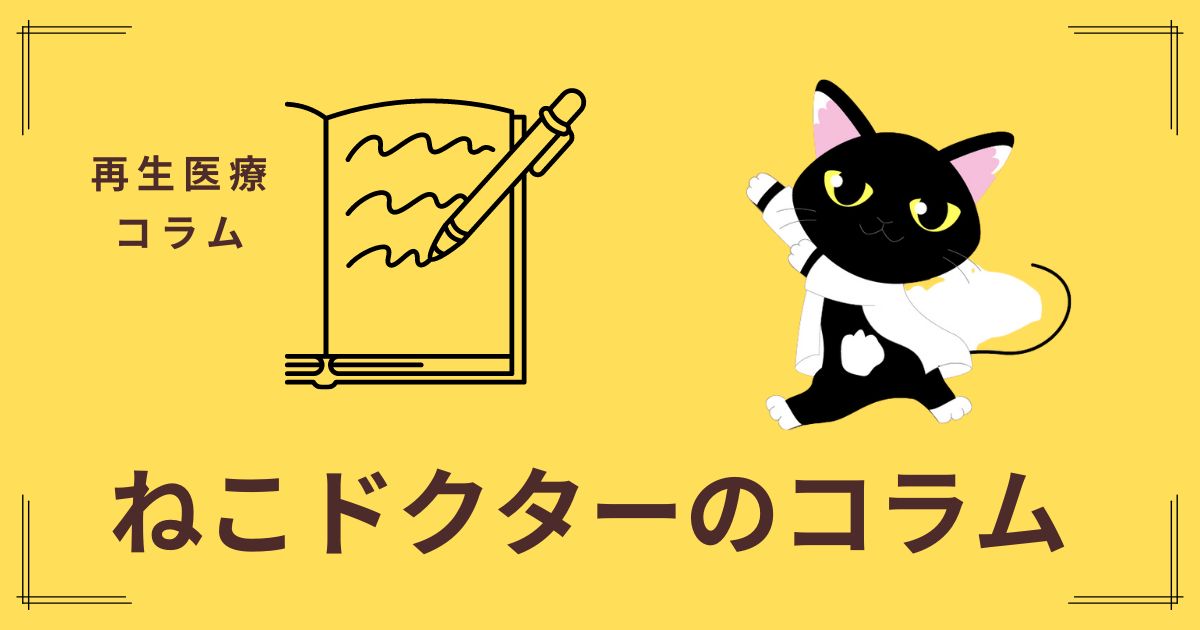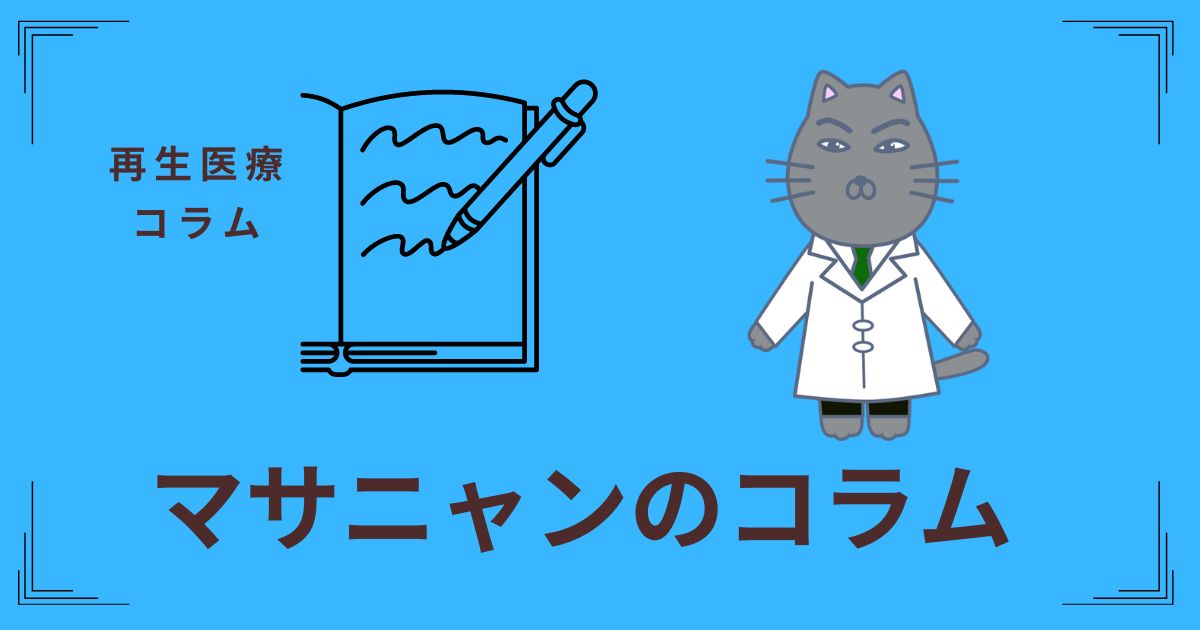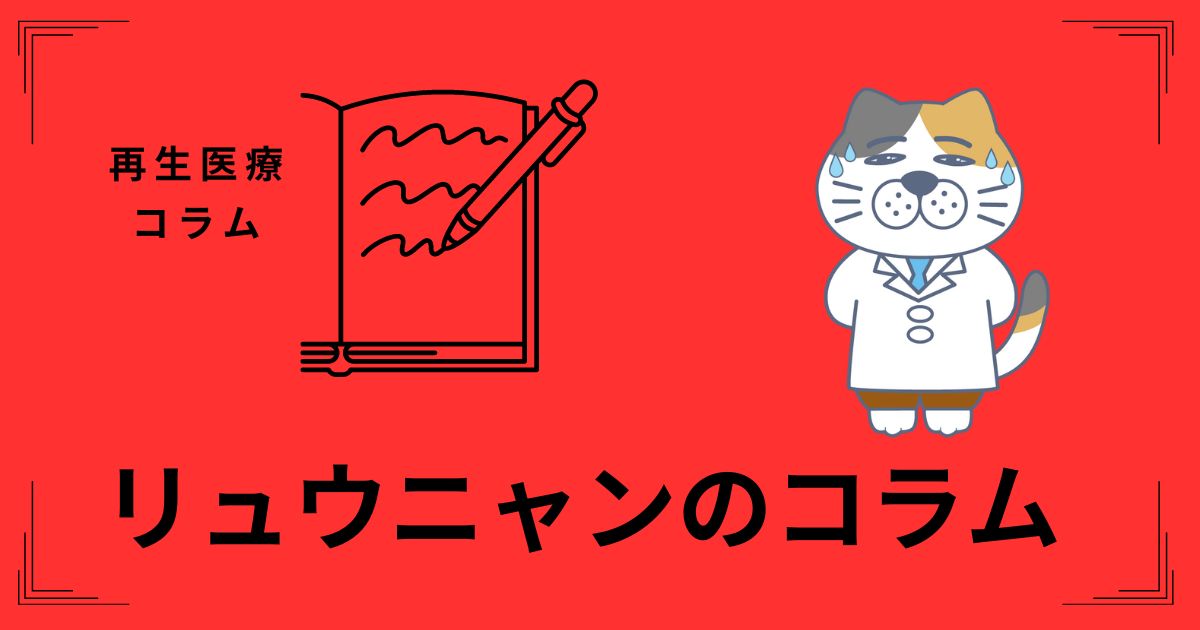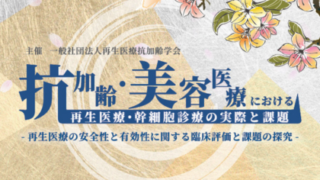2025年3月19日、日本経済新聞に
「安全検証不足の再生医療、学会が抑制へ。患者に情報提供」
という記事が掲載されました。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG17A0Y0X10C25A3000000/
記事によれば、「効果や安全性が十分に検証されていない再生医療が国内の医療機関で提供されているのは問題」として、日本再生医療学会が個々の治療計画を検証型か無検証型かに分類・判定し、患者が参照できる仕組みを検討するという内容です。
そしてこの発表の背景にあるのが、同日に日本再生医療学会から出された「YOKOHAMA宣言2025」です。
https://www.jsrm.jp/news/news-16112/
「なんとも眠たい」宣言
一言で言えば、これは「なんとも眠たい」宣言である。
もちろん、国内で提供されている再生医療を「検証型」か「無検証型」かに分けて、透明性を持って公開する取り組み自体を否定するものでは決してないが、それを言う前に、もっと先にやるべきことがあるのではないかと感じました。
それは、まさに宣言内でも触れられている「エクソソームを含む細胞外小胞等(Extracellular Vesicles: EVs)」の扱いです。
再生医療ではないにもかかわらず、「あたかも再生医療」かのように広告・宣伝され、今まさにこの瞬間にも、全国のクリニックで自由診療として薬事未承認の培養上清液やエクソソームなどが患者へ投与されています。
すでに健康被害も出ており、また今後いつ起きてもおかしくないという状況にある中で、あえて「YOKOHAMA宣言2025」の中から引用させてもらえば
再生医療を標榜する唯一の日本医学会分科会として「あらゆる知を結集し、再生医療の革新と普遍化により、全人類の幸福と未来に貢献する」ことをミッションとし、再生医療等技術、特に iPS 細胞の臨床応用は日本が国際的に卓越したリーダーシップを発揮してきた
と自負する日本再生医療学会が、このような悠長な宣言を出すことで果たして本当に患者の安全を守ることが出来るのだろうか。
エクソソームを含む細胞外小胞等について
本当に患者を守るための【安全性】を謳うのであれば、せめて学会として、少なくとも以下のことは即時に実施すべきではないでしょうか。
-
未承認薬(上清液・エクソソーム)の点滴投与の禁止
-
その安全性を担保する成分基準・使用基準の策定
というのも、学会はすでに2024年4月30日付で「細胞外小胞等の臨床応用に関するガイダンス」を出しており、そこでは以下のように述べられています:
https://www.jsrm.jp/news/news-14993/
一般に、EV調製物のリスクは薬機法の下で開発されるバイオ医薬品と大きく変わるところはない。
EV調製物の品質・有効性・安全性確保のためには、再生医療等安全性確保法下の再生医療等提供基準及び医薬品医療機器等法(薬機法)下の再生医療等製品(細胞加工製品)の品質管理・製造管理基準に準じた品質管理・調製管理(製造管理)を実施するべきである。
つまり、学会自らが上清液・エクソソームの治療や製造方法に対してのリスクを十分に理解した上で、「薬機法」や「再生医療安全性確保法」と同レベルのリスクに対する規制管理が必要であるというガイダンスを発表しているにもかかわらず、今回のYOKOHAMA宣言では明確な抑止策が打ち出されていないのです。
海外との比較:エクソソーム規制の国際的枠組みについて
すでに欧米諸国では、幹細胞培養上清液やエクソソーム(細胞外小胞)に関する規制がエクソソームの内容物が生理機能に与える影響に基づき、厳格に定められており、製品の安全性と有効性を確保するための枠組みが整備されている。
アメリカ(FDA)
アメリカでは、エクソソーム製品はFDA(米国食品医薬品局)のCBER(生物製剤評価研究センター)によって管轄されています。具体的には「Public Health Service(PHS)法 第351条」や「Federal Food, Drug, and Cosmetic Act(FD&C法)」に基づき、治療効果を謳う製品は「医薬品」および「生物製剤」として規制され、事前審査・承認が必要となります。
実際に2019年以降、FDAは複数の安全性警告を発出し、2023年10月時点で少なくとも6件の警告書を出しています。現在、エクソソームを用いた製品は、薬事承認(BLA:生物製剤ライセンス申請)を受けない限り商業的に提供することは認められていません。
ヨーロッパ(EMA)
EUでは、「Directive 2001/83/EC」および「Regulation 1394/2007/EC」により規制され、エクソソームが翻訳されたRNAや調整タンパク質などを含み、患者に治療効果が期待される場合には「先進治療医薬品(ATMP)」として扱われます。
これらはEMA(欧州医薬品庁)のCAT(先進療法委員会)による評価を受け、遺伝子治療、体細胞治療、組織工学製品として分類されます。特に再構成された核酸を含む場合は、遺伝子治療製品として取り扱われ、治験プロトコルおよび製造・品質管理体制が厳しく審査されます。
このガイドラインは、人由来細胞から分離・精製されたエクソソームを医薬品として評価する基準を提供しており、現時点では医薬品として承認された製品はありません。
国や学会の対応が遅すぎる
こうした国際的な動きに比べ、日本の制度対応はどうしてここまで遅れているのでしょうか?
改めて言いますが、YOKOHAMA宣言を完全に否定する意図はありません。
しかしながら、すでに死亡事故まで発生している幹細胞培養上清液の点滴治療に対し、2023年10月に再生医療抗加齢学会が発表した声明を受けてようやく今回の宣言が出された、という「後追い感」は否めません。
https://aarm.jp/news/幹細胞培養上清液に関する死亡事例の発生について/
穿った見方をすれば、「世論の流れを見て表面上警鐘は鳴らしているが、上清液・エクソソーム治療を推奨し、法の規制外であることをいいことに、ここぞとばかりにビジネス展開している学会員に対しての遠慮や配慮があるのでは?」と勘ぐりたくなるのも仕方ありません。
本当に評価できるか
宣言には以下のような一文があります:
患者・市民との対話を重ね、薬事承認(薬機法に基づいた製造販売承認)に基づく治療、ならびに安 確法下で自由診療として提供される薬事未承認の医療技術のうち安全性および有効性の「検証」Aを 伴う「検証型診療」Bおよびそれらの検証を伴わない「無検証診療」Cについての正確な理解が醸成 される
ですが——
-
どの立場の誰が?
-
どのような基準で?
-
何らかの意思によって「無検証診療」と判断された診療が“抑制対象”となり、不利益を被る患者への対応は?
といった基本的な疑問への答えが、明確には示されていません。
「YOKOHAMA宣言」の項目1〜8には以下のように記載されています:
患者・市民との対話を重ね、積極的な社会との対話、臨床に携わる会員との意見交換を行う
患者が治療選択にあたり参照可能な情報を広く公開する
日本で実施されている再生医療の現況を分析し、明らかになった課題を解決するとともに、その成果を国際社会に発信する
最新の知見から得られた洞察を規制に昇華するための調査および政策提言を行う
標準プロトコルを開発する
再生医療の在り方を検討する
一体いつに成されるのだろうか。
その脆弱性と法整備の遅れを改めて感じさせる記事と「宣言」である。
そして最後に問いたい。
日本の厚生労働省はこの法整備の遅れに対しどう考えているのか?
はなはだ疑問である。