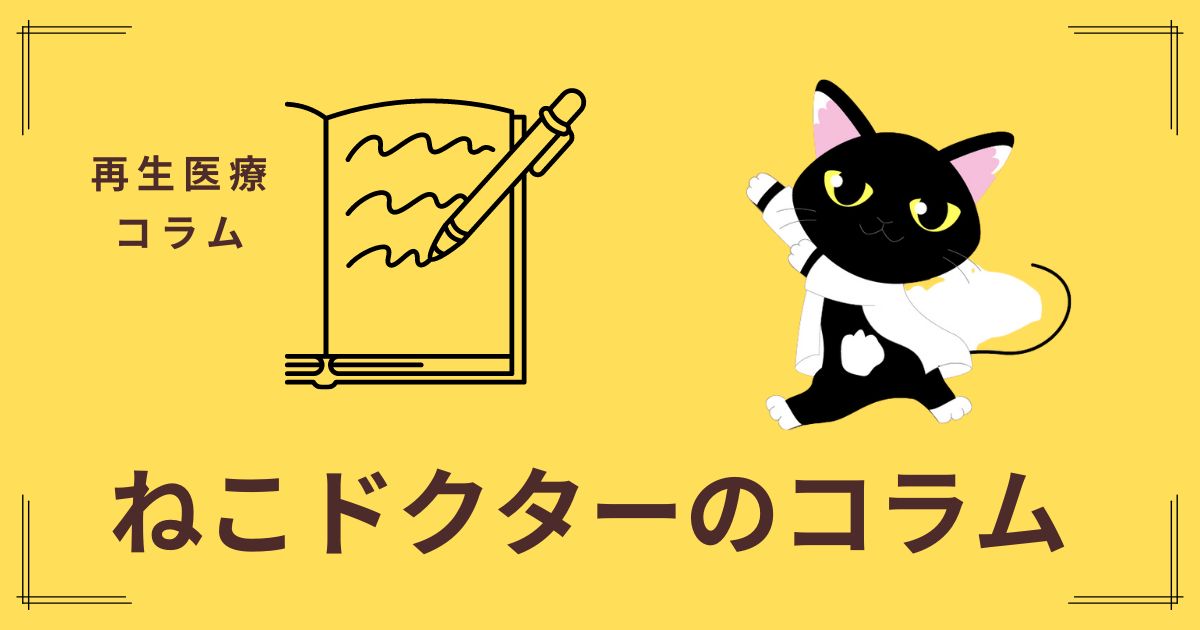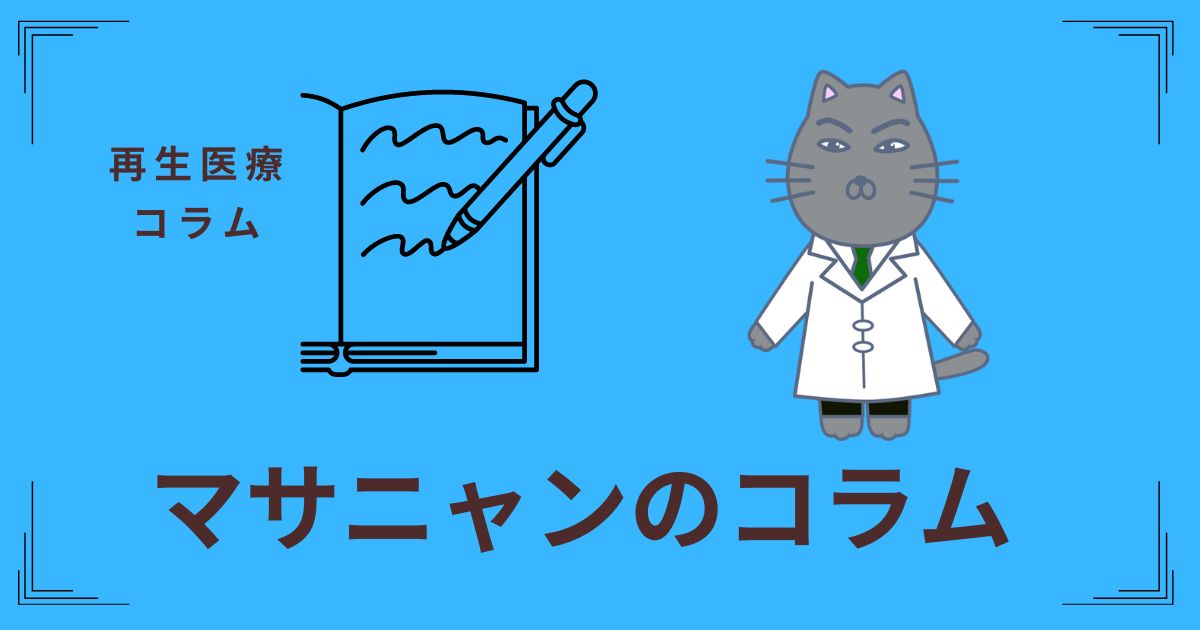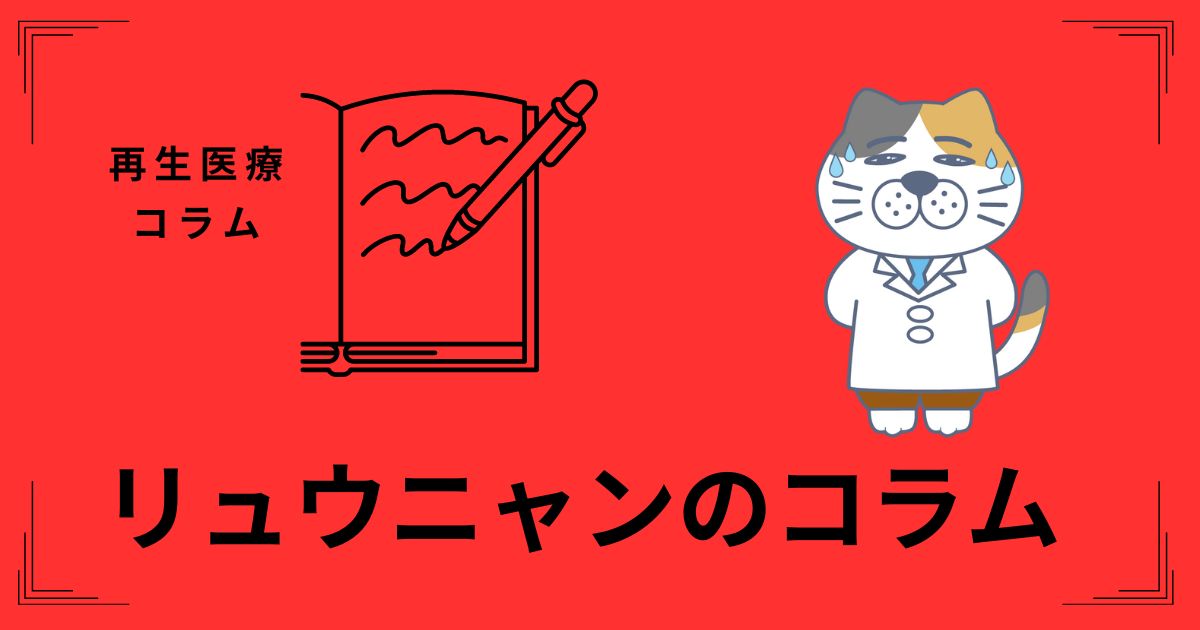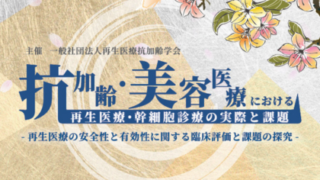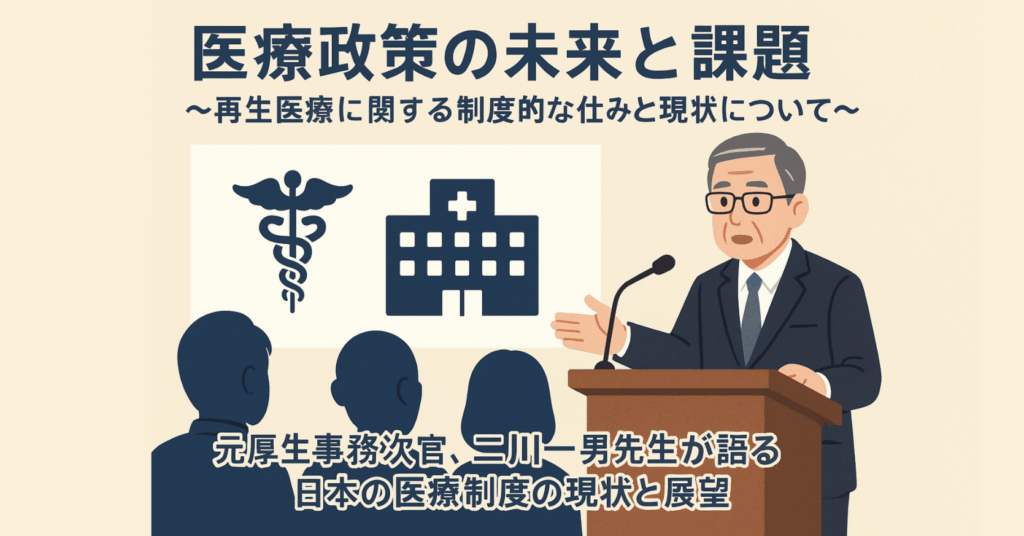
元厚生事務次官、二川一男先生が語る 日本の医療制度の現状と展望
こんにちは、マサニャンです!
第11回では、医療政策の未来と課題について取り上げます。
先日、「第2回再生医療抗加齢学会学術総会」の理事長特別企画として、元厚生労働事務次官の二川一男先生による講演会が開催されました。テーマは「医療政策の未来と課題」。日本の医療制度の現状と今後の変化について非常に興味深いお話を伺うことができました。
講演会の概要
講演会では、まず二川先生の自己紹介と、これまでの厚生労働省での職務経験が語られました。特に、年金制度に長く携わってきた経験から、社会保障全体に関する深い知見を持っていることが強調されました。講演は、人口動態の変化が社会保障制度に与える影響から始まり、年金制度、医療・介護制度の現状と課題、そして今後の医療政策の方向性へと展開されました。
日本の人口動態と社会保障制度
講演の冒頭で、日本の人口動態、特に高齢者人口の推移が示されました。
-
高齢化の現状:
2015年時点での65歳以上人口は約3300万人であり、その後も増加傾向にありますが、増加のペースは鈍化しています。しかし、75歳以上の人口は増加を続けており、医療や介護のニーズは今後さらに高まると考えられます。
- 年金制度への影響:
高齢者人口の増加は、年金制度の財政的な持続可能性に影響を与えます。講演では、マクロ経済スライドという仕組みが導入されており、これにより年金の給付水準が調整され、制度の安定性が保たれていることが説明されました。ただし、物価の上昇に対して年金の伸びが追い付かず、実質的な年金受給額が目減りしているという課題も指摘されました。
-
医療・介護制度への影響:
高齢化は医療・介護の需要を増大させ、医療費の増加につながります。講演では、2025年をピークに75歳以上の人口増加は緩やかになるものの、高齢者人口そのものは依然として高い水準で推移することが示されました。これにより、医療・介護制度の維持が重要な課題となることが強調されました。
年金制度の現状と課題
講演では、年金制度の仕組みと現状について、より詳細な説明がありました。
-
年金制度の仕組み:
厚生年金の保険料率は18.3%で固定されており、労使で折半して負担します。保険料収入の範囲内で年金を給付する仕組みとなっており、財政の安定性が図られています。
-
年金受給額:
平均的な給与(40歳前後で約35万円)の場合、毎月の保険料は6万円、年間で80万円近くになります。この保険料を30~40年間払い続けることで、老後の年金給付を受けることができます。
-
年金の将来:
年金制度は持続可能であるものの、将来的に年金受給額が減少する可能性も指摘されました。老後資金の不足に備え、自助努力の必要性が強調されました。具体的には、年金の繰り下げ受給や、確定拠出年金(iDeCo)などの制度を活用することが提案されました。
医療費と財政的課題
続いて、社会保障費の増加による財政的な課題について説明がありました。ジェネリック医薬品の普及による医療費の抑制効果や、診療報酬の限界についても詳しく解説され、今後の医療制度の持続可能性を考える上でのヒントが示されました。また、混合診療の検討や、創薬におけるアカデミアとベンチャー企業の連携の重要性も指摘され、医療分野のイノベーションが求められることが強調されました。
-
医療費の増加:
高齢化に伴い、医療費は増加し続けています。2040年には、医療・介護にかかる費用が2018年時点と比較して3割増加するとの推計が示されました。
-
制度の持続可能性:
このままでは、医療制度が財政的に立ち行かなくなる恐れがあります。消費税や保険料の値上げも選択肢となりますが、国民の理解を得ることは容易ではありません。
-
医療提供体制:
医療現場では、医師や看護師などの人材不足が深刻化しています。また、医療機関の経営も厳しくなっており、効率化や生産性の向上が求められています。
再生医療と美容医療の役割
再生医療に関しては、安全性確保法や薬機法の下での法規制について詳述されました。特に、美容医療のニーズが高まる中で、その社会的役割が再評価されていることが強調されました。美容医療は単なる美の追求ではなく、健康的で質の高い人生を求める上での重要な要素であるとし、その発展の意義を再確認しました。
質疑応答と今後の展望
講演後の質疑応答では、再生医療のエビデンス構築の重要性が議論され、医療ツーリズムと国内医療提供の分離についても意見交換が行われました。特に、海外からの患者を受け入れる際の倫理的・実務的な課題についても議論され、医療政策が直面する複雑な問題が浮き彫りになりました。
医療政策の今後の方向性
講演の最後に、今後の医療政策の方向性について、具体的な提案がなされました。
-
テクノロジーの活用:
AIやICTなどのテクノロジーを積極的に導入し、医療現場の効率化や省力化を図る。
-
データヘルスの推進:
医療情報をビッグデータとして活用し、より効果的な医療の提供や疾病予防に役立てる。
-
医療機関の連携:
地域包括ケアシステムの構築を通じて、医療機関の連携を強化し、患者中心の医療を実現する。
-
混合診療の検討:
保険診療と自由診療を組み合わせる「混合診療」をより積極的に検討することも提案されました。
まとめ
二川先生の講演は、日本の医療制度が直面する課題を多角的に分析し、その解決に向けた具体的な道筋を示すものでした。高齢化が進む中で、医療制度を持続可能なものとするためには、社会全体での意識改革と、大胆な政策転換が求められています。