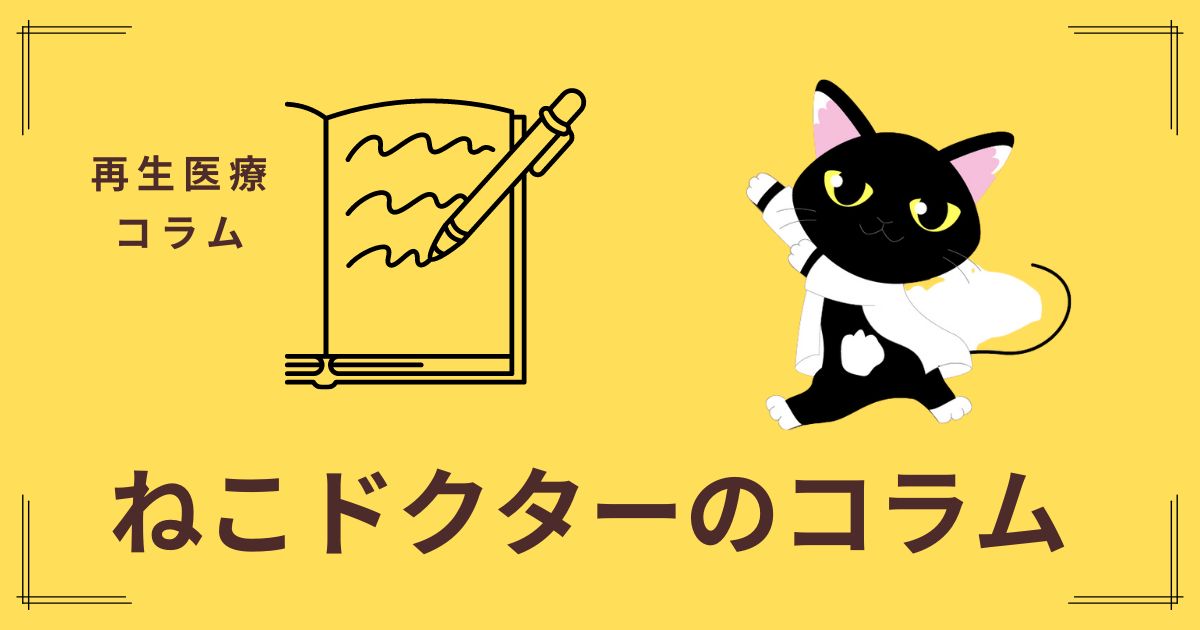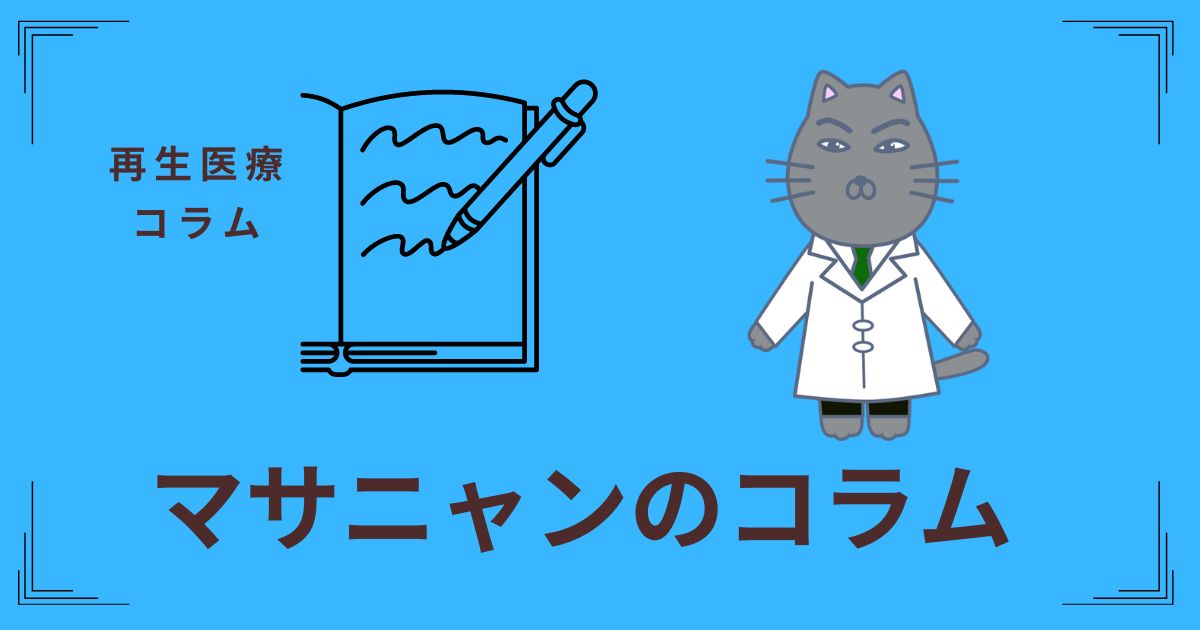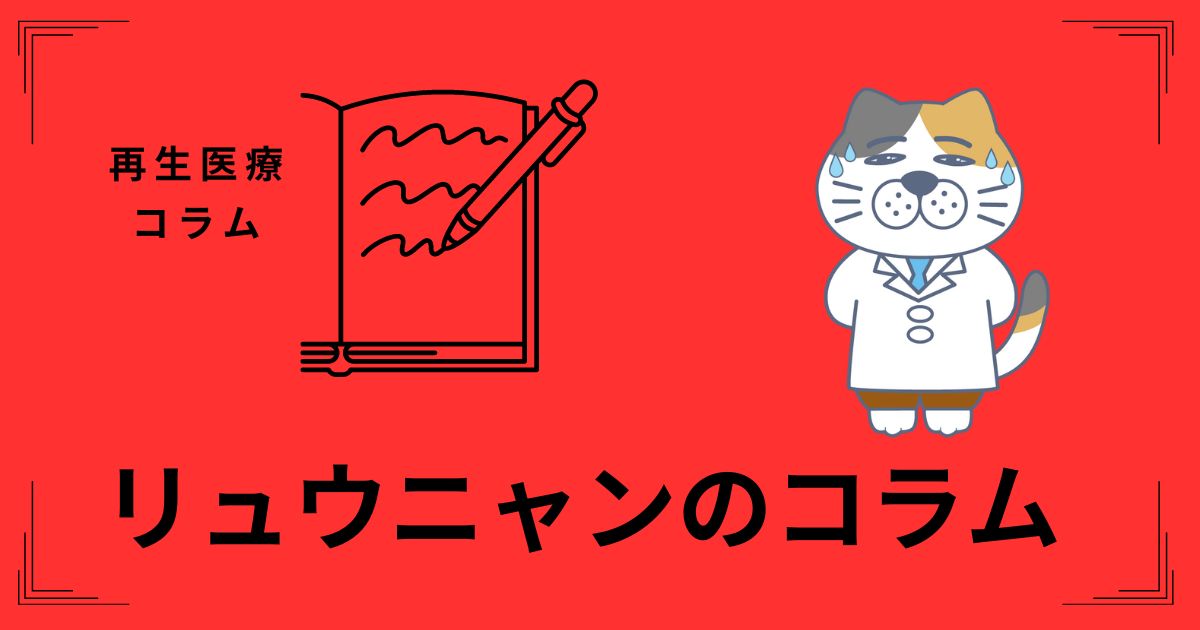こんにちは、リュウニャンです。
幹細胞シリーズも第8回となりました。
前回までの復習として、幹細胞とは自己複製と分化能力を持つ細胞でした。
ではその幹細胞から生まれる「前駆細胞」とは一体どのような細胞なのでしょうか?幹細胞との違いや、生体内での役割、さらには再生医療への応用まで解説していきます。
それでは始めましょう。
前駆細胞の概念と定義
前駆細胞とは、幹細胞から分化して生じ、最終的な成熟細胞へと分化できる細胞のことです。
幹細胞がいきなり心臓や脳などの完成された細胞になるのではなく、一度この前駆細胞を経由してから最終形態に至るという段階を踏んでいます。
前駆細胞には現時点で厳密な統一された定義があるわけではありませんが、一般的には以下のような特徴を押さえておくと理解しやすいでしょう:
-
分化能:前駆細胞は特定の方向へのみ分化でき、その分化の方向性(運命)はあらかじめ決まっています。幹細胞のように「あらゆる細胞」に化けることはできません。例えば血液の前駆細胞は血液細胞にしか、神経の前駆細胞は神経系の細胞にしか分化できません。
-
自己複製能力:前駆細胞もある程度の増殖能力を持ちますが、幹細胞ほど無限に自己複製できるわけではありません。分裂回数や増殖能力に制限がかかっており、いずれは分化の道を辿ります。
このように前駆細胞は「未分化だけれど分化の方向性は決まっている細胞」とまとめることができます。
実際、幹細胞はまず前駆細胞に分化し、前駆細胞がさらに目的の細胞に分化するという段階的プロセスが一般的です。
発現と命名の背景
「前駆細胞」という名称の背景には、生物の発生や組織再生における段階的な細胞分化の理解があります。発生学や細胞生物学の研究が進む中で、幹細胞から最終的な機能細胞が生み出される際に、いくつかの中間段階の細胞が存在することが明らかになりました。その中間段階の細胞が、最終産物の“前触れ”となることから「前駆(=先駆け・前触れ)細胞」と呼ばれるようになったのです。英語ではしばしば「Progenitor Cell」と呼ばれ、日本語の「前駆細胞」はその訳語に当たり、「最終分化細胞の前段階の細胞」を指しています。
例えば神経発生の分野では、神経管ができる胚の段階で未分化な神経幹細胞/前駆細胞が増殖し、そこからニューロン(神経細胞)やグリア細胞が次々と生み出されることが知られています。
このように、発生段階において幹細胞が分裂を重ねる中で一時的に存在する「過渡期の細胞」が前駆細胞という概念の源流です。
なお歴史的には、特定の組織に限って分化できる幹細胞を指す際に「前駆細胞」と呼ぶケースもありました。例えば成人の骨髄にいる造血幹細胞は血液系にしか分化しないため、「造血前駆細胞」と呼ばれることもあります。
このように幹細胞と前駆細胞の境界は必ずしも厳密ではなく、研究者によって使い分けが異なる場合がある点には注意が必要です。
幹細胞との区別
では改めて、前駆細胞と幹細胞の違いを整理してみましょう。
-
分化の範囲(多分化能の違い)
幹細胞には様々な種類がありますが、大きく分けて多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞など)と、体性幹細胞(組織幹細胞)があります。多能性幹細胞は体中のあらゆる細胞に分化可能であり、体性幹細胞も特定の組織内で複数種類の細胞に分化できます。
一方、前駆細胞は分化先が既に特定の系統に絞られているのが通常です。分化の“幅”という点で、幹細胞は広範囲であるのに対し、前駆細胞は限られた運命のみを持つと言えます。
-
自己複製能(増殖能力の違い)
幹細胞は自分と同じ能力を持つ細胞を自己複製により無期限に作り出せるのが大きな特徴です。
一方、前駆細胞は自己複製能力が制限的で、分裂を重ねるごとに分化へと傾いていきます。
つまり、幹細胞は“ずっと幹細胞で居続ける”こともできますが、前駆細胞は“いずれ成熟細胞になってしまう運命”なのです。
ただし、一部の体性幹細胞の中には分化先が一系統に限定されるものもあり、その場合は「ほとんど前駆細胞に近い幹細胞」と捉えることもできます。このように厳密な線引きは難しい面もありますが、基本的な違いを押さえておけば大丈夫です。
前駆細胞の種類
前駆細胞は体内のさまざまな組織・臓器に存在し、それぞれ対応する成熟細胞への分化能力を持っています。ここでは代表的な種類を紹介しつつ、特に研究や応用で注目される神経前駆細胞と骨芽前駆細胞に焦点を当てます。他にも多くの前駆細胞がありますので、合わせて見ていきましょう。
神経前駆細胞(Neural Progenitor Cell)
神経前駆細胞とは、中枢神経系に存在する未分化な細胞で、ニューロンやグリア細胞に分化できる細胞です。
発生段階では神経幹細胞とほぼ同義に扱われ、胎児の脳では神経管の内側(脳室帯)に存在する放射状グリア様の細胞が未分化型の神経前駆細胞(神経幹細胞)として増殖します。そこから分裂して生じた中間型前駆細胞が更に増殖し、最終的にニューロンへと分化することで、大脳皮質の層構造などが形成されます。
成人の脳でも、ごく限られた部位に神経前駆細胞/神経幹細胞が残存しています。代表的なのは脳室周囲と海馬と呼ばれる部位で、ここでは新しいニューロンを生み出す現象(神経新生)が起きていることが知られています。
神経前駆細胞は再生医療や創薬の文脈でも非常に注目されています。神経系の損傷や変性疾患に対して、新しい神経細胞を補充する手段としてこの細胞が期待されているからです。後述するように、近年はiPS細胞から神経前駆細胞を作り出し、脳や脊髄の疾患治療に応用する試みが進んでいます。また、神経前駆細胞を培養することで脳の発達モデルを構築したり、薬の効果や毒性を調べる創薬スクリーニングにも役立てられています。
骨芽前駆細胞(Osteoprogenitor Cell)
骨芽前駆細胞とは、骨を形成する骨芽細胞に分化できる前駆細胞です。また状況によっては軟骨を形成する軟骨芽細胞にも分化可能な細胞も含まれます。
骨芽前駆細胞は主に骨膜と呼ばれる骨の表面を覆う膜組織に多く含まれており、骨折の際などに新しい骨を作る源となります。骨膜には血管や神経も通っており、そこに存在する前駆細胞が傷害時に活性化して骨の修復や再生を担います。
また骨髄の間質にも骨や軟骨に分化しうる細胞が存在します。これらは骨髄間質幹細胞とも呼ばれ、骨芽前駆細胞の一種と考えられます。
実際、患者さん自身の骨髄を採取してそこから間葉系幹細胞を取り出し、培養増殖させてから患部に戻すといった再生医療も行われています。
上記以外にも、人体には各種の前駆細胞が存在します。
-
造血系の前駆細胞:骨髄中のリンパ芽球細胞は、血液細胞のうちリンパ球系列(B細胞やT細胞)の前駆細胞にあたります。また造血幹細胞から分化して赤血球や白血球の各系列に分かれていく細胞も、それぞれ前駆細胞(前赤芽球、前骨髄球など)と呼ばれます。これらは血液細胞を効率よく生み出すため骨髄内で増殖・成熟し、必要に応じて血中に供給されています。
-
筋肉の前駆細胞:骨格筋には筋衛星細胞と呼ばれる筋繊維の表面に付着した細胞があり、これは筋細胞への分化能力をもつ前駆細胞です。筋肉が損傷した際に衛星細胞が活性化して新しい筋繊維を形成し、傷を修復します。トレーニングで筋肥大が起きる背景にも、衛星細胞の分裂・融合による筋繊維の増強が関与しています。
-
血管の前駆細胞:血液中には血管内皮前駆細胞と呼ばれる細胞が存在し、全身を巡回しています。これらは必要に応じて血管の内皮細胞などに分化し、損傷した血管の修復や新生血管の形成(血管新生)を助けます。怪我をしたときに傷口で血管が再生するのも、こうした前駆細胞の働きによる部分が大きいと考えられています。
-
皮膚の前駆細胞:皮膚表皮の一番下の層(基底層)には、基底細胞と呼ばれる細胞があります。これは表皮細胞をどんどん分裂で生み出す前駆細胞です。皮膚のターンオーバー(新陳代謝)は、これら基底層の細胞が新しい角化細胞を供給することで維持されています。
前駆細胞の生理的意義
前駆細胞は上記のように全身の組織に散在していますが、その存在場所ごとに重要な生理的役割を果たしています。キーワードは迅速な細胞補充と組織恒常性の維持です。
私たちの身体では、日々細胞が新陳代謝で入れ替わり、また怪我や病気で一部の細胞が損傷を受けることがあります。こうしたとき、いきなり幹細胞から新しい細胞を作り出すのでは時間がかかりすぎる場合があります。そこであらかじめ前駆細胞という“予備軍”を用意しておくことで、迅速に必要な細胞を補充する仕組みが備わっているのです。
さらに、場所によっては前駆細胞が体内を巡回しています。前述の血管内皮前駆細胞などは血流に乗って全身を回っており、怪我や虚血が生じるとすぐさまその局所に留まって血管内皮細胞へ分化し、修復を行うことが確認されています。このように、あたかも巡回員のようにパトロールしている前駆細胞も存在するのです。
前駆細胞は組織の恒常性の維持にも大きく寄与します。皮膚・血液・腸管上皮など、盛んに生まれ変わる組織では、それぞれの前駆細胞が安定した供給源として働き、常に一定数の成熟細胞を保っています。
仮に前駆細胞が枯渇してしまうと、組織の再生能力が低下し、老化や機能不全につながります。実際、年齢を重ねると前駆細胞の機能も衰えてきて、傷が治りにくくなったり血液細胞の産生力が落ちたりします。これは前駆細胞(およびその供給源である幹細胞)の老化現象の一端と考えられています。
臨床応用例や治療原理
前駆細胞を用いた再生医療や治療法の研究は、世界中で数多く進められています。ここでは、その中から神経再生と骨再生の代表的な例を紹介し、前駆細胞がどのように臨床応用されているかを見てみます。
神経再生
一つの例がパーキンソン病に対する細胞移植療法です。パーキンソン病では脳内のドーパミン産生ニューロンが減少するため、これを補う目的でiPS細胞由来のドーパミン神経前駆細胞を患者の脳に移植する臨床研究が日本で行われています。厚生労働省の発表によれば、他家由来のiPS細胞から作製したドーパミン神経前駆細胞を移植することで、パーキンソン病の症状改善を目指す研究が2017年に計画承認されました。
この研究では京都大学や企業(ヘリオス社など)が連携し、患者脳内の線条体という部位に前駆細胞を注入して、その後ドーパミン神経へと成熟・機能することを確認しています。世界的にも、このパーキンソン病に対する神経前駆細胞移植は再生医療の最先端として注目されています。
もう一つの神経再生の例は、脊髄損傷に対する治療です。日本では慶應義塾大学のグループが中心となり、事故などで脊髄を損傷した患者に対しiPS細胞由来の神経前駆細胞を移植する臨床研究を行っています。対象は脊髄損傷から2〜4週間程度の亜急性期の患者で、損傷部位に前駆細胞を注射し、運動機能の回復や感覚の改善を図るというものです。2019年に初回の移植が実施され、現在も経過観察と臨床試験が続けられています。
神経前駆細胞は損傷した脊髄でニューロンやオリゴデンドロサイト(髄鞘を作る細胞)に分化し、神経回路の再生や軸索の髄鞘化を促すことで機能回復に寄与すると期待されています。これら神経再生医療の原理は、不足している神経細胞を前駆細胞から補充し、なおかつ前駆細胞が分泌する成長因子等で自己修復を促すというものです。
骨再生
骨芽前駆細胞や間葉系前駆細胞は、整形外科や歯科領域で応用が進んでいます。
一例として難治性の骨折や骨欠損への治療が挙げられます。通常の骨折はギプス固定などで自然治癒しますが、大きな骨欠損を伴うケースでは治癒が難しいことがあります。そうしたケースに対し、患者自身の骨髄から採取した間葉系前駆細胞を培養して数億個まで増やし、多血小板血漿(PRP)や人工骨マトリックスと混合して患部に移植する治療法が試みられています。前駆細胞が骨芽細胞へと分化して新生骨を形成し、かつ分泌するサイトカインが骨形成を促すことで、難治性の骨折を治そうというアプローチです。現在これは研究段階ですが、一部の患者では骨癒合が促進したとの報告もあります。
歯科領域でも歯周組織再生に前駆細胞が使われています。脂肪組織由来多系統前駆細胞(ADMPC)を活用した臨床研究では、重度の歯周病で歯を支える歯槽骨が失われた患者に対し、自身の腹部脂肪から採取・培養したADMPCを移植しています。具体的には、ADMPCを人工骨と混ぜ、歯周外科手術の際に骨欠損部に充填します。その結果、歯槽骨の再生や歯の動揺改善といった効果が報告されており、前駆細胞が組織修復を助ける一例といえます。この治療は厚生労働省により先進医療として承認を受け、現在も大阪大学歯学部附属病院などで臨床研究が進められています。
これらの他にも、心筋梗塞後の心臓再生に骨髄由来の前駆細胞を用いたり、末梢血管疾患に対して血管新生を促す前駆細胞を注射したりする試みが世界中でなされています。
このように、前駆細胞は様々な臓器の再生に応用可能であり、「細胞のお薬」として今後さらに活躍の場が広がると考えられています。
iPS細胞からの分化誘導
iPS細胞(人工多能性幹細胞)は体のあらゆる細胞に分化できる能力を持つため、これを出発材料にして様々な前駆細胞を作り出すことが可能です。幹細胞シリーズの第4回で解説したように、iPS細胞自体をそのまま移植するとテラトーマ(奇形腫)を形成してしまうリスクがあるため、実際の医療応用では目的の細胞にしっかり分化させ、未分化な細胞を除去してから移植する必要があります。そこで、「幹細胞 → 前駆細胞 → 最終分化細胞」という分化の階段を人工的に再現し、iPS細胞から安全かつ有用な前駆細胞を誘導する技術が発展してきました。
近年iPS細胞由来の前駆細胞を得る技術は着実に進歩しています。特に「必要な前駆細胞を目的の分化段階で止めておく」ことが重要で、そのため培養添加物の工夫や細胞を未成熟な状態でキープする手法が研究されています。
前駆細胞段階で移植すると、幹細胞ほど未分化ではないため移植先の組織になじみやすく、それでいて完全に成熟しきっていないため環境に応じた適応能力も残している、という利点があります。この考えのもと幹細胞を前駆細胞まで分化させてから移植する戦略が近年広まりつつあります。
前駆細胞応用の課題
前駆細胞は再生医療の切り札として期待されていますが、その実現にはいくつか乗り越えるべきハードルがあります。
品質のばらつき
前駆細胞は生物由来の製品であるため、ロット間や個体間で性質が異なる可能性があります。例えばドナー由来であれば提供者による品質差、自己由来であっても採取された組織や培養手技によって増殖能・分化能が変わり得ます。製造工程でのセルバンキングや標準化をしっかり行い、どのロットでも同等の性能を持つ前駆細胞を供給できる体制を築く必要があります。そのための特性解析(細胞表面マーカーや遺伝子発現の確認)が重要課題です。
分化制御の難しさ
前駆細胞を目的の細胞に確実に分化させること、あるいは逆に前駆細胞の状態で止めておくことは、技術的に繊細なコントロールを要します。分化誘導の培養条件がわずかに異なると、異なる細胞種に変化してしまったり、未分化な細胞が残存してしまったりする恐れがあります。また長期培養中に前駆細胞自体が性質変化することもありえます。このため、製造プロセスの最適化と工程ごとの品質評価(どの段階でどれだけ目的細胞に分化しているか、未分化細胞の混入はないかなど)をきちんと行う必要があります。
安全性
安全性確保は最重要課題です。
まず腫瘍化のリスクについて、幹細胞より分化が進んでいるとはいえ前駆細胞にも残存リスクがあります。特にiPS/ES由来の製品では、未分化な細胞が混入していればテラトーマ形成の可能性があるため、厳密な未分化細胞除去と腫瘍化試験が欠かせません。
次に免疫原性ですが、他人由来(同種)の細胞を使う場合、拒絶反応が起こる可能性があります。これを避けるため、自家細胞を用いるか、免疫適合性の高い細胞バンクを活用する取り組みが日本でも進んでいます。
さらに細胞にウイルスベクター等を使った場合の挿入変異リスクや、培養時に動物由来成分を使った場合の病原体混入リスクなど、総合的な安全性評価が求められます。これらに対応するため、ガイドラインに沿った規格試験をクリアしなければなりません。
おわりに
今回は「前駆細胞」について、その基本から応用まで幅広く解説しました。幹細胞と成熟細胞を繋ぐ縁の下の力持ちとして、生体内で大切な役割を果たす前駆細胞。再生医療ではその力を借りて、失われた機能を取り戻すチャレンジが行われています。研究は日進月歩で進んでおり、新しい知見が次々と報告されています。
リュウニャンのブログとしても、今後の動向を引き続き追いかけていきたいと思います。
それではまた次回、お楽しみに!