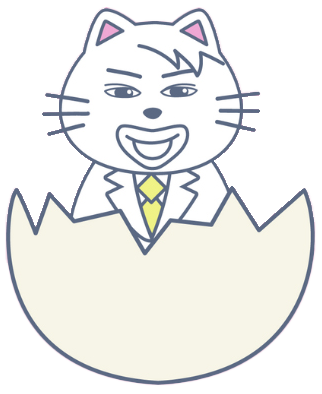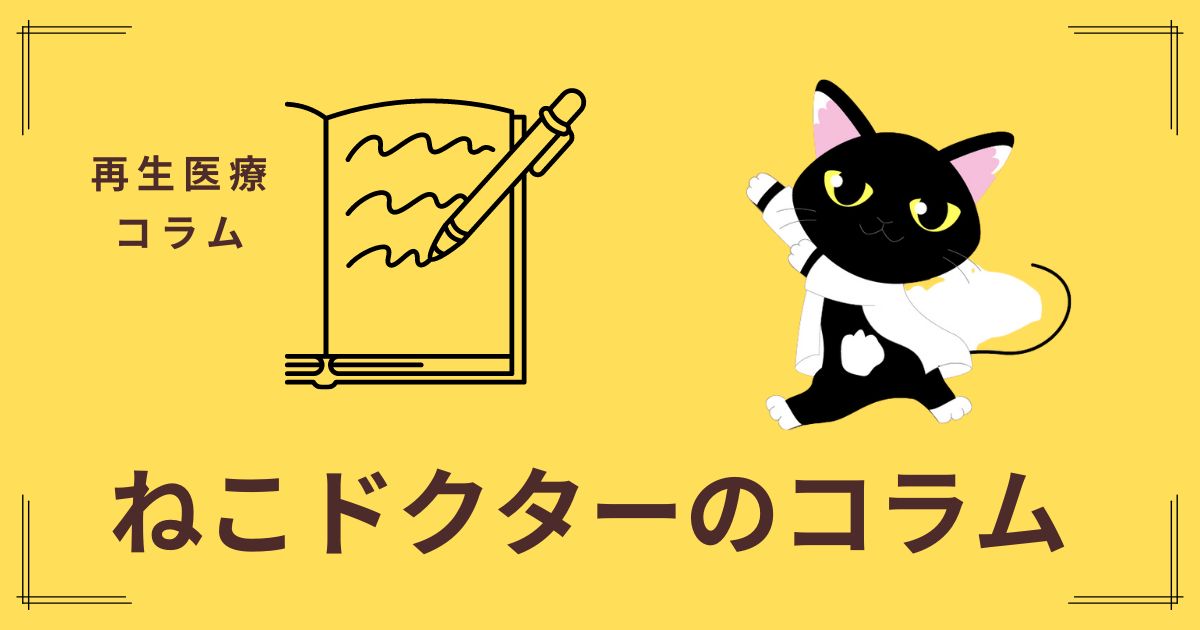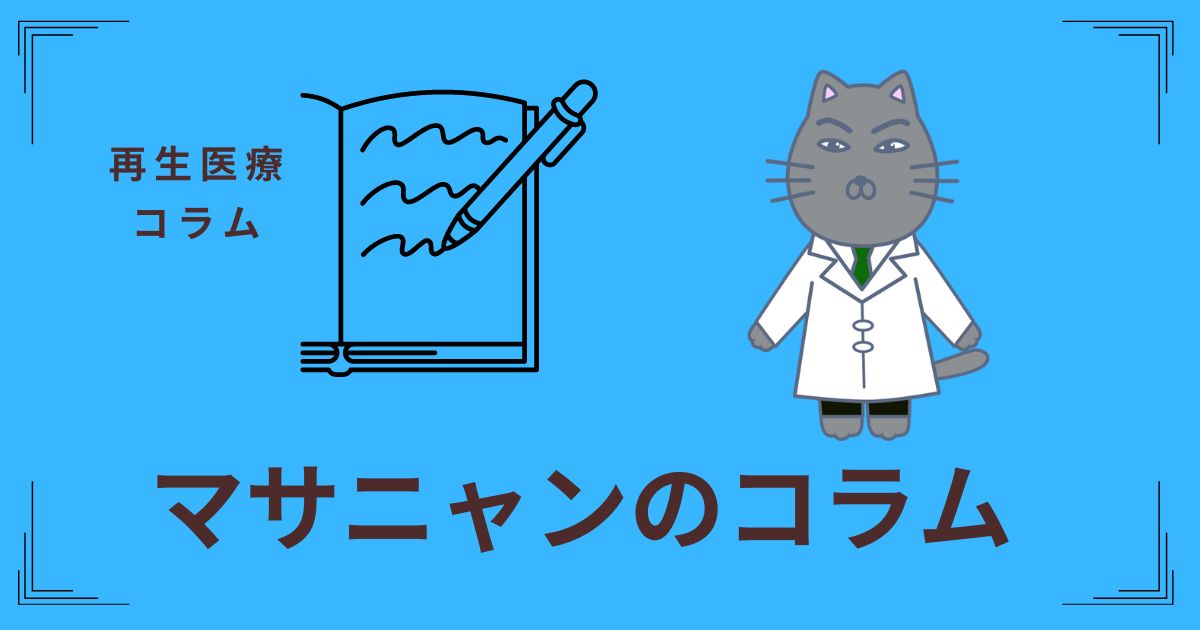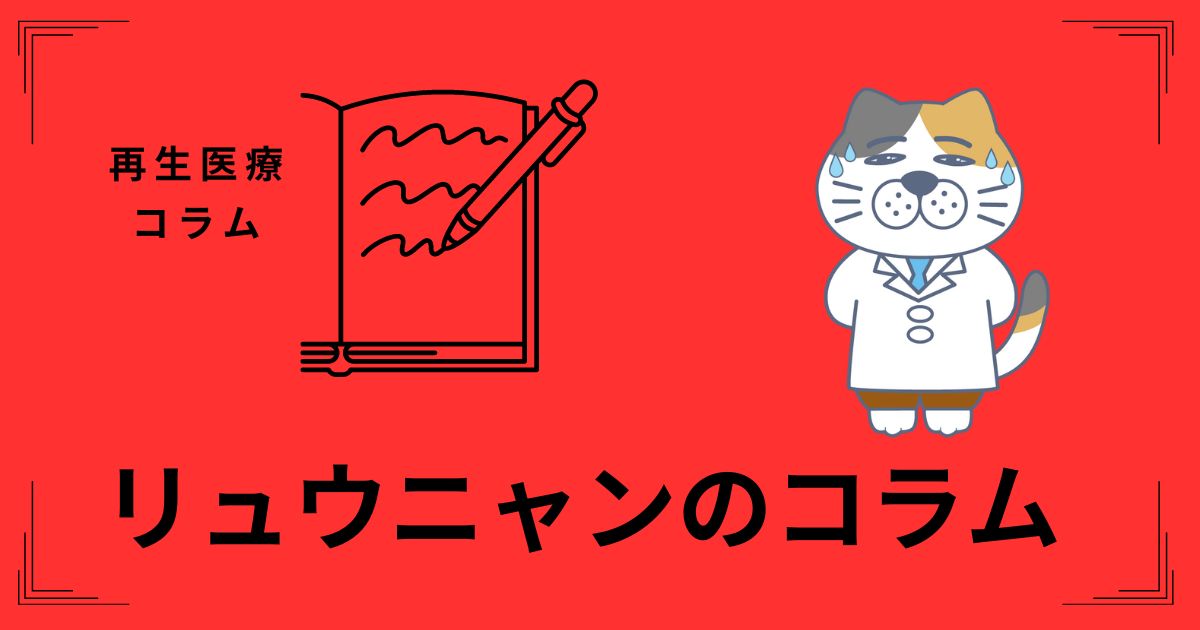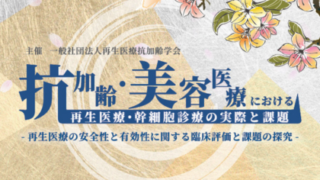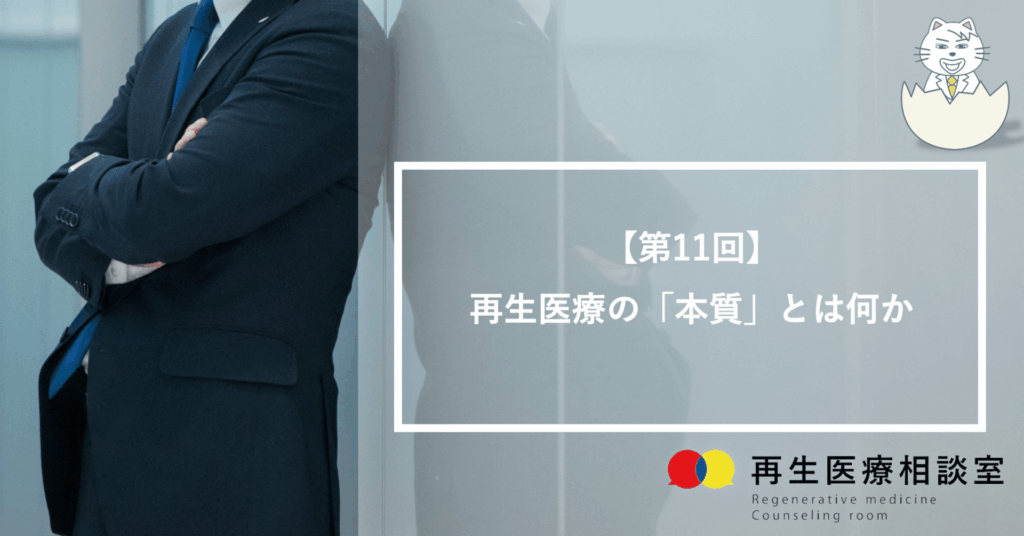
前回の記事では、日本再生医療学会の問題、そして澤芳樹氏の姿勢に対して疑問を呈しました。 学会は本来、学術団体であるはずが、現実には現場の実態からかけ離れたアカデミズムと企業癒着の構図が見えるようになっています。これは、患者不在の再生医療の象徴です…
しかし今回はその続きとして、「それでも再生医療には希望がある」と、あえて逆の側面を記しておきたいと思います。
□静かに、しかし着実に結果を出す「実用化された再生医療」
医師法下の自由診療という枠組みの中で、既に多くの臨床家が幹細胞やNK細胞、サイトカインなどを用いた治療が世界的に行われています。 この領域は、必ずしもメディアで取り上げられるわけでもなく、論文として表に出ることも多くはない。 ですが、“誰かを救った事実”という実績は、現場に蓄積されている。
再生医療は「未来の技術」ではないです。 既に、一部の分野では“今”の技術であり、実用化されている現実があり、患者様を救っているのを私は何度も目の当たりにしています。
□iPS細胞と「今できる医療」の乖離
例えば、iPS細胞は依然として“夢の技術”として扱われています。 その進展には時間がかかり、未だ保険診療の範囲に入るものは極めて限られます。
その一方で、間葉系幹細胞(MSC)を活用した治療が、加齢性疾患や慢性疾患、神経疾患等様々な領域に対して着実な成果を出している。 これは、数十年後の未来を見据える研究と、数か月後の回復を求める患者との「時間軸の乖離」を示しています。
つまり、研究者やアカデミアが描いている「理想的な再生医療の未来像」と、実際に今苦しんでいる患者が求めている治療との間に大きなギャップがあるということです。
□本当の課題は「信頼の分配」
再生医療をめぐる現在の問題は、技術の有無ではなく、“どこに信頼を置くか”という構造の問題である。 国家の承認があるから安心か。 学会に属しているから正しいのか。学会の指針が正しいのか。 企業が出資しているから確かなのか。
本来、患者は「自分にとって何が正しいか」で判断すべきですが、
現実には「肩書や制度、広告イメージ」といった外的要因によって「信頼」の方向性が操作されています。
現場で起きていることを無視して、「承認されたもの」だけを正義として扱う風潮や現場の中でもビジネス的一面に囚われた医師や企業の誇大広告の中で、 患者は正しい選択をする機会を奪われている。
本来、医療は“制度”のためにあるのではなく、患者一人ひとりのQOLを守るために存在している。 その視点を失ったとき、いくら学問的に正しくても、それは医療ではないと私は思います。
□最後に:再生医療の「可能性」を守るために
再生医療は、決して魔法のような治療ではない。 しかし、現代医療では手が届かなかった領域を補完する技術として、 確かな可能性を持っているのも事実で、私はそれを何度も目の当たりにしてきました。
だからこそ、学会の迷走や研究偏重の体質に対して、
現場の医療者がどう向き合うか、どう説明するかが問われている。
患者に「わかりやすく」「誠実に」伝えること
そこにこそ、再生医療の本当の価値を創ると信じて私はこれからも発信をしていきます。