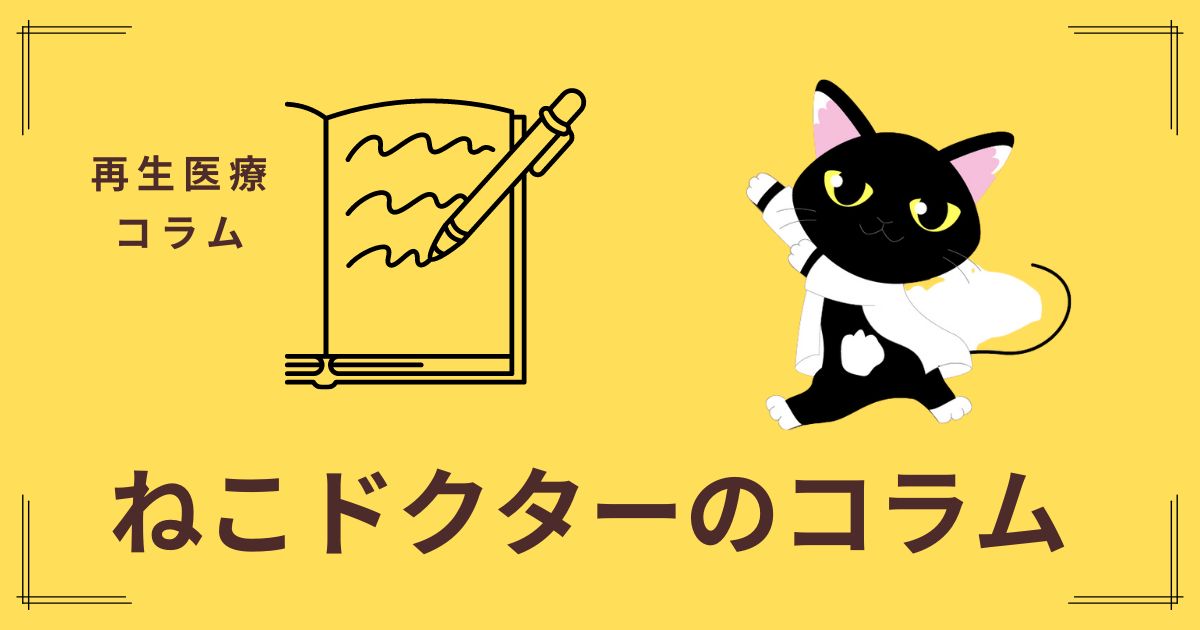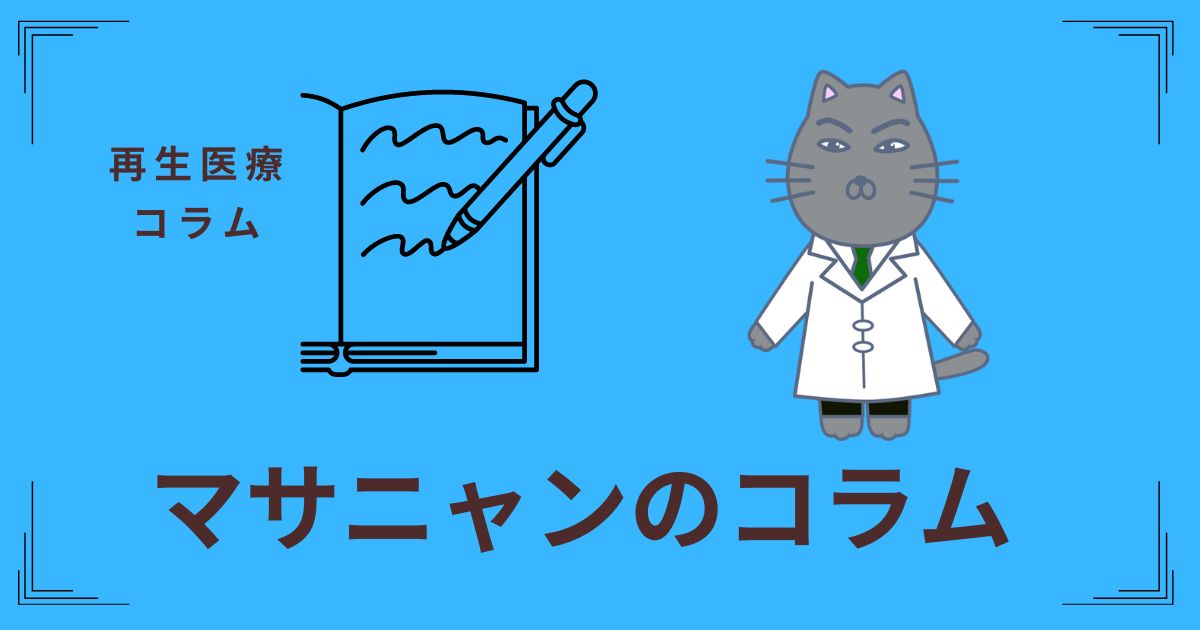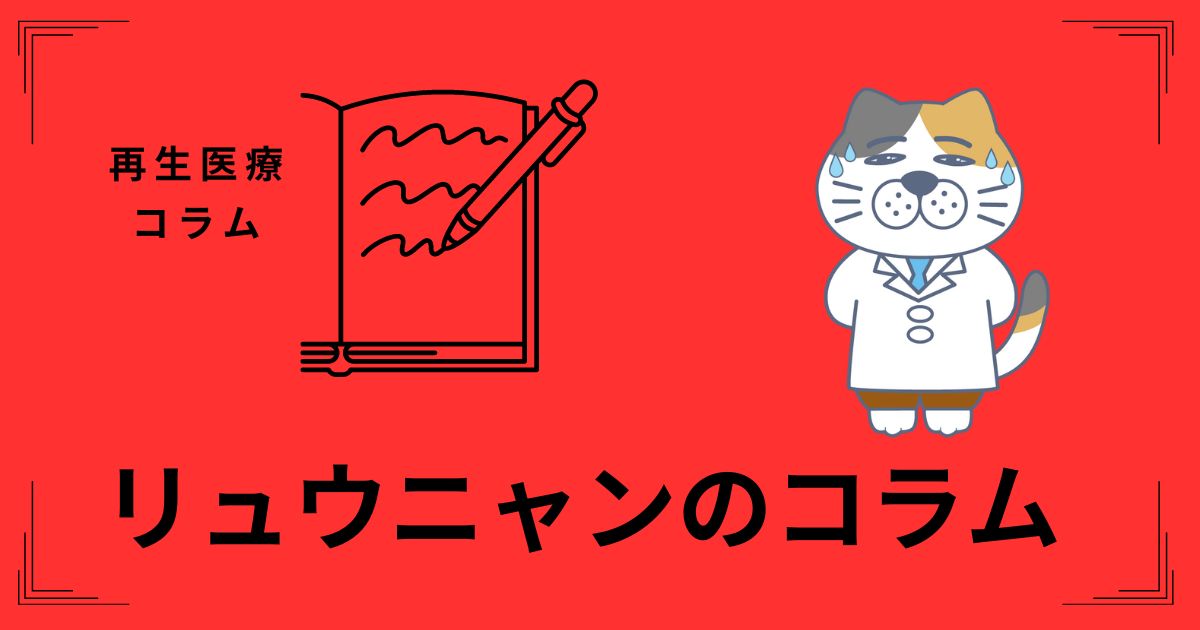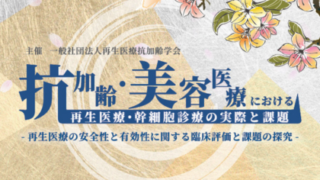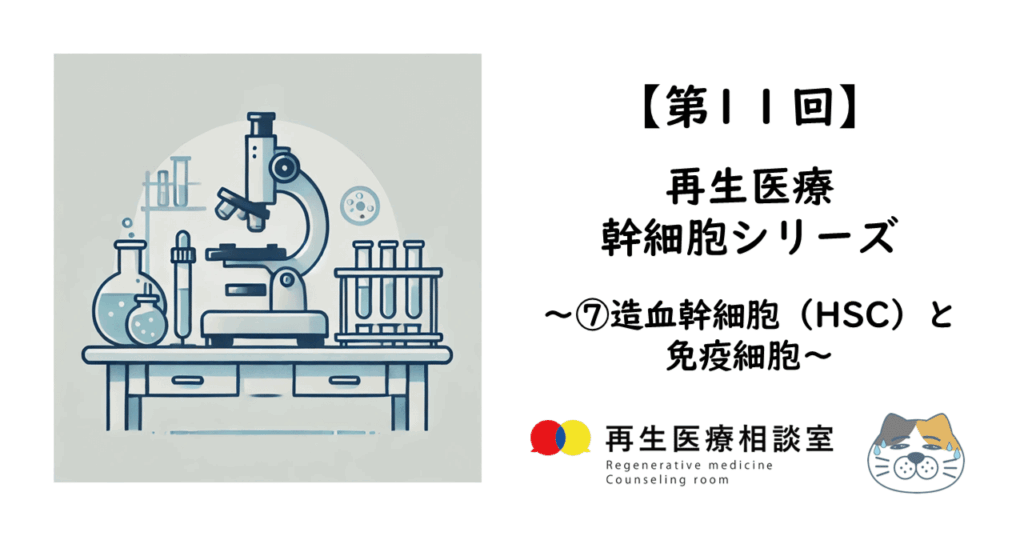
こんにちは、リュウニャンです!
前回・前々回にわたっては、再生医療の現場でもっとも注目されている幹細胞のひとつ「間葉系幹細胞(MSC)」について、前編・後編に分けてお届けしてきました。MSCの性質や採取方法、そして治療への応用までご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
今回はその続きとして、造血幹細胞(HSC)と免疫細胞についてお話していきたいと思います。
造血幹細胞は、私たちの体を日々支えてくれている“血液”を生み出す、とても重要な幹細胞です。そして、その造血幹細胞から分化する免疫細胞は、感染やがんと戦う私たちの“体内の守り手”でもあります。
白血病などの難治性疾患に対する造血幹細胞移植、がんに対する最新の免疫細胞治療(たとえばCAR-T療法)などについて、できるだけわかりやすく解説していきますので、初めての方も安心して読んでみてください。
造血幹細胞の定義と名前の由来
造血幹細胞(Hematopoietic Stem Cell, HSC)とは、血液中のあらゆる細胞を生み出す元となる幹細胞です。骨髄の中に存在し、自己複製によって自分の分身を維持しながら、多様な血液細胞へと分化する能力を持っています。いわば血液細胞の「母体」であり、必要に応じて赤血球や白血球など新しい血の細胞を供給し続けています。
「造血幹細胞」という名称は、「血液を造る幹(みき)の細胞」という意味で、その“幹”は系統樹の幹(ステム)に例えられます。この概念は1908年にロシアのマクシモフが提唱し、彼はすべての血液細胞が単一の祖先細胞から発生すると考えてそれを「ステムセル(幹細胞)」と呼びました。1961年にはティルとマカラックによるマウス実験で骨髄中に血液再生能を持つ細胞が存在することが証明され、以降「造血幹細胞」という概念が確立しました。
発見の歴史と造血幹細胞の特徴
造血幹細胞の存在は20世紀半ばに実証され、以来その性質が詳しく研究されてきました。骨髄の中の造血幹細胞は全体のごく一部(骨髄細胞の1万分の1以下)ですが、一生涯にわたり血液を作り続けます。1日あたり数千億個もの血液細胞が産生されるほど需要が大きいですが、限られた造血幹細胞が自己複製能(自分と同じ細胞を作る)と多分化能(様々な血液細胞に分化する)を駆使してこの需要を支えています。
造血幹細胞は骨髄内の「ニッチ」と呼ばれる特殊な環境に存在し、骨髄の支持細胞からのシグナルによってその性質を保たれています。このニッチは幹細胞の揺りかごのような役割を果たし、幹細胞が必要に応じて増えたり休んだりするのを調節しています。
造血幹細胞が存在する場所と採取源
成人では造血幹細胞は主に骨髄(背骨や骨盤などの中の柔らかい組織)に存在します。医療では、造血幹細胞を以下の方法で採取して利用することができます:
-
骨髄採取: 全身麻酔下で骨盤の骨に針を刺し、1リットル前後の骨髄液を吸引します。吸引液中に含まれる造血幹細胞を集めて移植に用います(ドナーの骨髄は数週間で回復します)。
-
末梢血幹細胞採取: ドナーに数日間G-CSF(顆粒球コロニー形成刺激因子)という薬剤を注射して造血幹細胞を骨髄から血液中に動員し、腕から血液を採取してアフェレシス(成分採取)で幹細胞を濾し取ります。約300mL程度の血液成分中に幹細胞が濃縮されます。
-
臍帯血: 出産時に胎盤や臍帯(へその緒)に残った血液を約20mLほど採取し、専用バンクで冷凍保存しておきます。臍帯血は提供者への負担なく入手でき、かつHLA型の適合が多少緩くても使える利点があります。その反面、一度に採れる細胞数が少ないため成人への移植では不足しがちですが、日本では複数の臍帯血を併用する工夫などで多くの実績を上げています。
日本では毎年およそ2,000~3,000件の造血幹細胞移植が行われており、そのうち非血縁者からの提供では臍帯血移植が骨髄・末梢血移植を上回る年が続いています。これは臍帯血バンクの整備によるもので、国内に6バンクで約1万本の臍帯血が保管されています。一方、骨髄バンクにも約55万人のドナーが登録(2023年時点)され、患者に合うドナーがいない場合は国際的なドナー検索も活用されています。
血液細胞と免疫細胞の関係
造血幹細胞からはまず骨髄系とリンパ系の系統に分かれ、そこからさまざまな成熟血液細胞が生まれます。
骨髄系からは赤血球(酸素を運ぶ)や血小板(止血に働く)、マクロファージや好中球など生まれつきの免疫細胞(異物を食べたり殺菌する細胞)が分化します。
一方リンパ系からはリンパ球と総称される免疫細胞、主にT細胞・B細胞・NK細胞が分化します。これら免疫細胞はそれぞれ専門の役割があります:
-
T細胞: 胸腺で成熟するリンパ球で、指令塔役のヘルパーT細胞と、感染細胞やがん細胞を直接攻撃するキラーT細胞があります。免疫全体の司令官として機能します。
-
B細胞: 骨髄で成熟するリンパ球で、抗体を産生する細胞です。抗体は病原体に結合して無力化し、他の免疫細胞による排除を助けます。
-
NK細胞: 自然免疫を担うリンパ球で、体内をパトロールしてウイルス感染細胞や腫瘍細胞を見つけ次第破壊します。生得的な殺傷能力を持つため「ナチュラルキラー」と呼ばれます。
-
マクロファージ: 大型の貪食細胞で、体内に侵入した細菌などを丸呑みして消化し処理します。同時に、その情報をT細胞に提示して免疫の後方支援も行う、掃除屋兼伝令役です。
このように造血幹細胞は血液細胞および免疫細胞すべての出発点であり、これが正常に機能することで私たちの体は酸素供給や感染防御といった生命維持活動を営めています。
造血幹細胞移植
治療の仕組み
造血幹細胞移植(Hematopoietic Stem Cell Transplantation, HSCT)は、病気で損なわれた造血・免疫システムを新しい造血幹細胞で置き換える治療法です。大別すると、患者自身の幹細胞を使う自家移植と、他人(ドナー)の幹細胞を使う同種移植があります。
自家移植は、患者からあらかじめ採取・保存した造血幹細胞を、大量の化学療法・放射線療法でがん細胞を叩いた後に体内へ戻す方法です。自分の細胞なので拒絶反応や移植片対宿主病(GVHD)の心配がない利点があります。主に悪性リンパ腫や多発性骨髄腫などで、高 dose療法後の“救援措置”として行われます。
同種移植は、HLA型の合うドナー(兄弟姉妹や骨髄バンク登録者など)や保存臍帯血から提供された造血幹細胞を移植する方法です。前処置として患者の病的な骨髄を一掃し、そこにドナー由来の幹細胞が定着して新しい血液を作り始めます。ドナーの免疫が患者のがんを攻撃する効果(移植片対腫瘍効果)も期待でき、再発リスクの高い白血病などではこの効果が治療成功の鍵となります。
ただし同種移植では、ドナー免疫が患者の正常組織を攻撃してしまうGVHDという重篤な合併症が発生する可能性があります。そのため免疫抑制剤によるコントロールが必要であり、感染症にも注意が必要です。
移植後、移入された造血幹細胞が生着すると、約2〜3週間で白血球(好中球)が回復し始め、続いて赤血球や血小板も増えていきます(免疫再構築)。この間患者は外部からの細菌やウイルスに極めて弱いため、無菌的管理や予防投薬が行われます。順調にいけば数ヶ月~1年で免疫機能がほぼ正常化し、新しい血液システムが体内で定常状態に至ります。
利点とリスク
造血幹細胞移植は非常に強力な治療で、他の治療では治せない病を根治させる可能性があります。例えば、ある種の白血病では移植の導入によってそれまで0%だった長期生存率が90%近くにまで改善した例もあります。特に同種移植ではドナーの免疫による抗白血病効果が得られるため、再発リスクの高い患者でも長期寛解が期待できます。
一方でリスクや課題も大きい治療です。GVHDに代表される免疫合併症は患者のQOLや生命を脅かし得ますし、無菌室管理が必要な期間は感染症との戦いになります。また、適合ドナーが見つからない問題も常に付きまといます治療コストも高額で、長期入院や特殊薬剤を要します。しかし日本では公的保険や助成制度により患者負担は抑えられ、先進医療として確立しています。
白血病に対する移植治療とCAR-T療法の登場
白血病のうち、再発・難治性のケースでは造血幹細胞移植がしばしば唯一の根治手段となります。強力な前処置とドナー細胞による免疫効果で白血病細胞を一掃し、再発を防ぐ狙いです。実際、再発した急性白血病患者に同種移植を行って相当数が長期生存を得ており、移植医療は血液がん治療の柱となっています。
近年、この分野にCAR-T細胞療法という新たな武器も加わりました。CAR-T療法とは、患者自身のT細胞を取り出して遺伝子改変し、がん細胞を狙う人工受容体(CAR)を発現させたT細胞を体内に戻す治療です。体内に戻ったCAR-T細胞は標識となるがん細胞(例えばB細胞系白血病のCD19抗原)を認識し、強力に攻撃・破壊します。臨床試験で劇的な効果が示され、2017年に米国で初めて承認、続いて2019年には日本でも小児・若年成人の難治性B細胞性白血病と一部の悪性リンパ腫に対して承認されました。
CAR-T療法はそれまで治療不可能だった患者を寛解に導く例があり、「生きた特効薬」とも言われます。ただし現状では適応疾患が限られており、主にB細胞系の血液がんに有効です。また副作用としてサイトカイン放出症候群(高熱・血圧低下など)や一過性の神経毒性が起こることがあり、集中治療体制のある施設で管理されます。それでも従来の移植に比べると身体的負担は一時的で済み、高齢の患者でも適応可能な場合があります。
移植とCAR-Tの比較・使い分け
適応範囲の点で、造血幹細胞移植は白血病・リンパ腫のみならず再生不良性貧血や先天性免疫不全症など非悪性疾患にも用いられるのに対し、CAR-T療法は現在のところ特定の血液がんに限られています。作用機序も、移植は患者の血液造血システムを丸ごと入れ替えるのに対し、CAR-Tはがん細胞だけをピンポイントに攻撃します。
リスク面では、移植はGVHDや重篤感染症といった長期管理のリスクが大きく、CAR-Tは急性期の副作用管理が中心です。コストはCAR-T療法が極めて高額(1回の治療で数千万円規模)であるのに対し、HSCTも高価ですが保険診療で広く行われています。
将来的には、CAR-T療法がさらに発展して移植の代替となる領域が増える可能性があります。しかし現段階では、移植とCAR-Tは相補的に使われることも多いです。例えばCAR-Tでいったん白血病を寛解させた後、その効果を維持するために同種移植を行う戦略や、逆に移植前のブリッジ治療にCAR-Tを用いる例もあります。患者の状態や病態に応じて両者を使い分け、組み合わせることで最善の治療結果を目指す方向に進んでいます。
今後の展望
血液・造血の医療領域は今、急速な技術革新の途上にあります。中でも期待される新技術として:
-
遺伝子編集を用いた造血幹細胞治療: 患者自身の造血幹細胞の遺伝子をCRISPR-Cas9で書き換えてから体に戻し、病気の原因を取り除く治療です。鎌状赤血球症では既にこの方法で疼痛発作をなくす治療法が欧米で承認されました。従来は移植しか治せなかった難病が、一度の遺伝子編集で治る可能性が出てきたのです。
- 人工血液: 人工的に作った赤血球や血小板で輸血を代替する研究です。iPS細胞から大量の血液細胞を培養する技術が開発途上で、日本でも実用化に向けた試験が行われています。実現すれば血液製剤不足や感染リスクの低減に大きく寄与するでしょう。
- “オフ・ザ・シェルフ”の細胞療法: 現在のCAR-Tは患者ごとに細胞を作製しますが、あらかじめ健康ドナー由来の汎用CAR-T細胞やCAR-NK細胞をストックしておき、必要な時にすぐ使えるようにする取り組みが進んでいます。これによりコスト低減や治療待機時間短縮が期待されます。
日本発のiPS細胞技術や世界的な遺伝子治療の波により、造血幹細胞と免疫細胞の治療応用はこれからさらに拡大するでしょう。難題であったドナー不足や副作用も、新技術で乗り越えられる日が来るかもしれません。造血幹細胞は血液という生命維持システムの源であり、その力を最大限に引き出す医学の進歩によって、多くの患者さんに新たな命のチャンスがもたらされることが期待されています。
今回は、造血幹細胞と免疫細胞について、その役割や治療への応用、さらには最新のがん免疫療法までご紹介しました。
さて、次回は少し視点を変えて、幹細胞ではないけれど、いま日本の自由診療でも注目されている「免疫細胞療法」について特集します!
特に、「樹状細胞」や「NK細胞(ナチュラルキラー細胞)」といった、免疫治療で話題の細胞たちを取り上げ、どんな働きをするのか、どのように治療に使われているのかを、わかりやすくお届けする予定です。
次回もぜひ楽しみにお待ちくださいね!