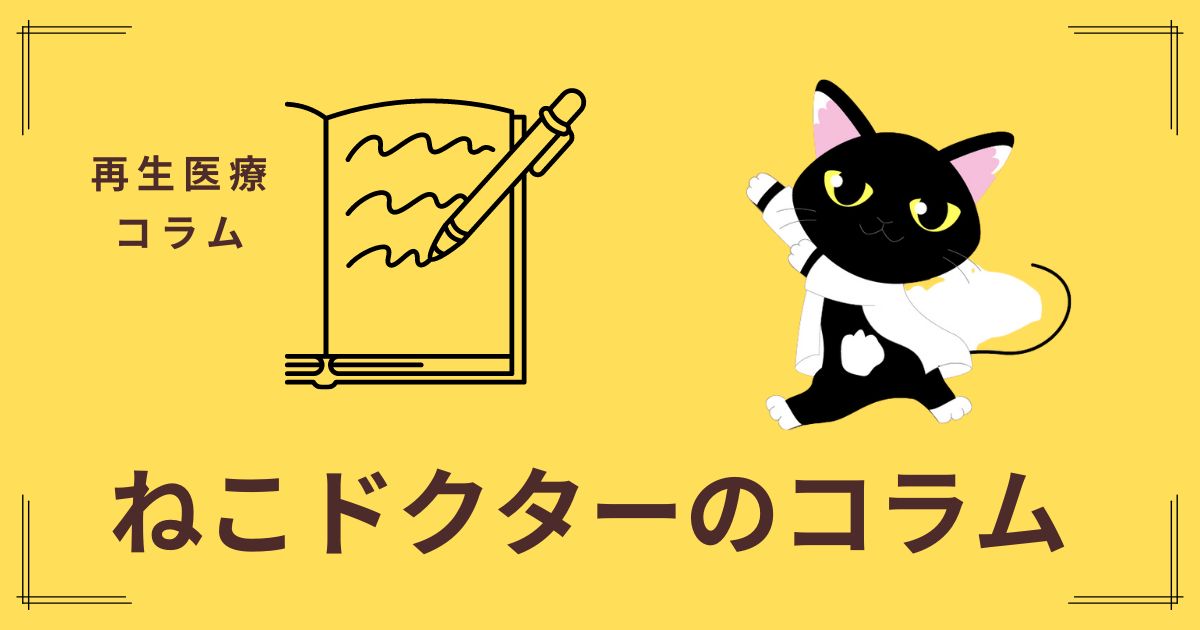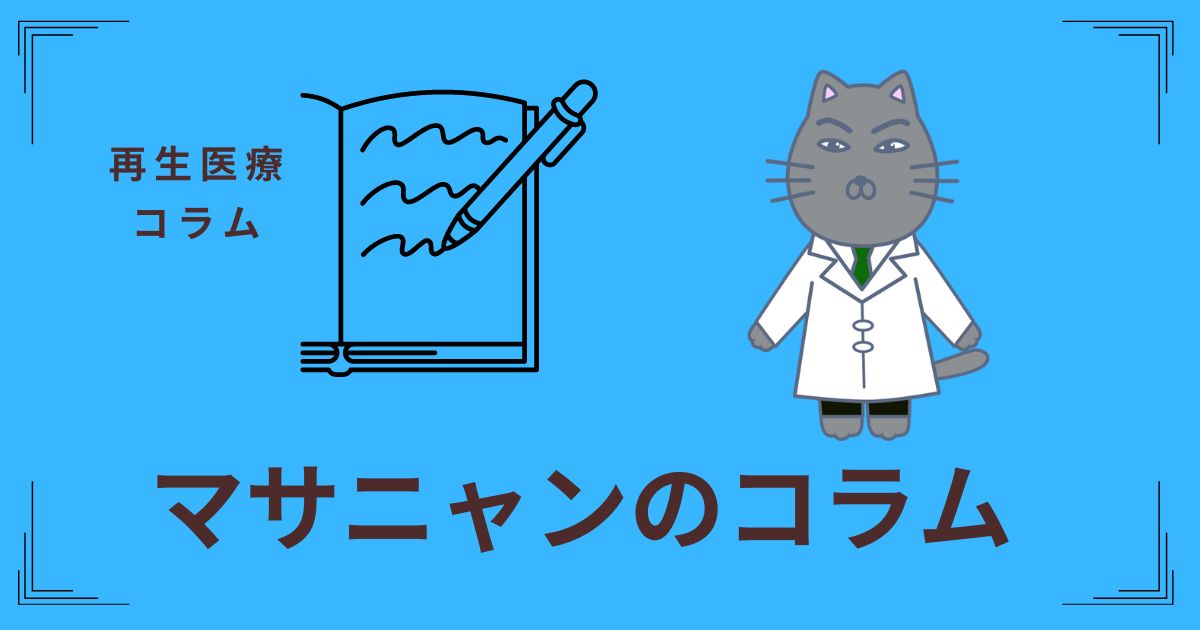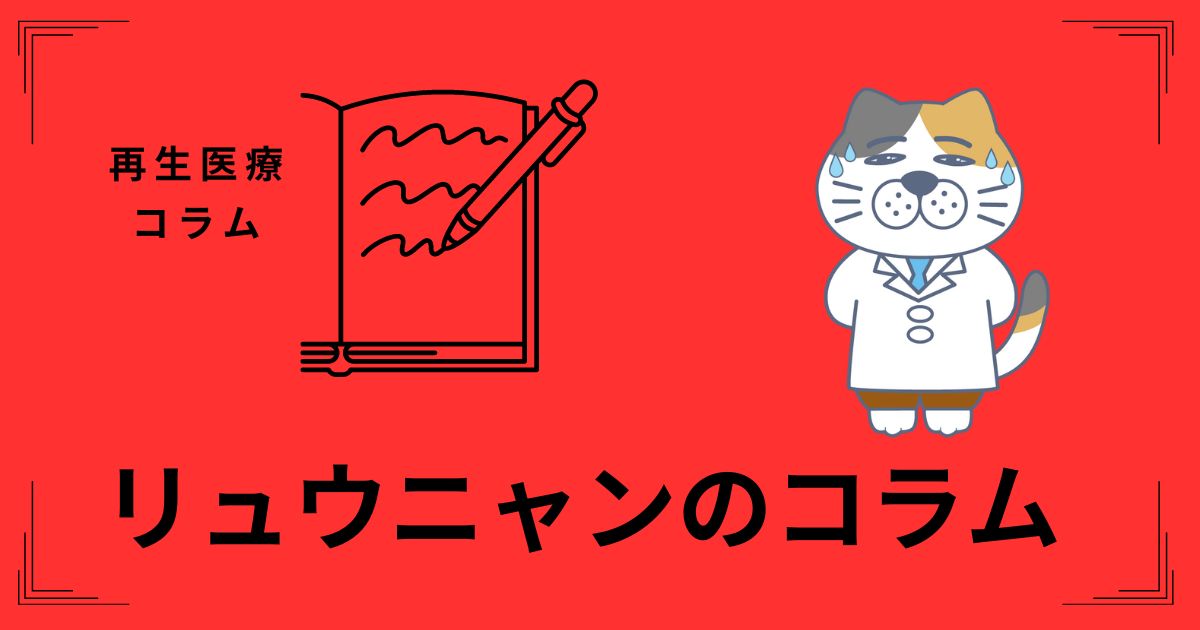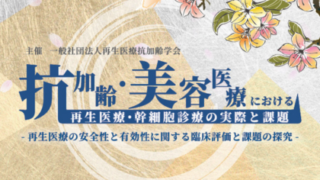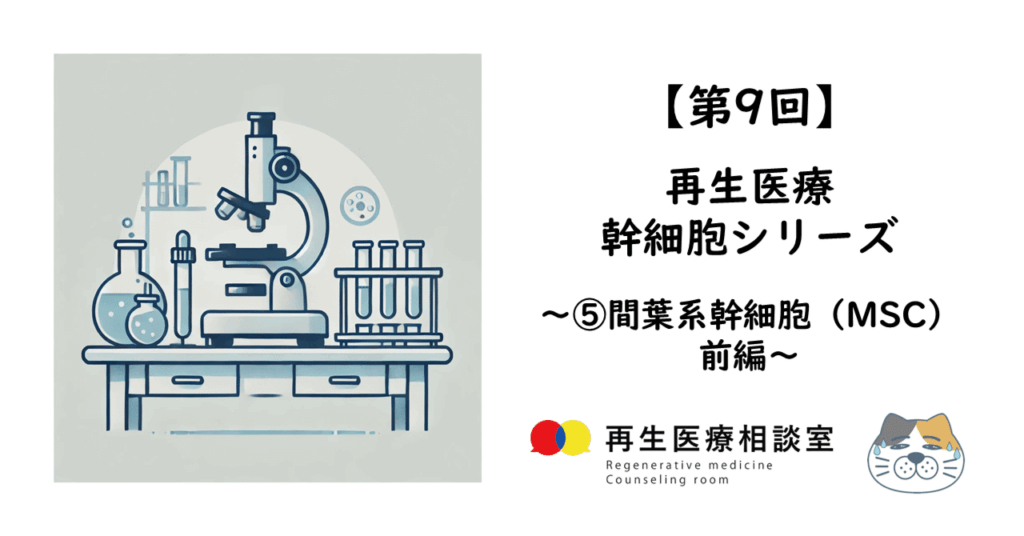
こんにちは!今回も「再生医療 幹細胞シリーズ」をお届けします。
前回までに、多能性幹細胞であるES細胞(胚性幹細胞)とiPS細胞(人工多能性幹細胞)について紹介しました。これらの細胞の大きな強みは、体内のほぼすべての細胞に分化できる「高い分化能力」にあります。
しかし、ES細胞には倫理的な問題や免疫拒絶のリスクがあり、iPS細胞にも腫瘍化のリスクや作製コストの高さなど、実用化に向けた課題が残されています。
そこで今回は、より実用化に近い幹細胞である成体幹細胞に注目します。
成体幹細胞とは、すでに成熟した組織内に存在し、特定の組織や臓器の修復・再生を担う細胞です。その中でも特に再生医療への応用が期待されているのが、間葉系幹細胞です。
今回の前編では、間葉系幹細胞の基本に迫ります!その定義、特徴、どこに存在するのか、そしてどうやって取り出すのかを詳しく解説します。
そして次回の後編では、MSCがどのように臨床研究で活用されているのか、治療のメカニズム、再生医療への応用、さらには今後の課題について深掘りしていきます。
再生医療を支える注目の細胞MSCは、ES細胞やiPS細胞と何が違うのか? 医療の現場でどう役立つのか? 一緒に探っていきましょう!ぜひ最後までお楽しみください!
成体幹細胞とは
私たちの体は、日々の生活の中で細胞がダメージを受けたり、寿命を迎えたりしながらも、新しい細胞が生まれることで健康を維持しています。そんな細胞の入れ替えを支えているのが成体幹細胞(Adult Stem Cells)です。
成体幹細胞は、私たちの組織や臓器を修復・維持するために働く幹細胞であり、再生医療の現場でも注目されています。
定義と役割
成体幹細胞とは、生体内特定の組織や臓器の中に存在し、特定の細胞に分化しながら組織の修復や再生を担う幹細胞です。
成体幹細胞は、決まった組織に存在し、その組織に必要な細胞にのみ分化するため、多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞)のようにあらゆる細胞になれるわけではありません。しかし、逆に腫瘍化のリスクが低く、安全性が高いという利点があります。
種類
成体幹細胞は、私たちの体のさまざまな部位に存在し、それぞれ異なる細胞へと分化する能力を持っています。代表的な成体幹細胞には次のようなものがあります。
-
造血幹細胞(Hematopoietic Stem Cells: HSC)
由来:骨髄、臍帯血、末梢血
分化できる細胞:赤血球、白血球、血小板など
特徴:血液を作り出し、免疫機能を支える -
間葉系幹細胞(Mesenchymal Stem Cells: MSC)
由来:骨髄、脂肪、臍帯、歯髄、滑膜など
分化できる細胞:骨、軟骨、脂肪、筋肉、神経など
特徴:組織の修復や炎症の抑制作用を持ち、再生医療で注目される -
神経幹細胞(Neural Stem Cells: NSC)
由来:脳(海馬、側脳室)
分化できる細胞:ニューロン(神経細胞)、グリア細胞
特徴:脳や神経系の再生に関与し、脳梗塞や脊髄損傷の治療に期待される
発見
成体幹細胞の研究は、1960年代にカナダのジェイムズ・ティルとアーネスト・マコラックによって、骨髄から造血幹細胞が発見されたことから始まりました。その後、1970年代には骨髄由来の間葉系幹細胞(MSC)が見出され、他の組織からも次々と幹細胞が発見されるようになりました。
間葉系幹細胞とは
定義
間葉系幹細胞(Mesenchymal Stem Cells、略してMSC)は、自己複製能を持ち、骨、軟骨、脂肪などさまざまな細胞に分化する能力を持つ細胞です。さらに、特定のシグナルを放出することで、免疫系のバランスを調整したり、炎症を抑制したり、損傷した組織を修復したりする働きもあります。
しかし、MSCはさまざまな組織から採取できるため、かつてはその定義が明確ではありませんでした。そこで、国際細胞治療学会(International Society for Cellular Therapy, ISCT) は、MSCの特徴を統一するために、以下の3つの基準を満たす細胞を「間葉系幹細胞」と定義しました。
-
プラスチック表面への接着性
MSCは、標準的な培養条件下でプラスチック表面に接着する性質を持っています。これは、血液細胞のように浮遊する細胞とは異なり、MSCが培養皿のプラスチックに付着して増殖することで、他の細胞との識別が容易になる特性です。 -
特定の細胞マーカーを持つこと
MSCは、特定の細胞表面マーカーを持つことが特徴です。ISCTは、MSCの識別のために以下のマーカーを基準としています。
発現するマーカー(MSCの代表的なマーカー):CD73、CD90、CD105
発現しないマーカー(造血幹細胞や免疫細胞ではないことを示す):CD14、CD34、CD45、HLA-DR -
骨・軟骨・脂肪への分化能力
MSCは、骨芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞へ分化する能力を持っています。
名前の由来
再生医療の分野で注目されている間葉系幹細胞という名前は、実は約25年以上前に正式に命名されました。その背景には、MSCの発見や特徴、そして研究の進展による変遷が関係しています。
間葉系幹細胞という名称が公式に使われるようになったのは、1990年代のことです。
もともと、この細胞はヒトや哺乳類の骨髄や骨膜(骨を覆う膜)から採取され、培養することで骨・軟骨・脂肪へと分化できることが確認されました。
そのため、次の2つの特徴を組み合わせて「間葉系幹細胞(Mesenchymal Stem Cells)」と名付けられました。
「間葉(Mesenchymal)」 → 骨や軟骨などの結合組織のもとになる細胞
「幹細胞(Stem Cells)」 → 増殖・分化する能力を持つ細胞
また、「間葉」とは、体のさまざまな組織を形成する中胚葉性の細胞からなる組織を指します。
発見と命名の変遷
-
1970年代:骨髄由来の幹細胞の発見
1970年代には、骨髄の中にスピンドル型(紡錘形)の細胞が見つかり、これが培養条件下で骨や軟骨に分化できることが確認されました。
この細胞が、後に「間葉系幹細胞」と呼ばれる細胞の起源となります。 -
1990年代:間葉系幹細胞(MSC)という名前の誕生
その後の研究により、この細胞が骨髄から分離できること、さらに再生医療への応用が期待できることが明らかになりました。
そこで1990年代に、「Mesenchymal Stem Cells(間葉系幹細胞)」という名称が正式に提唱されました。 -
現在:多様な組織に由来するMSC
当初は骨髄由来の間葉系幹細胞が主流でしたが、研究が進むにつれ、脂肪組織・臍帯・歯髄など、さまざまな組織からもMSCが分離できることが判明しました。
現在では、MSCは単に「Mesenchymal Stem Cells(間葉系幹細胞)」と呼ぶだけでなく、採取された組織ごとに異なる名称が付けられることもあります。
骨髄由来幹細胞(Bone Marrow Stem Cells, BMSC)
脂肪組織由来幹細胞(Adipose-Derived Stem Cells, ADSC)
臍帯由来幹細胞(Umbilical Cord-Derived Stem Cells, UCSC)
このように、MSCは「どの組織から採取されたか」によって分類されるようになり、「間葉系幹細胞」という名称は、より広い意味を持つ概念へと進化してきました。
由来組織
間葉系幹細胞は、私たちの体のさまざまな組織に存在しています。その大きな特徴の一つが、「多様な組織から採取できる」 という点です。
-
骨髄由来MSC
MSC研究のスタンダード!
骨髄由来のMSCは、1960年代に最初に発見されたMSC であり、現在も最もよく研究されている供給源の一つです。
研究の歴史が長くデータが豊富で、骨や軟骨への分化能力が高いというメリットがありますが、採取には骨髄穿刺が必要となり、患者への負担が大きいというデメリットがあります。 -
脂肪由来MSC
採取しやすく豊富に存在!
脂肪組織にはMSCが豊富に含まれており、2001年に初めて報告されて以来、再生医療や美容医療分野で注目されています。脂肪吸引の副産物として採取できるため負担が少ない というメリットがあります -
臍帯血・胎盤由来MSC
出産時に得られる若い細胞!
臍帯血や胎盤には、若くて活発なMSCが豊富に含まれています。採取が非侵襲的で母子に負担をかけないため、安全に得られるというメリットがあります。しかし、他家移植となるため、免疫拒絶のリスクがあるという懸念もあります。 -
歯髄由来MSC
歯の中にも幹細胞が!
親知らずや乳歯の歯髄(抜歯後の歯から得られる)から採取されるMSCで、神経細胞への分化能力があるため、神経再生治療への応用が期待されています。
単離方法
間葉系幹細胞を治療に使うためには、骨髄や脂肪、臍帯血などさまざまな組織から単離(分離・抽出)することができます。単離したMSCは、その後の培養を経て増殖させ、再生医療や細胞治療に活用されます。
MSCの単離は、①組織の採取→②細胞の分離→③培養・増殖という流れで行われます。単離方法は組織の種類によって異なり、それぞれの組織に適した技術が用いられます。
-
骨髄由来MSC
-
骨髄穿刺
骨髄液を採取するために、専用の針を使用して骨の内部(腸骨など)から1mLの骨髄を吸引します。 -
希釈と遠心分離
採取した骨髄をリン酸緩衝生理食塩水(PBS)で1:1に希釈し、3,000rpmで30分間遠心分離します。 -
バフィーコートの回収
遠心分離後、白血球や幹細胞が含まれる「バフィーコート」と呼ばれる層を回収します。 -
培養と増殖
回収した細胞を培養フラスコに移し、培養培地を用いて培養します。MSCはプラスチック表面に接着する性質があるため、他の細胞が洗い流され、MSのみが培養皿に残ります。
-
脂肪由来MSC
-
脂肪組織の採取
皮下脂肪を吸引または切除して採取します。 -
組織の細断
採取した脂肪組織を、ハサミやメスで細かく刻みます。 -
コラゲナーゼ処理
コラゲナーゼ酵素(Type I)を加え、37℃の温水浴で1時間攪拌しながら処理し、脂肪細胞とMSCを分離します。 -
遠心分離と濾過
処理後、遠心分離して脂肪層を除去し、100μmと40μmのフィルターで細胞を濾過します。 -
培養と増殖
PBSで細胞を洗浄し、培養培地で培養を開始します。
-
臍帯血由来MSC
-
臍帯血の採取
出産時にへその緒から臍帯血を採取します。 -
バフィーコートの分離
遠心分離を行い、単核細胞(MNCs)が含まれるバフィーコートを回収します。 -
培養と増殖
フラスコに細胞を播種し、非接着細胞を48時間後に除去し、MSCのみを増殖させます。
加齢による影響
「若いころはケガがすぐに治ったのに、年齢を重ねると治りが遅くなった…」
そんな経験はありませんか?
実は、これは幹細胞の減少と深く関係しています。
間葉系幹細胞(MSC)は、年齢とともに数が減少することが知られており、これが体の回復力の低下や老化の一因となっています。
研究によると、骨髄中に含まれるMSCの割合は、以下のように加齢とともに減少します。
- 新生児:1/10,000(約1万個に1個の割合)
- 50歳代:1/400,000(約40万個に1個の割合)
- 80歳代:1/2,000,000(約200万個に1個の割合)
つまり、新生児と比べると、80歳の高齢者ではMSCの数が1/200まで減少してしまうのです。
MSCの数が減少すると、再生能力が低下し、骨折の治癒遅延や骨粗しょう症のリスク増加などの問題が生じやすくなります。
間葉系幹細胞と線維芽細胞の違い
間葉系幹細胞(MSC)と線維芽細胞(Fibroblast)は、形がよく似ているため、見た目だけでは区別が難しいことが多いです。特に、以下のような点で混同されることがあります。
-
どちらも紡錘形(細長い形)をしている
-
どちらもプラスチック表面に接着する
-
どちらも培養が可能で、増殖する
しかし、細胞の機能や分化能力を調べることで、両者をしっかりと区別することができます。
MSC(Mesenchymal Stem Cell) は、骨髄・脂肪・臍帯・歯髄などに存在する幹細胞で、自己複製能、多分化能、免疫調節機能を持ちます。
一方で、線維芽細胞(Fibroblast) は、皮膚や結合組織に多く存在する細胞で、主にコラーゲンやエラスチンなどの細胞外マトリックスを分泌し、組織を維持する役割を担っています。線維芽細胞は、あくまで組織の構造維持に関与し、MSCのような幹細胞としての能力は持ちません。
MSCと線維芽細胞を正しく区別するためには、細胞のマーカーを調べる方法(フローサイトメトリー)や、分化能を確認する方法などが用いられます。
-
フローサイトメトリーでの識別
MSCと線維芽細胞は形態が似ているため、フローサイトメトリーを用いた細胞表面マーカー解析が識別に不可欠です。
MSCはCD73、CD90、CD105が陽性であり、CD34、CD45、CD14、HLA-DRが陰性であることが特徴です。
一方、線維芽細胞はVimentin、PDGFRα、TE-7、1B10が陽性で、MSC特有のマーカー(CD73、CD105)は低発現または陰性です。
形態だけでは両者の区別が難しく、組織由来の違いによって特徴が変わるため、陽性・陰性マーカーの両方を確認することで、より正確な識別が可能になります。
-
分化試験
MSCは、骨・軟骨・脂肪細胞へ分化できるため、実際に培養条件を変えて分化試験を行うことで、幹細胞の能力を持っているかどうかを判定することができます。
最後に
間葉系幹細胞(MSC)は、私たちの体の中で傷ついた組織を修復する力を持った、頼もしい細胞です。すでに実用化が進んでいるため、これからますます再生医療の現場で活躍していくでしょう。
次回は、間葉系幹細胞の治療応用について詳しくご紹介します!お楽しみに!