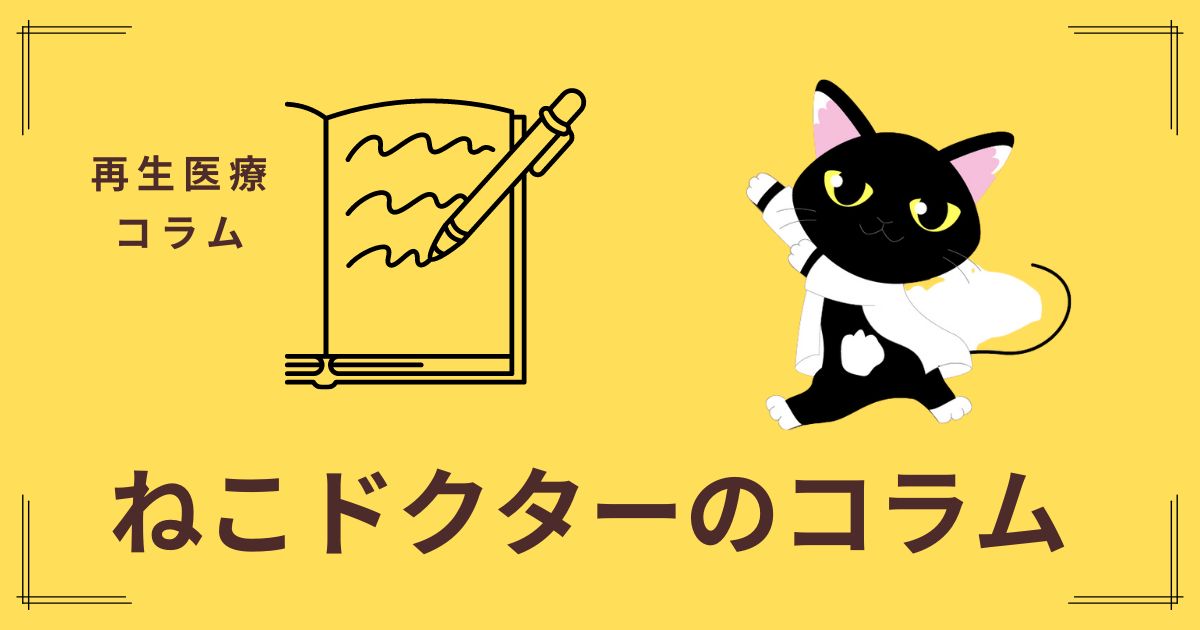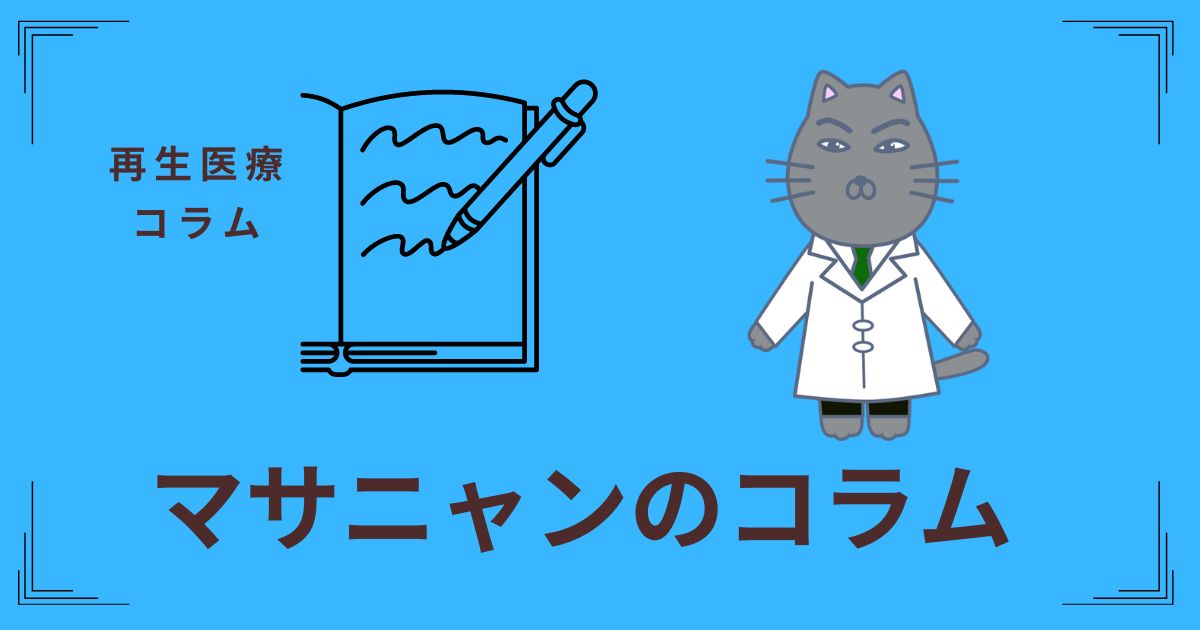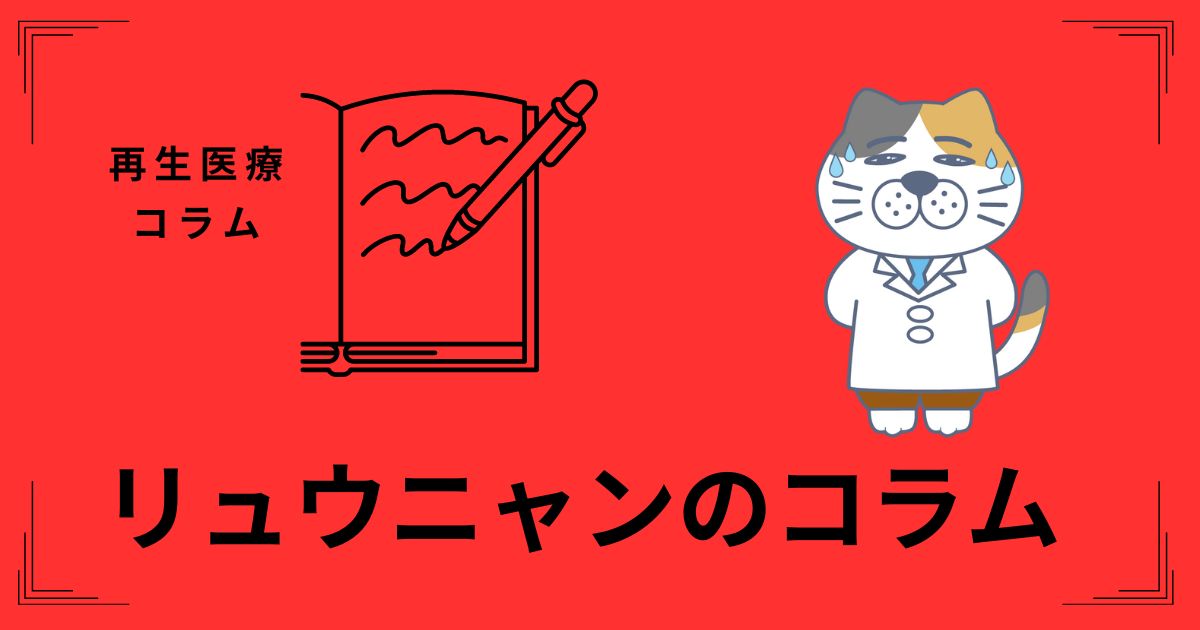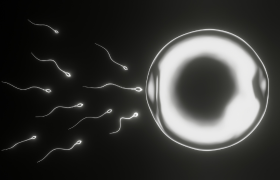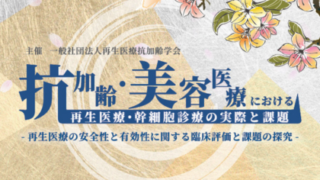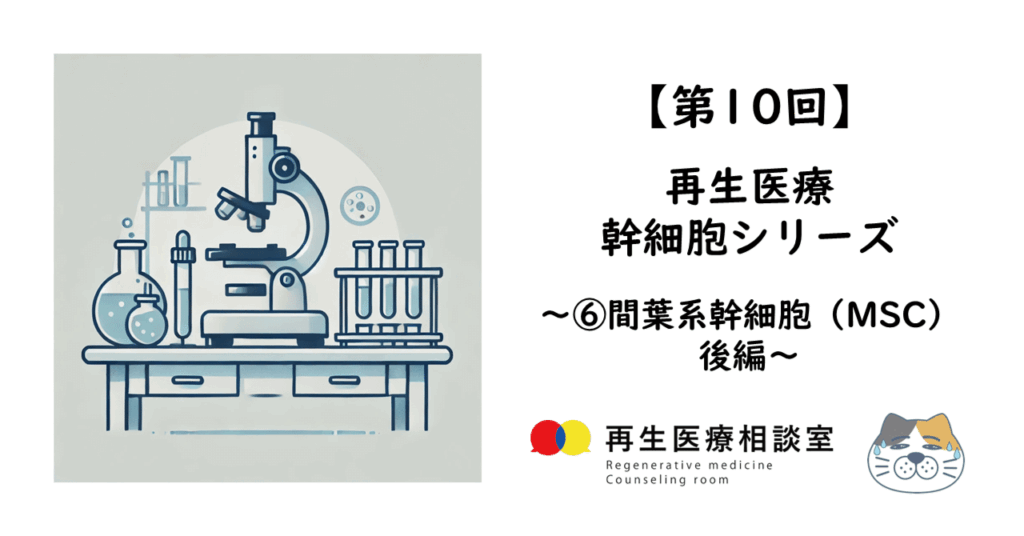
こんにちは!今回も「再生医療 幹細胞シリーズ」をお届けします。
前回は、成体幹細胞の中でも特に再生医療で注目されている「間葉系幹細胞(MSC)」について、その定義や由来、特徴などの基本情報をご紹介しました。
今回はその後編として、間葉系幹細胞がどのように治療に応用されているのか、実際の臨床でどう使われているのかについて詳しくお伝えしていきます。
- ES細胞やiPS細胞といった多能性幹細胞との違いは?
- どうして再生医療での実用化が進んでいるの?
- どんな病気に効果が期待されているの?
- 間葉系幹細胞の“いま”と“これから”を一緒に見ていきましょう!
- ぜひ最後までお楽しみください。
MSCが治療で注目される理由
間葉系幹細胞(MSC)は、骨、軟骨、脂肪などに分化する能力を持つだけでなく、損傷組織の修復に役立つさまざまな働きをします。
特に注目されているのが、
-
炎症を抑える
-
免疫のバランスを整える
-
損傷部位の修復を促進する
といった「細胞が出すシグナル(サイトカインや成長因子)」による間接的な治療効果です。
つまり、MSCは自らが細胞として置き換わるというよりも、「損傷した場所に行って、その場を整えて、体の修復力を引き出す」というような役割を担っているのです。これはパラクライン作用と言います。
MSC療法が幅広い疾患に効果を発揮すると考えられる背景には、そのパラクライン作用があります。
損傷や疾患により炎症が起きた組織にMSCを投与すると、MSCは傷んだ現場に集積し、炎症性サイトカイン環境を鎮静化して組織の再生に適した状態を整えます。
さらにMSCは血管新生や線維化抑制に寄与する因子も放出し、損傷組織への酸素・栄養供給を改善して治癒を後押しします。例えば肝細胞増殖因子(HGF)や血管内皮増殖因子(VEGF)などは血管再生を促進し、慢性炎症による組織の瘢痕化を抑える働きがあります。
関節疾患の研究では、MSC投与により軟骨そのものの再生はわずかでも炎症と疾患進行が顕著に抑制され、痛みや機能が改善することが示されました。
このようにMSCは「細胞そのもの」よりも「工場」としての機能で治癒を支える存在と言えます。
以上のようなパラクライン作用こそがMSC療法のカギであり、再生医療の切り札として世界的に期待が高まっています。
ES細胞・iPS細胞との違い
ES細胞やiPS細胞は、ほとんどすべての細胞に分化できる能力を持ちます(多能性)。一方で、
-
ES細胞は倫理的な問題や拒絶リスク
-
iPS細胞は腫瘍化リスクや高コストなどの課題があり、実用化にはまだ時間がかかっています。
これに対してMSCは、体の中に実際に存在している幹細胞で
-
採取や培養が比較的簡単
-
ES細胞に比べて倫理的な問題が少ない
-
腫瘍化や免疫拒絶反応のリスクが低いといった実用面での利点があり、すでに臨床の現場でも使われています。
MSCの応用領域と日本国内での現状
MSC療法は実に様々な疾患領域で研究・応用が進んでいます。ここでは主な領域ごとに、その臨床研究例や自由診療での利用状況、製品化の状況をまとめます。
脊髄損傷
脊髄損傷はMSC療法の中でも注目度が高い分野です。日本では自家骨髄MSCを用いた「ステミラック注」が2019年に条件・期限付き承認取得・保険適用されています。
ステミラック注は脊髄損傷患者自身の骨髄液から採取したMSCを培養して増やし、点滴静注する治療法で、受傷後できるだけ早期(おおむね31日以内)の患者を対象に行われ、麻痺など神経機能の改善効果が期待されています。世界的にも急性期脊髄損傷に対する初の幹細胞治療薬として注目され、国内では札幌医科大学附属病院が中心となって実施されています。
受傷後早期に患者自身のMSCを点滴投与することで、脊髄の炎症を抑制し神経細胞の二次障害を軽減、運動機能の回復を促す効果が期待されています。実際に試験では重度麻痺が一部改善した症例も報告され、現在も条件付き承認のもとデータ収集が続けられています。
一方、慢性期の脊髄損傷に対しては試行錯誤が続いています。脊髄損傷は神経系の再生という難題を含むため、iPS細胞由来の神経細胞移植など他のアプローチとの競争もありますが、MSCの持つ損傷抑制と環境改善効果はリハビリテーションと相まって回復を底上げできると期待されています。
脳血管障害(脳梗塞後遺症)
脳卒中(脳梗塞や脳出血)で後遺する半身麻痺や言語障害に対しても、MSC療法の研究が進んでいます。脳卒中では発症急性期の血栓除去や血圧管理後も、多くの患者に麻痺などの障害が残ります。MSCは慢性期の機能改善療法として期待されています。
自由診療では、脳梗塞後の後遺症改善を目的としたMSC点滴が一部クリニックで提供され、実際に受けた患者から「手足の動きが良くなった」という声も聞かれます。しかしプラセボ対照試験で明確な効果が示されたわけではなく、エビデンスはまだ蓄積途上です。
学術的には、MSCが脳内の炎症を鎮め、脳卒中後の自然回復力を底上げするという仮説が支持されています。研究者たちは神経栄養因子を高発現するMSCの開発などにも取り組んでいます。
変形性関節症
変形性膝関節症はMSC療法の代表的ターゲットの一つです。膝関節の軟骨がすり減り痛みや機能障害を生じる疾患で、高齢者に多く根本的治療が難しい分野です。
MSC療法では、患者自身の骨髄や脂肪からMSCを採取・培養し、関節腔内に注射することで、関節内の炎症を鎮め、組織の生存や修復を促す効果が期待されます。
日本でも、自家培養軟骨細胞シート(ジャック)による治療が保険適用となっていますが、これは外科的手法であり、MSCの注射療法とは異なります。現在、日本の自由診療では脂肪由来MSCの膝関節注射が広く行われており、痛みの軽減や歩行能力の改善を訴える患者も多いようです。ただし画像上の軟骨増生は投与後半年~1年では顕著でなく、症状改善は主に炎症緩和によるものと考えられています。
糖尿病やその合併症
糖尿病に対するMSC療法は、主に合併症の改善や自己免疫の調整を狙って研究されています。
1型糖尿病では免疫が膵島細胞を破壊してインスリン欠乏を起こしますが、MSCの免疫調整作用で自己免疫反応を鎮め、残存する膵β細胞の保護や再生を期待する試みがあります。また2型糖尿病でも、慢性炎症がインスリン抵抗性の背景にあることから、MSCの抗炎症作用で全身の代謝状態を改善する可能性が検討されています。
実際の臨床研究では、糖尿病性足潰瘍に対するMSC局所注射の試みや、重症虚血肢に対する血管新生目的のMSC移植などが行われ、一部で創傷治癒促進の報告があります。
自由診療では、まだ研究の途中ではありますが、実際の臨床現場では患者様からの良好なフィードバック(血糖改善等)も多く、今後のデータの蓄積が待たれています。
歯科領域(歯周病・歯槽骨の再生)
重度の歯周病で失われた骨や歯茎の再生、事故や加齢で痩せた歯槽骨の再建にMSCを活用する試みが始まっています。現在のところ、歯科領域のMSC療法は臨床研究段階のものが多く、一般の歯科医院で提供されている自由診療としては限定的です。
従来治療法としては人工骨材やエナメルマトリックス製剤、成長因子(FGF-2製剤など)を使っても限られた再生しか得られませんでしたが、新しいアプローチとして患者自身の脂肪から採取・培養したMSCを歯周組織欠損部に移植し、骨や歯周組織の再生を促す治療法が開発されています。大阪大学のグループは自己脂肪由来MSC移植による歯周組織再生を世界に先駆けて臨床研究で実施し、既に12症例で安全性と有効性を確認しました。
他の難病
-
難治性の肛門瘻
武田薬品の「アロフィセル」は、世界初の脂肪由来MSC製剤で、クローン病に伴う難治性肛門瘻を対象に、瘻孔周囲に同種MSCを局所注射して炎症を抑え、瘻孔閉鎖を促す新しい治療法。欧州で先行承認され、日本でも2021年に承認されました。
- 急性移植片対宿主病(GVHD)
「テムセルHS注」は、骨髄由来MSCの免疫調整作用を活かし、造血幹細胞移植後の急性GVHDに対して週2回点滴で免疫反応を抑える治療法。日本で2015年承認、保険適用済み。
- アルツハイマー病
アルツハイマー型認知症に対し、MSCの抗炎症・神経保護作用が神経細胞の生存を助け、脳環境を整え認知機能の低下抑制が期待されています。2018年日本の認定再生医療等委員会が軽度から中等度アルツハイマー病患者に対する再生医療提供計画を承認したことで、世界初のアルツハイマー病幹細胞治療の提供例となりました。
適応症はいずれも「慢性・難治性」で従来治療に限界のある疾患です。MSC療法はそうした領域で新たな治療選択肢となりつつあり、患者が実際に恩恵を受け始めています。
自由診療でのMSC治療
日本では再生医療安全性確保法の下、自由診療(保険外)に分類される再生医療も一定の条件下で実施が認められています。医師と患者の合意があれば、審査委員会による計画承認と厚労省への届け出を経て提供可能です。
この仕組みにより、国内では多数のクリニックがMSC療法を自由診療で提供しているのが実情です。例えば、自分の脂肪由来MSCを培養して静脈点滴する全身療法や、膝関節の痛みに対して膝関節内にMSCを注射する治療、さらには発毛や美容目的での局所MSC治療など、多岐にわたるメニューが民間クリニックで提供されています。
ただし、自由診療には以下のような課題もあります:
-
規制が不十分な場合があり、治療内容や基準が医療機関ごとに異なり、治療の品質や安全性が保証されないことがあります
-
エビデンス(効果の裏付け)がまだ十分に蓄積されていない治療もある
-
保険が使えないため費用が高額になりやすい
とはいえ、すべての自由診療が危険というわけではありません。なかには先進的な治療を受けることができる貴重な選択肢でもあり、信頼できる医療機関で治療の内容やリスクをよく理解したうえで検討すれば、適切な判断が可能です。情報をしっかり集め、自分に合った治療かどうかを見極めることが大切です。
海外におけるMSCの研究・臨床状況
海外でもMSC療法は幅広く研究・応用されていますが、その承認状況や規制は国によって異なるのが特徴です。
アメリカ
アメリカでは、FDA(食品医薬品局)の規制は非常に厳格で、現時点でMSC由来の細胞医薬品が正式承認された例はありません。ただし、再生医療先進国として臨床試験の数は膨大で、例えば慢性心不全へのMSC注入療法や、脊髄損傷・脳卒中後遺症への臨床試験が多数行われています。
ヨーロッパ
ヨーロッパでは、細胞治療製品は厳格なATMP(先進医療製品)規制下にあり、市販製品としては限られたものしか承認されていません。欧州発のMSC製品としては、膝骨関節炎や心臓病など特定の難病治療を対象にいくつか開発が進んでいますが、広く普及した例はまだ多くありません。
韓国
韓国では、世界初の同種脂肪由来MSCを用いた膝軟骨再生治療(カーティステム)が承認され、急性心筋梗塞に対する自家骨髄MSC治療や、ALS(筋萎縮性側索硬化症)に対する自家骨髄MSC製剤なども承認され、広く臨床応用されています。
総じて、韓国や日本は比較的早期にMSC製品を条件付きで実用化し、欧米は慎重な姿勢ながら着実にエビデンスを積み上げている、と言えます。
各国の規制の特徴として、日本は2014年施行の再生医療新法により一定の安全管理下で自由診療提供を許容しつつ、条件付き早期承認制度で有望品目を先行承認しています。韓国も条件付き承認や積極的な政府支援で実用化を推進。米国・欧州は無闇な市販化を避け、厳しい第III相試験データを要求する傾向です。
それぞれのアプローチに一長一短がありますが、世界的な潮流としてMSC療法は再生医療の主要な柱として確立しつつあります。
MSC治療の課題
間葉系幹細胞は非常に有望な細胞ですが、より広く安定して治療に使っていくためには、いくつか解決すべき課題もあります。
細胞品質の均一化
MSCは生きた細胞を使うため、ドナーの個人差や採取部位、培養手法によって増殖能や分泌因子プロファイルが異なり、細胞の質にバラつきが出やすいという特徴があります。
市販されているMSC製剤では、「細胞の生存率」や「特定のマーカーの発現」などの品質基準が設定されていますが、それでもロット間で多少の差が出てしまうのが現状です。どの製品でも安定した効果が出るような品質管理が今後さらに重要になります。
治療法の標準化
MSC療法は比較的新しい分野のため、「どの病気に、どうやって、何回、どれくらいの量を投与すればいいのか」といった標準的な治療法がまだ確立されていません。
現場では、医師や研究者の経験をもとに「この疾患にはこの方法が効きそう」といった実績が蓄積しつつありますが、それを裏付ける大規模な比較試験やガイドラインはまだ不足しています。
また、MSCがどのように効果を発揮しているのかというメカニズム(作用機序)も完全には解明されておらず、「どの分泌因子が本当に効いているのか?」という点も今後の研究課題です。
ガイドラインや法規制の整備
再生医療は急速に進歩している一方で、制度面での対応が追いついていない部分もあります。
たとえば、日本では一定の条件を満たせば自由診療としてMSC療法を提供することが可能ですが、その結果として、科学的根拠が十分でない治療が行われているケースも見受けられます。
また、患者さん自身が正しい情報を得にくい状況も問題視されています。クリニックごとに治療内容が異なり、費用も高額になることがあるため、しっかりとしたガイドラインや現場に相応しい法規制が必要とされています。
今後の展望
MSC療法は今後ますます発展が期待される領域です。すでに様々な治療応用が始まっていますが、将来的には、より多くの疾患に対して新たな希望をもたらす可能性があります。現在試みられているもの以外にも自己免疫疾患や難治性炎症疾患への展開が考えられ、心筋梗塞後心不全にも有望です。臓器固有の細胞(心筋細胞や神経細胞)を補充するほどの再生は難しくとも、MSCで臓器の機能低下を防げれば大きな価値があります。
技術面では、これまで細胞の培養は、フラスコ等を使った“平面培養”が主流でしたが、近年では三次元培養やバイオリアクターによる大量培養の技術が発展しています。これにより、より安定した品質でMSCを大量に製造できるようになり、治療コストの低減や普及拡大にもつながっていくと期待されています。
治療戦略の進化という点では、MSCを単独で使うだけでなく、他の治療法と組み合わせて使う「複合的なアプローチ」も進んでいくと考えられています。例えばMSCとバイオマテリアルの併用(傷害部位に留まるようハイドロゲルと混合して注入する)、遺伝子導入MSC(特定の成長因子や酵素を過剰発現させたMSCで治療効果を高める)などが開発されつつあり、治療の幅がどんどん広がってきています。また、将来的にはAI技術を使って、患者の状態に応じた最適なMSC製剤を選ぶパーソナライズド再生医療も現実になるかもしれません。
そして何より大切なのが、臨床研究や自由診療を通じて蓄積された実績をもとに、科学的根拠を積み上げていくことです。MSC療法が真に社会に浸透するためにはエビデンスの蓄積と周知が不可欠です。同時に、過大な宣伝による誤解を避け、患者に正確な情報を届けることも大切です。
将来的には、より確実なエビデンスに基づいた「標準治療」としてMSCが普及し、より多くの患者さんが恩恵を受けられるようになることが期待されています。
最後に
MSC療法は「夢の若返り薬」ではなく、科学に基づく新しい治療手段の一つです。現時点で万能ではないものの、着実に進歩しています。その可能性と限界を正しく理解し、課題を克服していくことで、多くの疾患で患者さんの生活の質を向上させる真の再生医療になっていくでしょう。今後の研究と臨床応用の展開に期待が寄せられています。
次回は、間葉系幹細胞と同じく成体幹細胞に分類される「造血幹細胞」についてご紹介します。
どうぞお楽しみに!