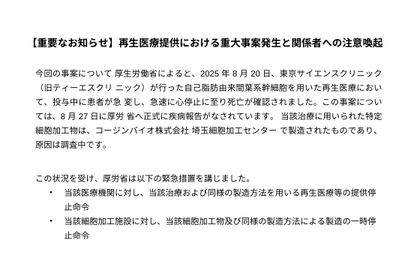Basic knowledge
再生医療の基礎知識
再生医療の基礎知識
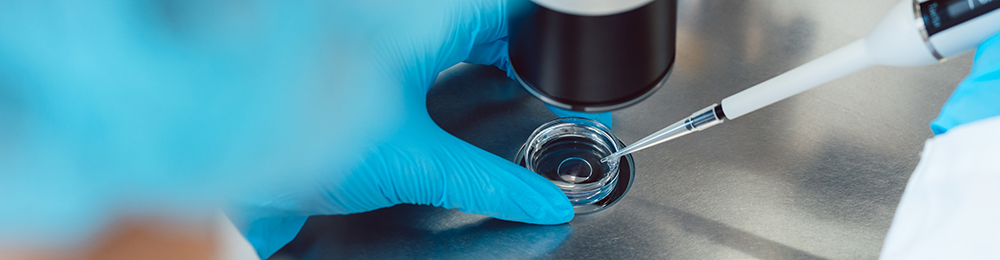
再生医療の基礎知識
幹細胞って何?
幹細胞とは
わたしたちはみな、自分たちのからだのなかに、皮膚や血液のように、ひとつひとつの細胞の寿命が短く、絶えず入れ替わり続ける組織を保つために、失われた細胞を再び生み出して補充する能力を持った細胞を持っています。こうした能力を持つ細胞が「幹細胞」です。幹細胞と呼ばれるには、次の二つの能力が不可欠です。一つは、皮膚、赤血球、血小板など、わたしたちのからだをつくるさまざまな細胞を作り出す能力(分化能)、もう一つは自分とまったく同じ能力を持った細胞に分裂することができるという能力(自己複製能)です。
幹細胞は大きく2種類に分けられます。一つは、皮膚や血液のように、きまった組織や臓器で、消えた細胞のかわりを造り続けている幹細胞です。このタイプの幹細胞は「組織幹細胞」と呼ばれています。組織幹細胞は何にでもなれるのではなく、血をつくる造血幹細胞であれば血液系の細胞、神経系をつくる神経幹細胞であれば神経系の細胞のみ、というように、役目が決まっています。もう一つは、ES細胞(胚性幹細胞)のように、わたしたちのからだの細胞であれば、どのような細胞でも作り出すことのできる「多能性幹細胞」(Pluripotent Stem Cell)です。つまり、多能性幹細胞は、わたしたちのからだのなかにある様々な組織幹細胞も作り出すことができるのです。iPS細胞(induced Pluripotent Stem Cell)とは、普通の細胞をもとにして人工的につくった「多能性幹細胞」のことなのです。
こうした「幹細胞」の性質を利用して、細胞そのものを薬として怪我や病気を治す「再生医療」という新しい治療法の研究や、体内の細胞の状態をからだの外で再現して病気のしくみを調べる研究が進んでいます。
幹細胞は大きく2種類に分けられます。一つは、皮膚や血液のように、きまった組織や臓器で、消えた細胞のかわりを造り続けている幹細胞です。このタイプの幹細胞は「組織幹細胞」と呼ばれています。組織幹細胞は何にでもなれるのではなく、血をつくる造血幹細胞であれば血液系の細胞、神経系をつくる神経幹細胞であれば神経系の細胞のみ、というように、役目が決まっています。もう一つは、ES細胞(胚性幹細胞)のように、わたしたちのからだの細胞であれば、どのような細胞でも作り出すことのできる「多能性幹細胞」(Pluripotent Stem Cell)です。つまり、多能性幹細胞は、わたしたちのからだのなかにある様々な組織幹細胞も作り出すことができるのです。iPS細胞(induced Pluripotent Stem Cell)とは、普通の細胞をもとにして人工的につくった「多能性幹細胞」のことなのです。
こうした「幹細胞」の性質を利用して、細胞そのものを薬として怪我や病気を治す「再生医療」という新しい治療法の研究や、体内の細胞の状態をからだの外で再現して病気のしくみを調べる研究が進んでいます。
受精卵と細胞運命
わたしたちのからだは60兆個〜100兆個の細胞からできています。これらの細胞をさかのぼると、みな一つの同じ細胞、受精卵にたどりつきます。わたしたちのからだは、この受精卵が分裂を繰り返すことによって出来上がるのです。
からだを構成する細胞は、生殖細胞と体細胞の2種類に大別されます。生殖細胞は卵子と精子になる細胞で、親の遺伝子を次世代に伝えるための特別な細胞です。生殖細胞以外の細胞は体細胞と呼ばれ、皮膚や血管、肝臓などの器官や組織を構成しています。
からだを構成する細胞の始まりである受精卵は卵子と精子が融合してできる一つの細胞です。精子と卵子は、減数分裂という特別な分裂を経てつくられ、通常の細胞の半分の染色体しか持っていません。卵子と精子が融合して受精卵になると、染色体の数は普通の細胞と同じ数となります。
受精が完了すると、発生がはじまります。受精卵は、同じDNA配列を複製しながら分裂を繰り返します。分裂を繰り返すにつれて、均一な細胞の集団が不均一な細胞の集団へと変わり、「胚」へと移行します。そして特定の細胞集団に含まれている細胞が将来どんな細胞になるのかという細胞の「運命」が徐々に決まっていくのです。
細胞の運命は、おおまかに3つに分かれていきます。
将来神経系や皮膚になる外胚葉
筋肉や血管になる中胚葉
肝臓や膵臓などの内臓器官になる内胚葉の3つです。
3つに分かれた細胞は、例えば外胚葉においては感覚器になるか、神経系になるか、皮膚になるか、神経においてはどのような種類の神経になるか・・・というようにさらに細かく分かれていきます。発生においては、運命はいったん決定されると大きく変更されることはないといわれています。すべての細胞は1つの受精卵から受け継いだ同じDNA配列を持っていますが、それぞれの細胞で、使われている遺伝子と使われていない遺伝子の組み合わせが異なるため形や機能の異なる細胞になるのです。
からだを構成する細胞は、生殖細胞と体細胞の2種類に大別されます。生殖細胞は卵子と精子になる細胞で、親の遺伝子を次世代に伝えるための特別な細胞です。生殖細胞以外の細胞は体細胞と呼ばれ、皮膚や血管、肝臓などの器官や組織を構成しています。
からだを構成する細胞の始まりである受精卵は卵子と精子が融合してできる一つの細胞です。精子と卵子は、減数分裂という特別な分裂を経てつくられ、通常の細胞の半分の染色体しか持っていません。卵子と精子が融合して受精卵になると、染色体の数は普通の細胞と同じ数となります。
受精が完了すると、発生がはじまります。受精卵は、同じDNA配列を複製しながら分裂を繰り返します。分裂を繰り返すにつれて、均一な細胞の集団が不均一な細胞の集団へと変わり、「胚」へと移行します。そして特定の細胞集団に含まれている細胞が将来どんな細胞になるのかという細胞の「運命」が徐々に決まっていくのです。
細胞の運命は、おおまかに3つに分かれていきます。
将来神経系や皮膚になる外胚葉
筋肉や血管になる中胚葉
肝臓や膵臓などの内臓器官になる内胚葉の3つです。
3つに分かれた細胞は、例えば外胚葉においては感覚器になるか、神経系になるか、皮膚になるか、神経においてはどのような種類の神経になるか・・・というようにさらに細かく分かれていきます。発生においては、運命はいったん決定されると大きく変更されることはないといわれています。すべての細胞は1つの受精卵から受け継いだ同じDNA配列を持っていますが、それぞれの細胞で、使われている遺伝子と使われていない遺伝子の組み合わせが異なるため形や機能の異なる細胞になるのです。
遺伝子のオン・オフ機構
細胞は分裂するとき、DNA塩基配列をそのままコピーしますので、ごく少数の例外はあるものの、すべての細胞は核のなかに同じ配列のゲノムを持っているといえます。このゲノムにはからだ全体の設計図が描かれていますから、持っている遺伝子がすべて書き込まれています。したがって、個々の細胞でこの設計図が同じように読まれてしまうと、細胞が皆同じ性質になってしまい、からだを作れません。そこで、個々の細胞の運命が分かれるように、その細胞にふさわしい遺伝子の機能だけが現れるよう「遺伝子のオン・オフ」を制御する仕組みが存在しています。
この遺伝子のオン、オフを核のなかのDNAもしくはヒストン上の化学的な修飾として固定化し、細胞が分裂してゲノムを受け継いでいくときにも伝えていく機構が、「エピジェネティック(epi-genetic)機構」と呼ばれるものです。この機構によって、DNA塩基配列という設計図の変更を伴わずに、細胞は安定して、その運命を維持したり、子孫細胞に伝えています。
この遺伝子のオン、オフを核のなかのDNAもしくはヒストン上の化学的な修飾として固定化し、細胞が分裂してゲノムを受け継いでいくときにも伝えていく機構が、「エピジェネティック(epi-genetic)機構」と呼ばれるものです。この機構によって、DNA塩基配列という設計図の変更を伴わずに、細胞は安定して、その運命を維持したり、子孫細胞に伝えています。
ガードン教授とクローン
受精卵からはじまった細胞が分化していく過程で、遺伝子のオン・オフが固定化されます。この固定化の選択は、細胞が分裂するときも引き継がれていきます。この固定化が緩くて細胞の運命が途中で変わってしまっては、適切な細胞、ひいてはからだをつくれなくなるため、厳重に固定化された大人の細胞の運命を巻きもどすことは不可能と考えられていました。しかし、この定説をくつがえしたのが、山中伸弥教授とともにノーベル賞を受賞したジョン・B・ガードン教授でした。
ガードン教授は、おたまじゃくしの腸にある細胞から核を抜き出して、除核した卵子に移植しました。すると、通常の受精と同じく、おたまじゃくしが生まれることを発見したのです。しかし、「おたまじゃくしのような若い幼生の細胞核だからではないか」という批判がありました。そこで、1975年、ガードン教授は大人のカエルの皮膚細胞から採取した核を2段階にわたって卵子に移植しました。その結果、世界で初めて、大人の細胞核から「クローン動物」を生み出すことに成功しました。つまり、ガードン教授は「再び受精卵となる」という能力の一端は、卵子が持っているのではないか、ということを示したのです。
しかし、こうしたクローンの作成は、カエルだからできることで、ほ乳類では難しい、という意見が根強くありました。ところが1997年にイギリスのロスリン研究所から発表されたクローン羊ドリーの誕生によって、ほ乳類でも「核移植によるクローン個体」が作れることが証明されました。ドリーは、分化してしまっていた大人の提供羊の細胞とまったく同じ遺伝情報を持って生まれてきました。ほ乳類でも、卵子のなかに「体細胞を全能性胚細胞に初期化する能力」があることが証明されたのです。ただ、依然として体細胞クローンの成功率は低く、無事にうまれても、初期化が不完全なことに起因する先天的な疾病を発症する可能性が高いことがわかっています。
ガードン教授は、おたまじゃくしの腸にある細胞から核を抜き出して、除核した卵子に移植しました。すると、通常の受精と同じく、おたまじゃくしが生まれることを発見したのです。しかし、「おたまじゃくしのような若い幼生の細胞核だからではないか」という批判がありました。そこで、1975年、ガードン教授は大人のカエルの皮膚細胞から採取した核を2段階にわたって卵子に移植しました。その結果、世界で初めて、大人の細胞核から「クローン動物」を生み出すことに成功しました。つまり、ガードン教授は「再び受精卵となる」という能力の一端は、卵子が持っているのではないか、ということを示したのです。
しかし、こうしたクローンの作成は、カエルだからできることで、ほ乳類では難しい、という意見が根強くありました。ところが1997年にイギリスのロスリン研究所から発表されたクローン羊ドリーの誕生によって、ほ乳類でも「核移植によるクローン個体」が作れることが証明されました。ドリーは、分化してしまっていた大人の提供羊の細胞とまったく同じ遺伝情報を持って生まれてきました。ほ乳類でも、卵子のなかに「体細胞を全能性胚細胞に初期化する能力」があることが証明されたのです。ただ、依然として体細胞クローンの成功率は低く、無事にうまれても、初期化が不完全なことに起因する先天的な疾病を発症する可能性が高いことがわかっています。
全身に幹細胞を持つプラナリア
プラナリアは、川などに生息する体長1~3cmほどの生き物です。三角形の頭に小さな目が2つ並んでついていて、平べったく細長い体をゆらしながら、水中をスーッと這うように移動する生物です。
プラナリアは、環境によって無性生殖と有性生殖とを切り替えて増殖します。無性生殖では、プラナリアは自身の体を2つに切って殖えます(自切)。自切したプラナリアは片方には頭が、もう片方にはしっぽがない状態です。ところが数日経つと、しっぽはもちろん脳や目などの組織を再生し、完全な2匹のプラナリアになります。プラナリアは未分化な幹細胞が全身に存在しており、体の位置情報に従い幹細胞の遺伝子を目的の組織に分化するよう操作して、失った体を正しく再生することができるのです。
プラナリアの再生は自切だけでなく、人工的に切断した時にも行われます。プラナリアを2つに切断すると完全な2匹のプラナリアに、3つに切断すると完全な3匹のプラナリアになります。こうしたプラナリアの再生の謎は、1900年ころから研究されていましたが、再生の決定的な要因はなかなか見つかりませんでした。100年以上たった現在、幹細胞からどのようにして器官や体を構築していくのか、体の極性や、位置情報を作るメカニズムを解き明かす研究が進められ、ついにプラナリアの再生の仕組みが解明されました。
PubMed
失われた体の一部や機能不全となった組織や器官を再生し機能を回復する医療、すなわち再生医療の実現の糸口をつかむため、小さなプラナリアの研究は分子レベルと態様を変え、新たな意義を持ちつつあります。
プラナリアは、環境によって無性生殖と有性生殖とを切り替えて増殖します。無性生殖では、プラナリアは自身の体を2つに切って殖えます(自切)。自切したプラナリアは片方には頭が、もう片方にはしっぽがない状態です。ところが数日経つと、しっぽはもちろん脳や目などの組織を再生し、完全な2匹のプラナリアになります。プラナリアは未分化な幹細胞が全身に存在しており、体の位置情報に従い幹細胞の遺伝子を目的の組織に分化するよう操作して、失った体を正しく再生することができるのです。
プラナリアの再生は自切だけでなく、人工的に切断した時にも行われます。プラナリアを2つに切断すると完全な2匹のプラナリアに、3つに切断すると完全な3匹のプラナリアになります。こうしたプラナリアの再生の謎は、1900年ころから研究されていましたが、再生の決定的な要因はなかなか見つかりませんでした。100年以上たった現在、幹細胞からどのようにして器官や体を構築していくのか、体の極性や、位置情報を作るメカニズムを解き明かす研究が進められ、ついにプラナリアの再生の仕組みが解明されました。
PubMed
失われた体の一部や機能不全となった組織や器官を再生し機能を回復する医療、すなわち再生医療の実現の糸口をつかむため、小さなプラナリアの研究は分子レベルと態様を変え、新たな意義を持ちつつあります。
イモリの再生
「トカゲのしっぽ切り」という言葉があるように、トカゲは危険を感じたり、敵から逃げる際に、自分のしっぽを切って逃げてしまいます。しっぽは切れてもまた生えてきます。
トカゲによく似たイモリは、しっぽはもちろん、足、あご、眼のレンズなどを失っても完全に再生することができます。
イモリの足を切断すると、周囲から表皮細胞が移動してきて1日足らずで切断面を覆います。表皮で覆われた傷口は、かさぶたや引き攣れなどの傷跡を起こさず滑らかな組織となります。そして、「再生芽」と呼ばれる未分化な細胞の塊を作ります。この再生芽にある未分化細胞は、皮膚の真皮の幹細胞(線維芽細胞)が脱分化したものです。この未分化細胞は、表皮や軟骨、腱などに再分化して、元と同じ組織を形づくるよう増殖します。 真皮の幹細胞がどのようにして脱分化するのかは完全に解明されていませんが、切断された末梢神経組織から分泌される数種のタンパク質の発現が四肢再生に関わることがわかってきました。
また、イモリの眼からレンズ(水晶体)を取り除くと、全く別の組織である上方の虹彩色素上皮からレンズを再生します。虹彩色素上皮はメラニン色素を多く含み真っ黒な組織です。この真っ黒な細胞が脱分化し、透明なレンズの細胞を再生するのです。
イモリは心臓も再生できます。イモリの心室を半分近く切除しても再生するという報告もあります。イモリの心臓にある心筋細胞が脱分化して増殖し、組織を再生している可能性があり、研究が進められています。
このようなイモリの再生は、種々の遺伝子の発現調節で行われています。 イモリの組織再生に関わる遺伝子を特定し、わたしたちヒトの遺伝子と比べることが、ヒトの組織の再生への足がかりとなるかもしれません。
トカゲによく似たイモリは、しっぽはもちろん、足、あご、眼のレンズなどを失っても完全に再生することができます。
イモリの足を切断すると、周囲から表皮細胞が移動してきて1日足らずで切断面を覆います。表皮で覆われた傷口は、かさぶたや引き攣れなどの傷跡を起こさず滑らかな組織となります。そして、「再生芽」と呼ばれる未分化な細胞の塊を作ります。この再生芽にある未分化細胞は、皮膚の真皮の幹細胞(線維芽細胞)が脱分化したものです。この未分化細胞は、表皮や軟骨、腱などに再分化して、元と同じ組織を形づくるよう増殖します。 真皮の幹細胞がどのようにして脱分化するのかは完全に解明されていませんが、切断された末梢神経組織から分泌される数種のタンパク質の発現が四肢再生に関わることがわかってきました。
また、イモリの眼からレンズ(水晶体)を取り除くと、全く別の組織である上方の虹彩色素上皮からレンズを再生します。虹彩色素上皮はメラニン色素を多く含み真っ黒な組織です。この真っ黒な細胞が脱分化し、透明なレンズの細胞を再生するのです。
イモリは心臓も再生できます。イモリの心室を半分近く切除しても再生するという報告もあります。イモリの心臓にある心筋細胞が脱分化して増殖し、組織を再生している可能性があり、研究が進められています。
このようなイモリの再生は、種々の遺伝子の発現調節で行われています。 イモリの組織再生に関わる遺伝子を特定し、わたしたちヒトの遺伝子と比べることが、ヒトの組織の再生への足がかりとなるかもしれません。
初期化とは何か
「初期化」とは、細胞がそれまでに継承・蓄積してきた厳重な固定化=エピジェネティックな標識=を消去・再構成し、受精卵並みの分化能を取り戻すことで、「リプログラミング」という言い方もします。
山中教授は、それまで卵子を使ったクローン技術が可能にしてきた「初期化」という現象を、卵子も使わず、たった4つの遺伝子を細胞に導入することにより再現できることを、2006年マウスで、2007年にはヒトで示しました。山中教授は、体の細胞を初期化するという、将来の医療に大きな変革をもたらす新技術を生み出しただけでなく、「初期化=生命の出発点への巻き戻し」という生物学上の根源的な謎の正体に初めて近づいたのでした。
山中教授は、それまで卵子を使ったクローン技術が可能にしてきた「初期化」という現象を、卵子も使わず、たった4つの遺伝子を細胞に導入することにより再現できることを、2006年マウスで、2007年にはヒトで示しました。山中教授は、体の細胞を初期化するという、将来の医療に大きな変革をもたらす新技術を生み出しただけでなく、「初期化=生命の出発点への巻き戻し」という生物学上の根源的な謎の正体に初めて近づいたのでした。
幹細胞の種類
多能性幹細胞の種類
わたしたちのからだの細胞であれば、どのような細胞でも作り出すことのできる「多能性幹細胞(Pluripotent Stem Cell)」。これにはいくつかの種類があります。
ES細胞(胚性幹細胞:Embryonic Stem Cell)
胚は、受精卵が数回分裂し、100個ほどの細胞のかたまりとなったものです。この胚の内側にある細胞を取り出して、培養したものがES細胞です。ES細胞は他人の受精卵から作られた細胞であるため。移植すると拒絶反応がおきてしまう問題があります。また、生命の源である胚をこわして作るという倫理問題を含んでいます。
ES細胞(胚性幹細胞:Embryonic Stem Cell)
ntES細胞 (nuclear transfer Embryonic Stem Cell)
受精前の卵子から核を取り出し、皮膚など他の体細胞の核を移植して胚(クローン胚)を作り、胚の内側の細胞を取り出して培養したものをntES細胞といいます。ntES細胞は、患者自身の体細胞の核を持つため、拒絶反応はおきないと考えられています。ただし、卵子の提供を必要とするという問題があります。
iPS細胞(人工多能性幹細胞:induced Pluripotent Stem Cell)
皮膚などのからだのなかにある細胞に、リプログラミング因子と呼ばれている特定の因子群を導入すると、細胞がES細胞と同じくらい若返り、多能性を持ちます。このように人工的に作った多能性幹細胞のことをiPS細胞といいます。世界ではじめて作製した山中教授によって名付けられました。
その後、より安全で高品質のiPS細胞を作製するために様々な研究が進められています。iPS細胞は胚の滅失に関わる倫理問題もないうえ、患者自身の体細胞から作り出せば、拒絶反応の心配もないと考えられています。
iPS細胞(人工多能性幹細胞:induced Pluripotent Stem Cell)
ES細胞(胚性幹細胞:Embryonic Stem Cell)
その後、より安全で高品質のiPS細胞を作製するために様々な研究が進められています。iPS細胞は胚の滅失に関わる倫理問題もないうえ、患者自身の体細胞から作り出せば、拒絶反応の心配もないと考えられています。
iPS細胞(人工多能性幹細胞:induced Pluripotent Stem Cell)
ES細胞
京都大学の山中教授らがヒトiPS細胞の樹立を発表するまで、再生医療研究のもっとも中心的な存在として注目された細胞がES細胞です。
ESとは「Embryonic Stem Cell」の略で日本語で「胚性幹細胞」、つまり胚の内部細胞塊を用いてつくられた幹細胞です。そのために「万能細胞」と呼ばれることもあります。1981年にイギリスのエヴァンスがマウスES細胞を樹立したのがそのはじまりです。
ES細胞は発生初期の胚の細胞からつくられるため、受精卵に非常に近い能力を持っていて、私たちのからだを構成するあらゆる細胞へと変わることができます。ES細胞は、適切な環境さえ整えれば半永久的に維持することができるといわれています。この維持培地から、神経や血液などを培養する条件に近い環境へ移すと、その環境に応じてさまざまな細胞に分化していくこともわかりました。
マウスでの成功を受けて、さまざまな動物のES細胞が樹立され、1998年にはアメリカのトムソンらがついにヒトでもES細胞の樹立を成功させました。ES細胞は半永久的に維持でき、目的の細胞へと分化させることができることから、再生医療のソースとして大きな期待が集まりました。しかし、ES細胞から細胞や臓器をつくることができたとしても、それは移植される患者さんにとっては「他者」の細胞であるために、臓器移植と同じように拒絶反応の対象となってしまいます。
加えて、「胚」を破壊しなければES細胞を得ることができません。「ES細胞のもととなる胚は、不妊治療の際に不要になった「余剰胚」を、提供者にきちんと同意をとって作られています。しかし「胚」を用いるということからES細胞研究に対して違和感を持つ人も少なくなく、再生医療への応用も日本では長年禁止されていましたが、政府は、今後あらたに作成するES細胞については、再生医療に用いることを可能とする体制の整備をはじめています。
ESとは「Embryonic Stem Cell」の略で日本語で「胚性幹細胞」、つまり胚の内部細胞塊を用いてつくられた幹細胞です。そのために「万能細胞」と呼ばれることもあります。1981年にイギリスのエヴァンスがマウスES細胞を樹立したのがそのはじまりです。
ES細胞は発生初期の胚の細胞からつくられるため、受精卵に非常に近い能力を持っていて、私たちのからだを構成するあらゆる細胞へと変わることができます。ES細胞は、適切な環境さえ整えれば半永久的に維持することができるといわれています。この維持培地から、神経や血液などを培養する条件に近い環境へ移すと、その環境に応じてさまざまな細胞に分化していくこともわかりました。
マウスでの成功を受けて、さまざまな動物のES細胞が樹立され、1998年にはアメリカのトムソンらがついにヒトでもES細胞の樹立を成功させました。ES細胞は半永久的に維持でき、目的の細胞へと分化させることができることから、再生医療のソースとして大きな期待が集まりました。しかし、ES細胞から細胞や臓器をつくることができたとしても、それは移植される患者さんにとっては「他者」の細胞であるために、臓器移植と同じように拒絶反応の対象となってしまいます。
加えて、「胚」を破壊しなければES細胞を得ることができません。「ES細胞のもととなる胚は、不妊治療の際に不要になった「余剰胚」を、提供者にきちんと同意をとって作られています。しかし「胚」を用いるということからES細胞研究に対して違和感を持つ人も少なくなく、再生医療への応用も日本では長年禁止されていましたが、政府は、今後あらたに作成するES細胞については、再生医療に用いることを可能とする体制の整備をはじめています。
iPS細胞
ES細胞がいろいろな問題をかかえるなか、京都大学の山中伸弥教授によって報告されたのがiPS細胞でした。私たちの体の細胞は全てたったひとつの受精卵に由来しており、同一のゲノムを共通に持っていますが、それぞれの細胞では必要な遺伝子以外は情報が読まれないようにゲノムにカギがかけられています。このため、血液が皮膚になったり、皮膚が心筋になることはありません。
これまで細胞核を未受精卵へと移植するクローン作成技術やES細胞の融合実験から、卵子やES細胞にゲノムにかけられたカギをはずす「初期化」の能力があることが知られていました。そこで、山中教授らは、公開データベース情報にもとづいてES細胞や生殖細胞に特異的に発現する遺伝子を絞り込み、遺伝子24個のセットをマウス線維芽細胞に組み込みました。その結果、ES細胞と同等まで初期化された細胞を樹立することに成功しました。これが人工多能性幹細胞(Induced Pluripotent Stem Cell)、iPS細胞です。さらに、この24個の遺伝子から必須の遺伝子を絞りこむ実験を行い、「Yamanaka Factor」と呼ばれている4遺伝子のセットにまで絞り込みました。
その後、樹立効率を上げるための導入法、別の因子の組み合わせでiPS細胞を樹立するなど、様々なiPS細胞樹立方法が開発され、より再生医療に適した方法が何かが検討されています。現在は、いよいよ臨床研究が始まろうとしているiPS細胞の品質管理(樹立方法を含む)について、国、研究機関、医療機関が綿密に協議している段階です。SKIPでは、iPS細胞を用いた臨床研究の進捗状況について、リスク&ベネフィットを含め、できるかぎり正確にお伝えしていきたいと考えています。
これまで細胞核を未受精卵へと移植するクローン作成技術やES細胞の融合実験から、卵子やES細胞にゲノムにかけられたカギをはずす「初期化」の能力があることが知られていました。そこで、山中教授らは、公開データベース情報にもとづいてES細胞や生殖細胞に特異的に発現する遺伝子を絞り込み、遺伝子24個のセットをマウス線維芽細胞に組み込みました。その結果、ES細胞と同等まで初期化された細胞を樹立することに成功しました。これが人工多能性幹細胞(Induced Pluripotent Stem Cell)、iPS細胞です。さらに、この24個の遺伝子から必須の遺伝子を絞りこむ実験を行い、「Yamanaka Factor」と呼ばれている4遺伝子のセットにまで絞り込みました。
その後、樹立効率を上げるための導入法、別の因子の組み合わせでiPS細胞を樹立するなど、様々なiPS細胞樹立方法が開発され、より再生医療に適した方法が何かが検討されています。現在は、いよいよ臨床研究が始まろうとしているiPS細胞の品質管理(樹立方法を含む)について、国、研究機関、医療機関が綿密に協議している段階です。SKIPでは、iPS細胞を用いた臨床研究の進捗状況について、リスク&ベネフィットを含め、できるかぎり正確にお伝えしていきたいと考えています。
疾患特異的iPS細胞
患者さんの皮膚や血液など、患者さん由来の組織からつくるiPS細胞を特に「疾患特異的iPS細胞」といいます。疾患特異的iPS細胞は患者さんの遺伝情報(病気を発症させる遺伝子も含む)を保有しているため、その病態を培養皿の中で再現することが可能となります。そのため、希少疾患や神経難病など疾患の原因遺伝子が明確ではあるが患者数の少ない疾患、病変部位が脳内などサンプル採取の困難な疾患、もしくは病気の発生や進行が全くわかっていない疾患に対して大きな力を発揮します。
中でも、神経難病のひとつである神経変性疾患は、何らかの要因から神経細胞が徐々に変性しその機能を失う病気で、神経細胞が新たに生まれてくることはほとんどないため、病気が進行しその機能を失う前に治療を行うことが重要になります。医療の進歩により病態初期の兆候をとらえる技術は発展しつつありますが、その精度はいまだ充分でなく、根本的な治療法開発にはもっと早い段階での病態検出が必須となります。疾患特異的iPS細胞では、生まれたばかりの神経細胞を作製すること、病態が進行する様子を観察することが可能となり、従来の技術と比較して早期の状態で病態マーカーの検出が可能となることが期待されています。iPS細胞のこのような性質を活用した病態マーカーの探索はすでに実施されており、疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明や新薬創出、新規治療法開発と組み合わせることで神経変性疾患の根本的な治療法開発が進められています。
また、疾患特異的iPS細胞の老化を意図的に促進させ、より早く病気の兆しを観察する方法も研究されており、個別化医療や先制医療(将来かかりそうな病気を予測して予防的な治療を行う)に対するiPS細胞技術の応用も期待されています。
中でも、神経難病のひとつである神経変性疾患は、何らかの要因から神経細胞が徐々に変性しその機能を失う病気で、神経細胞が新たに生まれてくることはほとんどないため、病気が進行しその機能を失う前に治療を行うことが重要になります。医療の進歩により病態初期の兆候をとらえる技術は発展しつつありますが、その精度はいまだ充分でなく、根本的な治療法開発にはもっと早い段階での病態検出が必須となります。疾患特異的iPS細胞では、生まれたばかりの神経細胞を作製すること、病態が進行する様子を観察することが可能となり、従来の技術と比較して早期の状態で病態マーカーの検出が可能となることが期待されています。iPS細胞のこのような性質を活用した病態マーカーの探索はすでに実施されており、疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明や新薬創出、新規治療法開発と組み合わせることで神経変性疾患の根本的な治療法開発が進められています。
また、疾患特異的iPS細胞の老化を意図的に促進させ、より早く病気の兆しを観察する方法も研究されており、個別化医療や先制医療(将来かかりそうな病気を予測して予防的な治療を行う)に対するiPS細胞技術の応用も期待されています。
組織幹細胞
私たちの体の中に自然に存在し、働いている幹細胞を組織幹細胞といいます。
例えば、骨髄には造血幹細胞があり、赤血球や白血球などの血液細胞を作っています(多分化能)。その他、皮膚や肝臓など様々な場所で見つかっています。骨折が治るのも、髪の毛を切っても伸びたり、抜けてもまた生えてくるのは、それぞれの場所に存在する組織幹細胞の働き(自己複製能)のおかげです。
例えば、骨髄には造血幹細胞があり、赤血球や白血球などの血液細胞を作っています(多分化能)。その他、皮膚や肝臓など様々な場所で見つかっています。骨折が治るのも、髪の毛を切っても伸びたり、抜けてもまた生えてくるのは、それぞれの場所に存在する組織幹細胞の働き(自己複製能)のおかげです。
間葉系幹細胞の利用価値
幹細胞と言えば、ES細胞やiPS細胞がよく知られています。それらは実験研究用に人工的に作りだされた特殊な細胞です。一方、一般的な幹細胞は人間の成長を支える細胞で、幼少期は大人よりたくさんの幹細胞が存在しています。大人になり、見かけの成長がとまっても幹細胞は存在しており、一生を通して、組織が損傷したときに細胞を補填する働きをします。これらの幹細胞は、組織幹細胞(成体幹細胞・体性幹細胞)と呼ばれています。中でも、骨髄などに存在する造血幹細胞は、半世紀以上前から研究され、臨床応用も活発に行われています。この造血幹細胞移植の治療法確立は、あらゆる組織幹細胞を利用する移植治療の可能性を広げました。しかしながら、組織によっては生体内から幹細胞を分離することが困難で、治療に用いることが難しいものもあります。例えば、脳や心臓などの組織幹細胞がそれにあたります。
そこで注目されるのが間葉系幹細胞です。間葉系幹細胞は、発生過程で中胚葉から分化する脂肪や骨にすることができ、その上、成人の骨髄、脂肪組織や歯髄などから比較的容易に得ることができます。
これまでの研究で、間葉系幹細胞は中胚葉系の骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞などだけではなく内胚葉系の内臓組織や外胚葉系の神経などの細胞にも分化する能力を持つことがわかりました。
また近年、間葉系幹細胞が免疫抑制作用を持つことや腫瘍に集積する性質があることが報告され、間葉系幹細胞を移植後の拒絶防止に利用する研究や、がんの遺伝子治療薬の運び屋として利用する研究が行われています。
さらに間葉系幹細胞は、組織エンジニアリングという分野でも利用研究が進められています。組織エンジニアリングが目指すものは、「①細胞②足場③栄養」を適切に組み合わせて3次元の人工臓器や組織を作り出すことです。間葉系幹細胞から分化させた細胞を利用した軟骨細胞シートによる軟骨損傷の治療はすでに行われており、健康保険の適用が認められています。
そこで注目されるのが間葉系幹細胞です。間葉系幹細胞は、発生過程で中胚葉から分化する脂肪や骨にすることができ、その上、成人の骨髄、脂肪組織や歯髄などから比較的容易に得ることができます。
これまでの研究で、間葉系幹細胞は中胚葉系の骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞などだけではなく内胚葉系の内臓組織や外胚葉系の神経などの細胞にも分化する能力を持つことがわかりました。
また近年、間葉系幹細胞が免疫抑制作用を持つことや腫瘍に集積する性質があることが報告され、間葉系幹細胞を移植後の拒絶防止に利用する研究や、がんの遺伝子治療薬の運び屋として利用する研究が行われています。
さらに間葉系幹細胞は、組織エンジニアリングという分野でも利用研究が進められています。組織エンジニアリングが目指すものは、「①細胞②足場③栄養」を適切に組み合わせて3次元の人工臓器や組織を作り出すことです。間葉系幹細胞から分化させた細胞を利用した軟骨細胞シートによる軟骨損傷の治療はすでに行われており、健康保険の適用が認められています。
初臨床応用における組織幹細胞と多能性幹細胞の関係
組織幹細胞は、特定の細胞種に分化する性質を持ちますが、培養皿の中である程度しか増殖しません。治療効果を持つ組織幹細胞を体内から確実に採取でき十分量培養できる場合には、組織幹細胞による細胞療法が有効です。しかし、一般には治療に必要な多くの細胞を得ることができません。組織幹細胞を用いた治療法の中で安全性と有用性が確認されているのは、白血病などの血液腫瘍性疾患に対して造血幹細胞を移植する骨髄移植で、最も研究の進んでいる分野です。
一方で、多能性幹細胞はわたしたちのからだの中のどのような細胞にもなる(分化する)ことができ、培養皿のなかではほぼ無限に増殖します。この性質は、臨床応用を考えた際の適用範囲の広さと供給量という点で大変優れています。
しかしこの細胞を動物にそのまま移植すると、いろいろな細胞に秩序なく分化してテラトーマという腫瘍を形成してしまいます。このため多能性幹細胞を細胞治療に用いる際には、体内での細胞運命の決定の秩序を参考にして、培養器の中で細胞を人為的に分化誘導し、それぞれの治療に必要とされる細胞を注意深く作製しなければなりません。
生体内において、幹細胞の分化は細胞外環境に大きく制御されています。培養器の中でも多能性幹細胞を目的の細胞に分化させるには、生体内環境を再現するよう、培地の成分や培養時間などの培養環境を時空間的に操作制御することが必要となります。
一方で、多能性幹細胞はわたしたちのからだの中のどのような細胞にもなる(分化する)ことができ、培養皿のなかではほぼ無限に増殖します。この性質は、臨床応用を考えた際の適用範囲の広さと供給量という点で大変優れています。
しかしこの細胞を動物にそのまま移植すると、いろいろな細胞に秩序なく分化してテラトーマという腫瘍を形成してしまいます。このため多能性幹細胞を細胞治療に用いる際には、体内での細胞運命の決定の秩序を参考にして、培養器の中で細胞を人為的に分化誘導し、それぞれの治療に必要とされる細胞を注意深く作製しなければなりません。
生体内において、幹細胞の分化は細胞外環境に大きく制御されています。培養器の中でも多能性幹細胞を目的の細胞に分化させるには、生体内環境を再現するよう、培地の成分や培養時間などの培養環境を時空間的に操作制御することが必要となります。
ダイレクトリプログラミング
ダイレクトリプログラミングとは?
受精卵から個体が形成されていく過程は一方向性であり、一度分化した細胞は元の未分化な細胞には戻れない、あるいは他の系列の細胞にはならないと、長年にわたり信じられていました。(受精卵と細胞運命)
しかし最近の研究で細胞の特異的な分化の鍵となる転写因子群を導入することで、体細胞から、多能性幹細胞であるiPS細胞だけでなく、心筋、神経、肝細胞などのさまざまな分化細胞を直接誘導できることがわかってきました。 このように、体細胞から多能性幹細胞を経ずに特異的な分化細胞に直接誘導することは、「ダイレクトリプログラミング」と呼ばれており、基礎研究、創薬、さらには再生医療において、新たな潮流として研究開発が行われています。
ダイレクトリプログラミングを、培養皿のなかではなく、生体内で行う再生医療技術も開発中です。例えば、生体内心筋リプログラミングという、心臓の中の非心筋細胞(線維芽細胞)を直接生体内で心筋に転換することで、心臓再生を目指した研究が国内外で進められています。生体内リプログラミングは、まだ基礎研究の段階にあり、実用化のためには多くの検討が必要でありますが、将来遺伝子治療の一大領域へと発展していく可能性が期待されています。
しかし最近の研究で細胞の特異的な分化の鍵となる転写因子群を導入することで、体細胞から、多能性幹細胞であるiPS細胞だけでなく、心筋、神経、肝細胞などのさまざまな分化細胞を直接誘導できることがわかってきました。 このように、体細胞から多能性幹細胞を経ずに特異的な分化細胞に直接誘導することは、「ダイレクトリプログラミング」と呼ばれており、基礎研究、創薬、さらには再生医療において、新たな潮流として研究開発が行われています。
ダイレクトリプログラミングを、培養皿のなかではなく、生体内で行う再生医療技術も開発中です。例えば、生体内心筋リプログラミングという、心臓の中の非心筋細胞(線維芽細胞)を直接生体内で心筋に転換することで、心臓再生を目指した研究が国内外で進められています。生体内リプログラミングは、まだ基礎研究の段階にあり、実用化のためには多くの検討が必要でありますが、将来遺伝子治療の一大領域へと発展していく可能性が期待されています。
ダイレクトリプログラミングの始まり
1987年、マウスの線維芽細胞にわずか1種類のMyoDという転写因子を導入すると骨格筋細胞に転換されるという現象が報告されました1)。これこそが、転写因子の導入により細胞が別の種類の細胞に変わることを示した、最初のダイレクトリプログラミングといえます。しかしながら、その後はMyoDのように単一の遺伝子で細胞の運命を書き換えられたという報告は少なく、細胞種を転換することは容易ではないと研究者間で考えられていました。
iPS細胞の登場による、爆発的な進展
2006年にiPS細胞が報告されたことで、転写因子を複数組み合わせた”転写因子カクテル”による細胞の運命転換研究が一気に加熱しました。2008年には、膵臓の外分泌細胞からインスリン産生細胞2)や、線維芽細胞からマクロファージ様細胞3)を誘導する転写因子カクテルが報告され、2010年には神経細胞4),5)や心筋細胞6)などが線維芽細胞から誘導できるようになりました。
2):Zhou, Q., Brown, J., Kanarek, A., Rajagopal, J. & Melton, D. A. In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to beta-cells. Nature 455, 627-632, doi:10.1038/nature07314 (2008).
3):Feng, R. et al. PUA and C/EBP alpha/beta convert fibroblasts into macrophage-like cells. P Natl Acad Sci USA 105, 6057-6062, doi:10.1073/pnas.0711961105 (2008).
4):Vierbuchen, T. et al. Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature 463, 1035-U1050, doi:10.1038/nature08797 (2010).
5):Heinrich, C. et al. Directing Astroglia from the Cerebral Cortex into Subtype Specific Functional Neurons. Plos Biology 8, doi:ARTN e1000373 10.1371/journal.pbio.1000373 (2010).
6):Ieda, M. et al. Direct Reprogramming of Fibroblasts into Functional Cardiomyocytes by Defined Factors. Cell 142, 375-386, doi:10.1016/j.cell.2010.07.002 (2010).
2):Zhou, Q., Brown, J., Kanarek, A., Rajagopal, J. & Melton, D. A. In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to beta-cells. Nature 455, 627-632, doi:10.1038/nature07314 (2008).
3):Feng, R. et al. PUA and C/EBP alpha/beta convert fibroblasts into macrophage-like cells. P Natl Acad Sci USA 105, 6057-6062, doi:10.1073/pnas.0711961105 (2008).
4):Vierbuchen, T. et al. Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature 463, 1035-U1050, doi:10.1038/nature08797 (2010).
5):Heinrich, C. et al. Directing Astroglia from the Cerebral Cortex into Subtype Specific Functional Neurons. Plos Biology 8, doi:ARTN e1000373 10.1371/journal.pbio.1000373 (2010).
6):Ieda, M. et al. Direct Reprogramming of Fibroblasts into Functional Cardiomyocytes by Defined Factors. Cell 142, 375-386, doi:10.1016/j.cell.2010.07.002 (2010).
発展するリプログラミング研究
現在では、転写因子カクテルのみならず、microRNAと呼ばれる細胞内で遺伝子発現を制御している因子や、化合物を組み合わせることによるリプログラミング研究も成されており、iPS細胞の登場前である10年前からは想像もできないほど、様々な方法によって多様な細胞を得る事ができるようになってきました7)。今後も再生医療や創薬への応用を目指し、”より多様な”
”より高効率な” ”より簡便な” ”より安全な” など様々なテーマを掲げたダイレクトリプログラミングの研究が盛んに行われるものと考えられます。
7):Xu, J., Du, Y. Y. & Deng, H. K. Direct Lineage Reprogramming: Strategies, Mechanisms, and Applications. Cell Stem Cell 16, 119-134, doi:10.1016/j.stem.2015.01.013 (2015).
7):Xu, J., Du, Y. Y. & Deng, H. K. Direct Lineage Reprogramming: Strategies, Mechanisms, and Applications. Cell Stem Cell 16, 119-134, doi:10.1016/j.stem.2015.01.013 (2015).
幹細胞の歴史
幹細胞の歴史 ~iPS細胞のできるまで~
山中教授らによって誕生したiPS細胞は、突然のひらめきから生まれたものではありません。
生物の「発生」の研究は古代ギリシアから行われていて、iPS細胞は世界中の科学者が長い年月をかけて行ってきた「発生」や「再生」の研究を基にして発見されました。
ここではiPS細胞誕生までの幹細胞研究の発展の歴史を簡単にご紹介します。
再生医療と幹細胞
幹細胞移植の特徴と現状
幹細胞移植とは?
現在、臨床で行われている幹細胞移植と言えば造血幹細胞移植のことを指します。造血幹細胞は、末梢血、骨髄、そして臍帯血から得ることができます。造血幹細胞は、赤血球、白血球、血小板など、体が必要とする多様な種類の血液細胞を作ることのできる細胞です。この細胞を体の外へ取り出し、患者さんに点滴で移植します。
造血幹細胞は、これらの血液の細胞を作るだけでなく、移植された人の造血幹細胞を新しく作り出す能力があり、恒常的に造血システムを維持することができます。
造血幹細胞移植と同じように血液成分を体内に入れる治療で輸血があります。輸血は一時的に血液細胞を供給できるのに対し、造血幹細胞移植は長期にわたって血液細胞を供給する、という点に違いがあります。詳しく説明すると、輸血では不足した赤血球、白血球、血小板などを即座に補うことができますが、それらの細胞が寿命を迎えると新たに輸血する必要があります。一方で、造血幹細胞移植では、造血幹細胞が体内で生着し血液細胞を作るまでの時間は必要ですが、その後は血液細胞を作り続けます。このように、幹細胞は体内で持続的に機能できるという特徴があり、それが治療上の大きな効果を発揮します。
造血幹細胞は、これらの血液の細胞を作るだけでなく、移植された人の造血幹細胞を新しく作り出す能力があり、恒常的に造血システムを維持することができます。
造血幹細胞移植と同じように血液成分を体内に入れる治療で輸血があります。輸血は一時的に血液細胞を供給できるのに対し、造血幹細胞移植は長期にわたって血液細胞を供給する、という点に違いがあります。詳しく説明すると、輸血では不足した赤血球、白血球、血小板などを即座に補うことができますが、それらの細胞が寿命を迎えると新たに輸血する必要があります。一方で、造血幹細胞移植では、造血幹細胞が体内で生着し血液細胞を作るまでの時間は必要ですが、その後は血液細胞を作り続けます。このように、幹細胞は体内で持続的に機能できるという特徴があり、それが治療上の大きな効果を発揮します。
幹細胞移植の方法
患者さんの正常な造血幹細胞を事前に採取し、治療などの後に患者さん自身の体に戻します。自分自身の血液なので、免疫による拒絶反応は起きません。
B. 別の人の幹細胞を自分に移植する(他家移植(同種移植))
他の人の造血幹細胞を移植します。具体的には、他人から採取した骨髄や末梢血から得られた幹細胞、或いは臍帯血を点滴で移植します。
幹細胞移植の適合性
iPS細胞移植について
また、患者さん自身のiPS細胞から、目的の細胞を作れば自家移植による治療ができ、拒絶反応も起こらないと考えられています。しかし、実際には莫大な費用と時間がかかり、すべての患者さんが適切な治療を受けられるとは限りません。そこで、日本人に多いHLA型のiPS細胞を作製し、ストックする計画が進められています。75名のiPS細胞で、日本人の80%のHLA型に対応するiPS細胞が供給できると計算されています。
京都大学医学部付属病院 iPS細胞臨床開発部
くすりとiPS細胞
くすりとiPS細胞
そのためには、最初に疾病に作用する化学物質を見つけ出すこと(基礎研究)が重要です。具体的には病態を培養皿の中で再現した病態モデルを作製し、そのモデルに作用する化学物質の評価、化合物スクリーニングを実施します。このようなプロセスを経て抽出された治療薬候補物質は、次に、動物を用いて有効性と安全性をチェックされます(非臨床試験)。非臨床試験をクリアした治療薬候補は、健常もしくは患者さんでの有効性と安全性確認(臨床試験)へと移行し、その反応性が良好であれば、薬として承認され(承認申請・製造販売)患者さんの元に届くことになります。
このようにお話しすると薬の開発は簡単そうに聞こえますが、実際はとても難しく、薬の種(タネ)となる新しい化合物の発見から実際に患者さんの手元に届くまで少なくとも20年近くの時間を要し、かかる費用は数百億から数千億円にまで達します。しかしながら、長い期間と莫大な費用をかければ成功確率が上がるとも限らず、治療薬候補が実際に薬となる確率は0.001%前後と極めて低いのが現状です。このような状況は年々深刻になっており、できてくる新しい薬の数も減少しています。
それでは、こういった疾患はなぜ治すのが難しいのでしょうか。それは、従来の技術では病態自体を明らかにするのが困難で、明確な病態モデル・薬効評価モデルが存在しないからです。こういった状況を打破する最後の砦として近年大いに着目されているのが2006年に京都大学の山中教授らが作製した人工多能性幹細胞(iPS細胞)です。患者さん由来の組織もしくは細胞からiPS細胞を作製し、病変がみられる部位の細胞へと誘導することで、患者さんが保有する遺伝情報を反映した病態モデル細胞の作製が可能となります。こういった疾患特異的iPS細胞技術を駆使することで、通常ならば採取困難な部位の患者由来細胞を作製、また病態進行を培養皿の中で追うことが可能となり、上述したような難病の病態解明への足掛かりとなります。
さらには患者由来iPS細胞を用いた病態モデルは、既存の他のモデルと比較して病態をより正確に反映していることから治療薬創出に向けた有用なツールにもなります。対象となる疾患もこれまで開発に着手されていない領域の疾患であることからiPS細胞技術を駆使した創薬研究は、患者さんはもちろん製薬会社も大いに注目しています。
1.病気を再現します(基礎研究)
患者由来のiPS細胞を病変がみられる組織の細胞へと分化誘導することで、その病気のより正確な病態を再現します。
2.効果があるのか確かめます(基礎研究・非臨床試験)
iPS細胞を用いた病態モデルの細胞は治療薬候補化合物の選別にも大いに力を発揮します。より正確な病態モデルであるからこそ治療効果が見込める治療薬候補を高精度に抽出可能となります。
3.安全性を確かめます(非臨床試験)
iPS細胞を用いた病態モデルの細胞は毒性評価・副作用評価にも役立ちます。特に、従来の系では、その作用を調べることが難しかった脳への毒性・副作用評価系として期待されています。
早わかり細胞研究
細胞を培養するってどういうこと?
動物であれ植物であれ、命あるものは細胞から成り立っています。「細胞を培養する」とは、一言で言うと、細胞を生物から取り出し、生体外で生かし続けることです。細胞を培養するには、その細胞を取り出す前の環境に近づけるのが最良と考えられています。
古くは19世紀から、世界中の研究者の多大な努力によって、動物・植物・菌・バクテリアなど様々な種の生物の、多様な細胞の培養法が確立されてきました。
動物細胞の培養は、培養中の細胞に様々な処置を加え、生物「個体」レベルでは見ることが難しい細胞への影響を細かく見ることができるため、疾患研究・創薬研究にとても有用です。
また、一部の動物細胞はウイルス研究のためにも用いられています。ウイルスは自身のみでは増殖することができませんが、宿主となる細胞に感染させ、制御された条件下で増殖させることができるため、抗ウイルス薬の創製やワクチンの開発に有用です。(もちろん、実験者はウイルスの取扱いに最新の注意を払わなければいけません)
細胞を培養するためには、まずはそれぞれの培養に適した温度・湿度・気体組成を整えることが重要となります。どこの研究施設でも、細胞はインキュベーター(培養器)と呼ばれる機械の中で培養されます。インキュベーターとは、空気調整機能付きの保温器です。
ヒトやマウスなどの哺乳類の細胞の培養では、一般的にインキュベーターの温度を37℃に設定し、中に水受け皿を入れて湿度を約95%に保ちます。
また、インキュベーターとボンベをホースでつなぎ、空気組成を調整します。
一般的には5~20% O2、5~10% CO2に設定しますが、これは培養する細胞株によって異なります。例えばヒトiPS細胞の場合、20% O2・3~5% CO2で培養する方法が一般的です。
古くは19世紀から、世界中の研究者の多大な努力によって、動物・植物・菌・バクテリアなど様々な種の生物の、多様な細胞の培養法が確立されてきました。
動物細胞の培養は、培養中の細胞に様々な処置を加え、生物「個体」レベルでは見ることが難しい細胞への影響を細かく見ることができるため、疾患研究・創薬研究にとても有用です。
また、一部の動物細胞はウイルス研究のためにも用いられています。ウイルスは自身のみでは増殖することができませんが、宿主となる細胞に感染させ、制御された条件下で増殖させることができるため、抗ウイルス薬の創製やワクチンの開発に有用です。(もちろん、実験者はウイルスの取扱いに最新の注意を払わなければいけません)
細胞を培養するためには、まずはそれぞれの培養に適した温度・湿度・気体組成を整えることが重要となります。どこの研究施設でも、細胞はインキュベーター(培養器)と呼ばれる機械の中で培養されます。インキュベーターとは、空気調整機能付きの保温器です。
ヒトやマウスなどの哺乳類の細胞の培養では、一般的にインキュベーターの温度を37℃に設定し、中に水受け皿を入れて湿度を約95%に保ちます。
また、インキュベーターとボンベをホースでつなぎ、空気組成を調整します。
一般的には5~20% O2、5~10% CO2に設定しますが、これは培養する細胞株によって異なります。例えばヒトiPS細胞の場合、20% O2・3~5% CO2で培養する方法が一般的です。
細胞培養はいつから始まった?
(細胞培養の歴史~器官培養からiPS細胞まで~)
「細胞培養」とは、原核生物(細菌、古細菌)及び真核生物(動物、植物、菌)を制御された条件下で維持するということを意味します。ここでは、その中でも、「動物細胞の培養」の歴史について重点を置いて説明します。
動物細胞の培養、すなわち動物の体内から取り出した細胞を制御された条件下で維持し続けるということは、19世紀から現在に至るまで、生物学者・医学者にとって大きなテーマとなっています。動物の体外で起こり、外から見えないような変化を顕微鏡下で詳細に観察・解析することで、生物学・医学は大きく発展してきました。
1860~80年代 器官培養の挑戦、等張液の発明
器官培養は、1860年代始めにルートヴィヒ(Carl
Ludwig)が灌流システムを開発し、動物の体外で心臓を生かそうとした研究に起源を発します。1866年、彼はカエルの心臓を血漿中につけて灌流を行うことで、心臓の拍動を記録することに成功し、世界で初めて動物の器官を「体外で活動させる」ことに成功しました。
1878年、フランスのエイエム(Georges Hayem)は、約0.9%の食塩水が血液の代わりになることを発表します。生体と同程度の塩濃度の溶液を用いれば、細胞を急激に収縮および膨張させることなく、形を維持できるという、いわゆる「等張液」の発明でした。
その後1882年に、イギリスのリンガー(Sydney Ringer)はこの0.9%食塩水を、Mg2+、K+、Ca2+も含むものに改良し(現在のリンゲル液)、カエルの心臓を数日間生かすことに成功します。エイエムの用いたNa+とCl-だけでなく、他のイオンも用いることでより「生体内の液体」を再現することに成功し、心臓を生きたまま保つことに成功したのです。
しかし、ただ器官をリンゲル液に入れるだけでは、栄養供給ができず、栄養不足でいずれ死んでしまうという欠点がありました。また、ルートヴィヒのように血漿を用いてもなお、器官への完全な栄養供給は不可能であり、長期培養は難しいということがわかりました。(現在でも、心臓や脳、精巣など、器官培養の試みはありますが、長期に(~1ヶ月)培養することは依然難しいことが知られています。)
1880~1910年代 組織・細胞培養法の確立、成長培地の発明
1885年、ドイツのルー(Wilhelm Roux)は鶏胚の神経節の一部を摘出し、保温したリンゲル液中で数日間生かすことに成功しました。動物において、器官より小さい構成単位である組織培養への道標を示したのです。
その流れを受け、1907年アメリカのロス・グランビル・ハリソン(Ross Granville Harrison)はカエルの凝固リンパ球を加えたリンゲル液でカエルの神経組織を数週間に渡って維持し、神経突起の成長を観察することに成功しました。ハリソンによって、初めて、栄養を供給しつつ組織を維持し、細胞の成長が動物の体外で確認できたのです。これが、組織培養、及び細胞培養の始まりでした。また、彼の考案した凝固リンパ球を加えた等張液は、細胞の成長を促す培養液、すなわち成長培地(Growth Medium)の初めての作製例でもありました。
今や「細胞培養の父」と呼ばれるハリソンの成功によって、「器官」ではなく「組織」・「細胞」であれば凝固リンパ球培地で数週間の安定的な培養が可能であることがわかると、ハリソンと同様の凝固リンパ球培地を用いた組織培養が世界各地でスタートしました。
1907年、フランスのジョリー(Justin Marie Jolly)はHanging-drop法を用いて、凝固リンパ球培地でトカゲの白血球を培養し、初めて培養下で細胞分裂を観察することに成功しました。
1910年、アメリカのバロウ(Montrose Thomas Burrows)は、同じ研究室のキャレル(Alexis Carrel)と協力してハリソンの組織培養法を改良し、鶏胚エキスや血漿を組織培養時の培地に添加することで、凝固リンパ球を用いた場合よりも組織の成長が促進されることを報告しました。彼らは、自ら改良を行ったこの培地を用いて、鶏胚から採取した細胞を培養し、細胞分裂を観察することに成功しました。
その後、血清を用いても、細胞を良好に培養できるということが明らかになってきます。(そのうち牛血清は現在の細胞・組織培養でも広く使われています)
1910~40年代 細胞培養の改良と限界
バロウによる培地の改良以降、培養下で細胞を効率よく増殖させることができるようになりましたが、依然、培養における数々のトラブルは当時の研究者の悩みの種でした。1916年、アメリカのルース(Payton Rous)とジョーンズ(F. S.
Jones)はトリプシンが接着細胞を剥がすのに有効であることを発見し、今まで力学的方法のみに頼っていた、細胞の分離作業に大きな効率化をもたらしました。
1940年、ペニシリンとストレプトマイシンを培地に添加することにより、動物細胞の培養におけるバクテリアのコンタミネーション(汚染)のリスクを大きく減らせることがわかり、細胞培養はさらに容易な技術となりました。
しかしこれらの技術改良をもってしてもなお、細胞を永続的に培養することは不可能でした。
1943年~ 細胞株の樹立
アメリカのゲイ(George Gey)とアール(Wilton
Earle)は、鶏胚エキスと馬血清を用いてマウスの線維芽細胞を安定して培養する系を立ち上げました。その中で彼らは、培養条件を揃えても生き残る細胞と死ぬ細胞が出るのは何故か?という疑問を解消するため、1つ1つの細胞を単離して培養するという実験を行っていました。1943年、アールの部下であったサンフォード(Katherine
Sanford)とライクリー(Gwendolyn Likely)が行った実験中に偶然生まれたL929は、世界で初めてのマウス不死化細胞、いわゆる「細胞株」でした。
本来、生体から取った正常な体細胞(生殖細胞以外の細胞)は、細胞分裂寿命というものが存在し、一定の回数の細胞分裂を行うと分裂能を失ってしまうことが知られています。もちろん分裂しない細胞がすぐ死ぬというわけではありませんが、当時の技術では、分裂を「終えた」細胞を数週間以上維持することは不可能であり、つまり「永続的に培養できる細胞」というものが存在しませんでした。無限の増殖能を持つ細胞としては、大きく分けて幹細胞とガン細胞の2種類が存在します。1943年に行われた実験は、細胞を単離して培養することで、マウス線維芽細胞のうち、偶然培養中にガン化したものを取ってきたということになります。つまり、このガン化マウス線維芽細胞「L929」こそが、人類が最初に手にした永続的に培養できる細胞、すなわち「細胞株」なのです。
1951年~ ヒト細胞株の樹立
ヒトの細胞を数週間維持するという試みは、1907年のハリソンの実験(カエル神経細胞)以降、多くの研究者が競って行いましたが、40年経っても誰も成功しませんでした。そんな閉塞感の中、1951年、アメリカのゲイは、世界初の細胞株であるL929樹立の経験を生かし、世界初のヒト細胞株「HeLa」を樹立することに成功します。「正常でない細胞」の増殖性に目を付けていた彼は、51年の2月、子宮頸がん患者から摘出された病理切片を入手します。そしてこの切片を培養し、世界初のヒト細胞株の樹立に成功しました。この患者はヘンリエッタ・ラックス(Henrietta
Lacks)という30代の黒人女性で、彼は患者の名前をもじってその細胞株に「HeLa」と名付けました。(この患者は同年10月に死亡しており、最後まで自分が世界初の「細胞ドナー」となったことを知らされませんでした)
1954年~ 細胞培養を用いたワクチンの開発
1954年、アメリカのジョナス・ソーク(Jonas Edward
Salk)は51年に樹立されたHeLa細胞を用いて、ポリオウイルスのワクチンを開発しました。培養細胞にポリオウイルスを感染させて増殖させ、それらをホルマリンで不活化し、その抽出物を注射することで、ポリオウイルスにかかったことのない人でも免疫を獲得できるという仕組みです。ワクチン自体はイギリスのエドワード・ジェンナーの天然痘ワクチン(1798年)やフランスのルイ・パスツールの炭疽菌ワクチン(1885年)によって古くから開発されてきましたが、ヒト細胞株の培養は、ワクチン製造開発にも応用できるという新たな道筋を示しました。
1960年~ さらなる細胞株の樹立
1960年以降、CHO細胞(チェイニーズハムスター由来)、S2細胞(ショウジョウバエ由来)、Vero細胞(アフリカミドリザル由来)などの多様な種類の動物の細胞株が樹立され、様々な動物由来の細胞を用いた研究が行われるようになりました。UV照射や癌誘発剤を用いることで、動物から採取した正常な細胞を培養下で効率的にガン化させ、細胞株として樹立することが可能になりました。1980年代の終わり頃に、変異が発生することでガンの原因になる数々の癌遺伝子、また癌抑制遺伝子が同定され、ガンの発生、および細胞株樹立に関わるメカニズムも明らかになってきました。
1964年~ Embryonic carcinoma (EC細胞)の研究と樹立
悪性奇形腫(Teratocarcinoma)という病気があります。この病気は生殖腺で主に発生します。体を構成するすべての細胞の元となる生殖細胞がガン化することが原因で、三胚葉全ての細胞を持った腫瘍(奇形腫)を形成します。そのうち未分化細胞の割合が高いものを悪性奇形腫と呼びます。
1964年、アメリカのクラインスミス(Lewis J. Kleinsmith)とピアース(G. Barry Pierce)はマウスの1~7.5日胚を子宮から摘出し、子宮以外に移植することで、マウスにおいてTeratocarcinomaを誘導しました。誘導したTeratocarcinomaの一部を採取して培養してみると、無限の増殖性を持ち、細胞株として樹立することができました。彼らはマウス胚に由来するこの細胞株を、胚性がん腫細胞 Embryonic Carcinoma cell (EC cell)と名付けました。彼らは、このEC細胞は胚性幹細胞が腫瘍化したものであると考えたのです。
その後の1974年、アメリカのブリンスター(R. L. Brinster)は、EC細胞をマウスの胚盤胞に注入することで、生まれたマウスの体細胞に、注入したEC細胞由来のものが含まれている、つまりキメラマウスが作製できることを示しました。
1977年にはイギリスのホーガン(B. Hogan)によってヒトのEC細胞が悪性奇形腫から樹立されましたが、細胞の表面抗原、および適切な培養条件がマウスEC細胞と異なることが示唆されました。
マウスEC細胞は、初めて樹立された幹細胞でしたが、樹立過程で既にガン化しており、上述の定義では、「ガン細胞」と「幹細胞」の合いの子のような存在といえます。
1981年~ Embryonic stem cell (ES細胞)の研究と樹立
EC細胞は、樹立した細胞を動物個体に戻すと体細胞として寄与できることに非常に新規性がありましたが、寄与率の低さや、キメラマウスで腫瘍が頻発することなどから正常な状態であるとは言えず、「正常な」幹細胞の熾烈な樹立競争が行われました。
その結果、1981年7月にイギリスのエヴァンズ(M.J.Evans)が、また同年9月にアメリカのマーティン(Gail R. Martin)が、ほぼ同様の方法を用いてマウスの胚盤胞から胚性幹細胞Embryonic Stem cell (ES cell)を樹立したことを発表します。
この細胞は、in vitroにおける各胚葉への分化能はもちろんのこと、キメラマウスの作製においても大きなツールとなっており、現在でも広く使われています。 その後、1998年にはアメリカのトムソン(James A. Thomson)によってヒトのES細胞も樹立されました。
2006年~ induced Pluripotent Stem cell (iPS細胞)の研究
ES細胞は胚から樹立された胚性幹細胞であり、癌遺伝子・癌抑制遺伝子の変異を伴わない無限の増殖性を持ち、三胚葉全てへの分化能を持つことから、次世代の細胞リソースとしての期待が持たれていました。しかし、ES細胞を作製する場合は受精卵を用いるため、倫理的な問題や、また細胞移植で用いる場合の免疫拒絶のリスクが存在しました。2006年、日本の山中らは、ES細胞において特異的に発現する転写因子のうち、線維芽細胞に発現させることでES
-likeな状態を作り出せる転写因子を探索し、Oct4, Sox2, Klf4, c-Mycの4つの転写因子を同定したことを発表しました。そして、この転写因子の発現によって誘導されたES-likeな細胞を、iPS細胞 (induced
Pluripotent Stem Cell)と名付けました。さらに翌2007年には、山中らがOCT4, SOX2, KLF4, C-MYC、トムソンらがOCT4, SOX2, LIN28,
NANOGを用いて、ともにヒトの線維芽細胞から、ヒトのiPS細胞の樹立に成功したことを発表しました。
転写因子の強制発現による分化誘導は、アメリカのワイントローブ(Harold M. Weintraub)による転写因子MyoDの強制発現による筋芽細胞の誘導(1987)などの先行報告がありました。現在はiPS細胞だけでなく、様々な種の細胞を転写因子の発現で直接誘導する、ダイレクトリプログラミングの研究も盛んに行われています。
動物細胞の培養、すなわち動物の体内から取り出した細胞を制御された条件下で維持し続けるということは、19世紀から現在に至るまで、生物学者・医学者にとって大きなテーマとなっています。動物の体外で起こり、外から見えないような変化を顕微鏡下で詳細に観察・解析することで、生物学・医学は大きく発展してきました。
1878年、フランスのエイエム(Georges Hayem)は、約0.9%の食塩水が血液の代わりになることを発表します。生体と同程度の塩濃度の溶液を用いれば、細胞を急激に収縮および膨張させることなく、形を維持できるという、いわゆる「等張液」の発明でした。
その後1882年に、イギリスのリンガー(Sydney Ringer)はこの0.9%食塩水を、Mg2+、K+、Ca2+も含むものに改良し(現在のリンゲル液)、カエルの心臓を数日間生かすことに成功します。エイエムの用いたNa+とCl-だけでなく、他のイオンも用いることでより「生体内の液体」を再現することに成功し、心臓を生きたまま保つことに成功したのです。
しかし、ただ器官をリンゲル液に入れるだけでは、栄養供給ができず、栄養不足でいずれ死んでしまうという欠点がありました。また、ルートヴィヒのように血漿を用いてもなお、器官への完全な栄養供給は不可能であり、長期培養は難しいということがわかりました。(現在でも、心臓や脳、精巣など、器官培養の試みはありますが、長期に(~1ヶ月)培養することは依然難しいことが知られています。)
その流れを受け、1907年アメリカのロス・グランビル・ハリソン(Ross Granville Harrison)はカエルの凝固リンパ球を加えたリンゲル液でカエルの神経組織を数週間に渡って維持し、神経突起の成長を観察することに成功しました。ハリソンによって、初めて、栄養を供給しつつ組織を維持し、細胞の成長が動物の体外で確認できたのです。これが、組織培養、及び細胞培養の始まりでした。また、彼の考案した凝固リンパ球を加えた等張液は、細胞の成長を促す培養液、すなわち成長培地(Growth Medium)の初めての作製例でもありました。
今や「細胞培養の父」と呼ばれるハリソンの成功によって、「器官」ではなく「組織」・「細胞」であれば凝固リンパ球培地で数週間の安定的な培養が可能であることがわかると、ハリソンと同様の凝固リンパ球培地を用いた組織培養が世界各地でスタートしました。
1907年、フランスのジョリー(Justin Marie Jolly)はHanging-drop法を用いて、凝固リンパ球培地でトカゲの白血球を培養し、初めて培養下で細胞分裂を観察することに成功しました。
1910年、アメリカのバロウ(Montrose Thomas Burrows)は、同じ研究室のキャレル(Alexis Carrel)と協力してハリソンの組織培養法を改良し、鶏胚エキスや血漿を組織培養時の培地に添加することで、凝固リンパ球を用いた場合よりも組織の成長が促進されることを報告しました。彼らは、自ら改良を行ったこの培地を用いて、鶏胚から採取した細胞を培養し、細胞分裂を観察することに成功しました。
その後、血清を用いても、細胞を良好に培養できるということが明らかになってきます。(そのうち牛血清は現在の細胞・組織培養でも広く使われています)
1940年、ペニシリンとストレプトマイシンを培地に添加することにより、動物細胞の培養におけるバクテリアのコンタミネーション(汚染)のリスクを大きく減らせることがわかり、細胞培養はさらに容易な技術となりました。
しかしこれらの技術改良をもってしてもなお、細胞を永続的に培養することは不可能でした。
本来、生体から取った正常な体細胞(生殖細胞以外の細胞)は、細胞分裂寿命というものが存在し、一定の回数の細胞分裂を行うと分裂能を失ってしまうことが知られています。もちろん分裂しない細胞がすぐ死ぬというわけではありませんが、当時の技術では、分裂を「終えた」細胞を数週間以上維持することは不可能であり、つまり「永続的に培養できる細胞」というものが存在しませんでした。無限の増殖能を持つ細胞としては、大きく分けて幹細胞とガン細胞の2種類が存在します。1943年に行われた実験は、細胞を単離して培養することで、マウス線維芽細胞のうち、偶然培養中にガン化したものを取ってきたということになります。つまり、このガン化マウス線維芽細胞「L929」こそが、人類が最初に手にした永続的に培養できる細胞、すなわち「細胞株」なのです。
1964年、アメリカのクラインスミス(Lewis J. Kleinsmith)とピアース(G. Barry Pierce)はマウスの1~7.5日胚を子宮から摘出し、子宮以外に移植することで、マウスにおいてTeratocarcinomaを誘導しました。誘導したTeratocarcinomaの一部を採取して培養してみると、無限の増殖性を持ち、細胞株として樹立することができました。彼らはマウス胚に由来するこの細胞株を、胚性がん腫細胞 Embryonic Carcinoma cell (EC cell)と名付けました。彼らは、このEC細胞は胚性幹細胞が腫瘍化したものであると考えたのです。
その後の1974年、アメリカのブリンスター(R. L. Brinster)は、EC細胞をマウスの胚盤胞に注入することで、生まれたマウスの体細胞に、注入したEC細胞由来のものが含まれている、つまりキメラマウスが作製できることを示しました。
1977年にはイギリスのホーガン(B. Hogan)によってヒトのEC細胞が悪性奇形腫から樹立されましたが、細胞の表面抗原、および適切な培養条件がマウスEC細胞と異なることが示唆されました。
マウスEC細胞は、初めて樹立された幹細胞でしたが、樹立過程で既にガン化しており、上述の定義では、「ガン細胞」と「幹細胞」の合いの子のような存在といえます。
その結果、1981年7月にイギリスのエヴァンズ(M.J.Evans)が、また同年9月にアメリカのマーティン(Gail R. Martin)が、ほぼ同様の方法を用いてマウスの胚盤胞から胚性幹細胞Embryonic Stem cell (ES cell)を樹立したことを発表します。
この細胞は、in vitroにおける各胚葉への分化能はもちろんのこと、キメラマウスの作製においても大きなツールとなっており、現在でも広く使われています。 その後、1998年にはアメリカのトムソン(James A. Thomson)によってヒトのES細胞も樹立されました。
転写因子の強制発現による分化誘導は、アメリカのワイントローブ(Harold M. Weintraub)による転写因子MyoDの強制発現による筋芽細胞の誘導(1987)などの先行報告がありました。現在はiPS細胞だけでなく、様々な種の細胞を転写因子の発現で直接誘導する、ダイレクトリプログラミングの研究も盛んに行われています。
赤い液体は何?
細胞培養で用いる赤い液体は、「培地」と呼び、この液の中に細胞を漬け、インキュベーター内で温度・湿度・空気組成を保って細胞を培養します。
現在使われている培地の多くは、1959年にEagle博士により発表された(イーグル最小必須培地(Eagle's minimal essential medium:EMEM))をベースとしています。
EMEMは人工的に塩・アミノ酸・糖(グルコース)・ビタミンを混ぜた液体であり、細胞と等張なので細胞に浸透圧のダメージを与えず、かつ細胞に最低限の栄養を供給します。
EMEMは本来赤くありません。ではなぜ「赤い液体」なのかというと、フェノールレッドというpH指示薬が添加されるのが一般的だからです。
一般的に多くの細胞はpH7.0付近、つまり中性の条件を好みます。フェノールレッドを入れることで、現在の培地が細胞に適したpHなのかを一目で判断でき、いつ培地交換をすればいいのかが分かります。
フェノールレッドはpH7.0付近では赤色ですが、酸性寄りになると黄色に、アルカリ性寄りになると赤紫色に変色します。
培地の色が黄色、つまり酸性寄りの場合は、ほとんどの場合は培地内の細胞が多すぎて、その代謝物(乳酸など)が多く培地中に放出されることが原因です。また、カビやバクテリアなどのコンタミネーションが発生した場合にも、それらの微生物が増殖して代謝物を放出し、培地が黄色くなります。
培地の色が赤紫色、つまりアルカリ性の場合は、なんらかの原因によって培養時のCO2濃度が下がっていることが原因です。培地のほとんどはCO2 5%の条件下で中性になるような組成となっていますが、培養時のCO2濃度が低下すると、中性を保てずアルカリ性になります。また、細胞を培養しているプレート・ディッシュをインキュベーターの外に置きすぎると培地がアルカリ性に寄ってしまうので、作業が終わったらすみやかにインキュベーター内に戻すのが肝心です。
現在使われている培地の多くは、1959年にEagle博士により発表された(イーグル最小必須培地(Eagle's minimal essential medium:EMEM))をベースとしています。
EMEMは人工的に塩・アミノ酸・糖(グルコース)・ビタミンを混ぜた液体であり、細胞と等張なので細胞に浸透圧のダメージを与えず、かつ細胞に最低限の栄養を供給します。
EMEMは本来赤くありません。ではなぜ「赤い液体」なのかというと、フェノールレッドというpH指示薬が添加されるのが一般的だからです。
一般的に多くの細胞はpH7.0付近、つまり中性の条件を好みます。フェノールレッドを入れることで、現在の培地が細胞に適したpHなのかを一目で判断でき、いつ培地交換をすればいいのかが分かります。
フェノールレッドはpH7.0付近では赤色ですが、酸性寄りになると黄色に、アルカリ性寄りになると赤紫色に変色します。
培地の色が黄色、つまり酸性寄りの場合は、ほとんどの場合は培地内の細胞が多すぎて、その代謝物(乳酸など)が多く培地中に放出されることが原因です。また、カビやバクテリアなどのコンタミネーションが発生した場合にも、それらの微生物が増殖して代謝物を放出し、培地が黄色くなります。
培地の色が赤紫色、つまりアルカリ性の場合は、なんらかの原因によって培養時のCO2濃度が下がっていることが原因です。培地のほとんどはCO2 5%の条件下で中性になるような組成となっていますが、培養時のCO2濃度が低下すると、中性を保てずアルカリ性になります。また、細胞を培養しているプレート・ディッシュをインキュベーターの外に置きすぎると培地がアルカリ性に寄ってしまうので、作業が終わったらすみやかにインキュベーター内に戻すのが肝心です。
その他
SKIP
※2020年2月に一般向けの方向けコンテンツを本サイトへ移管しました。
SKiP(Stem Cell Knowledge & Information Portal)【一般の方向け】
(https://saiseiiryo.jp/skip_archive/)
SKiP(Stem Cell Knowledge & Information Portal)【一般の方向け】
(https://saiseiiryo.jp/skip_archive/)